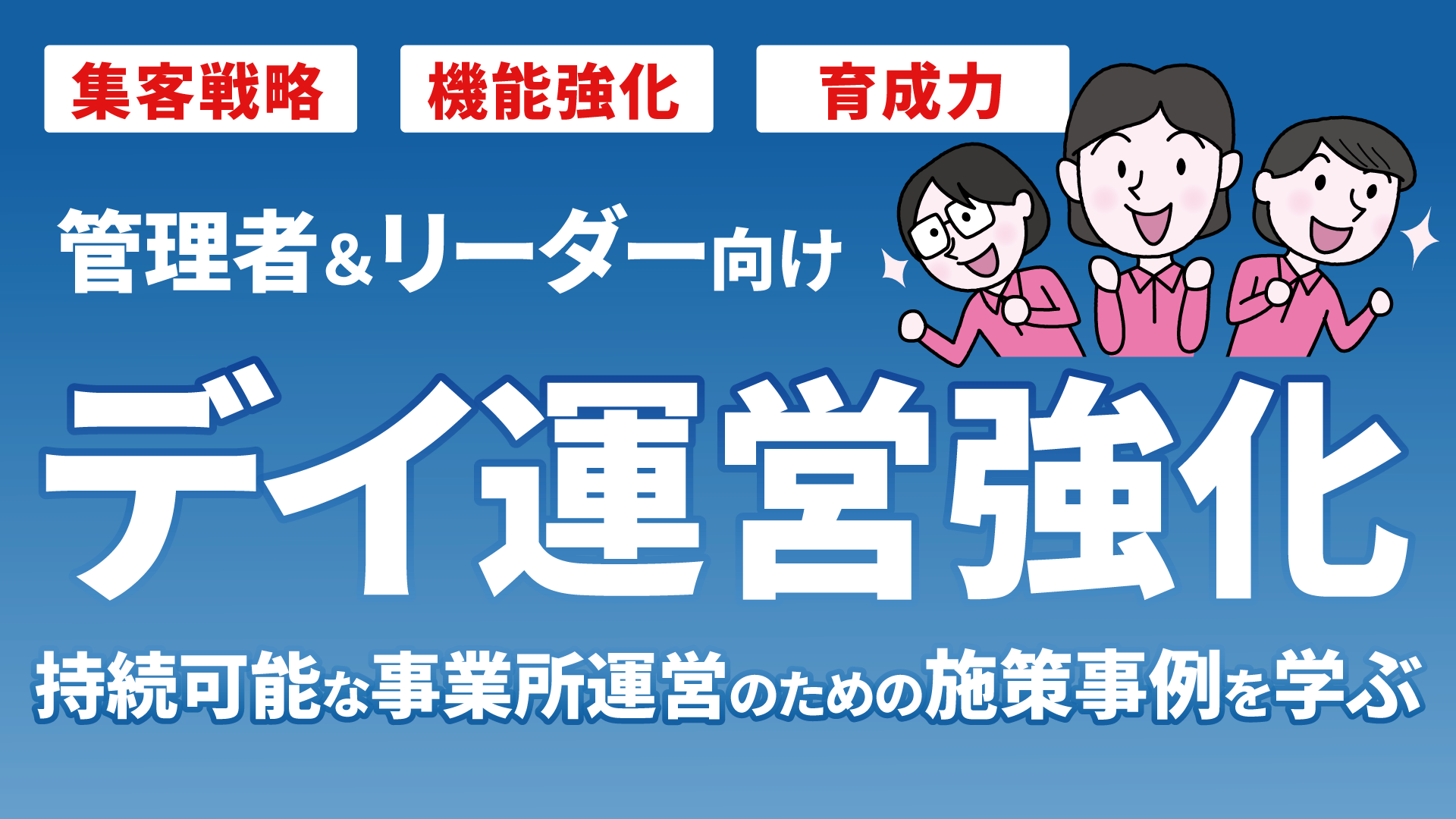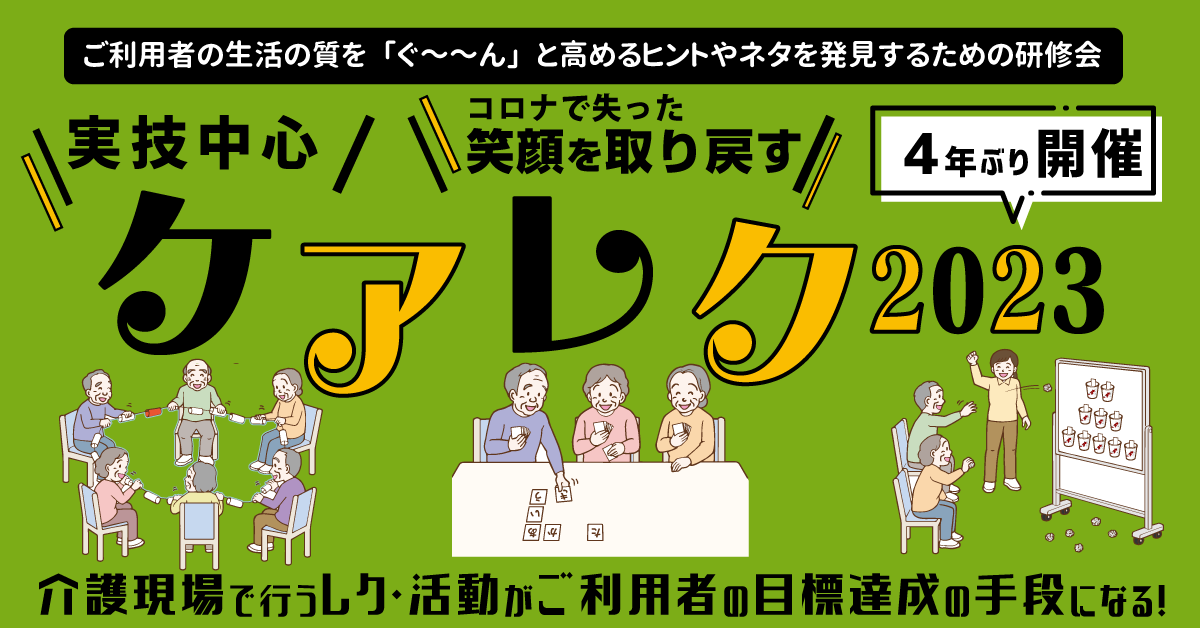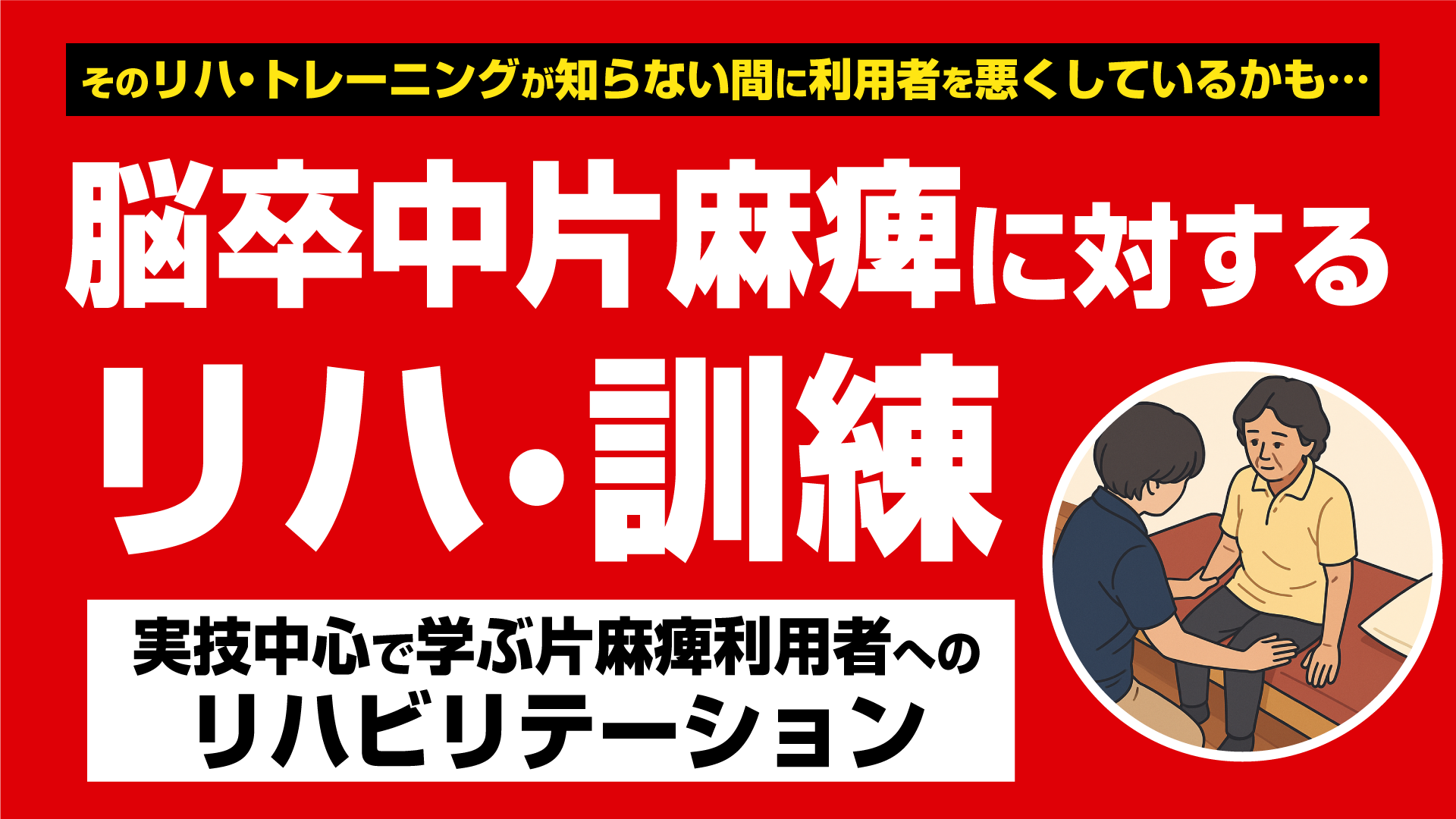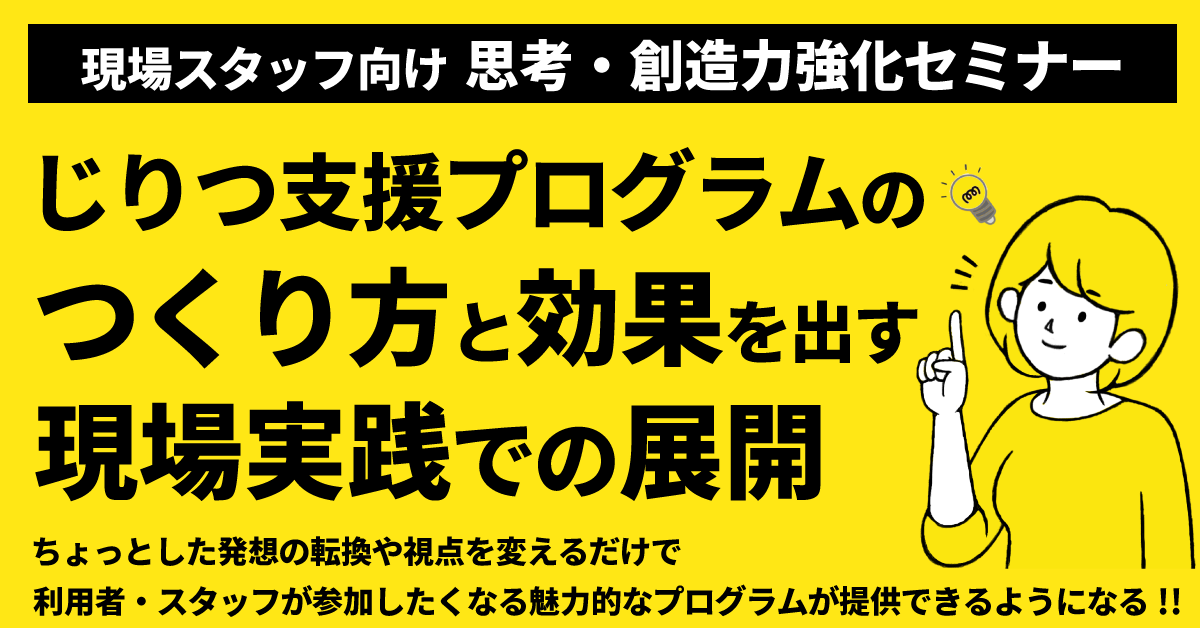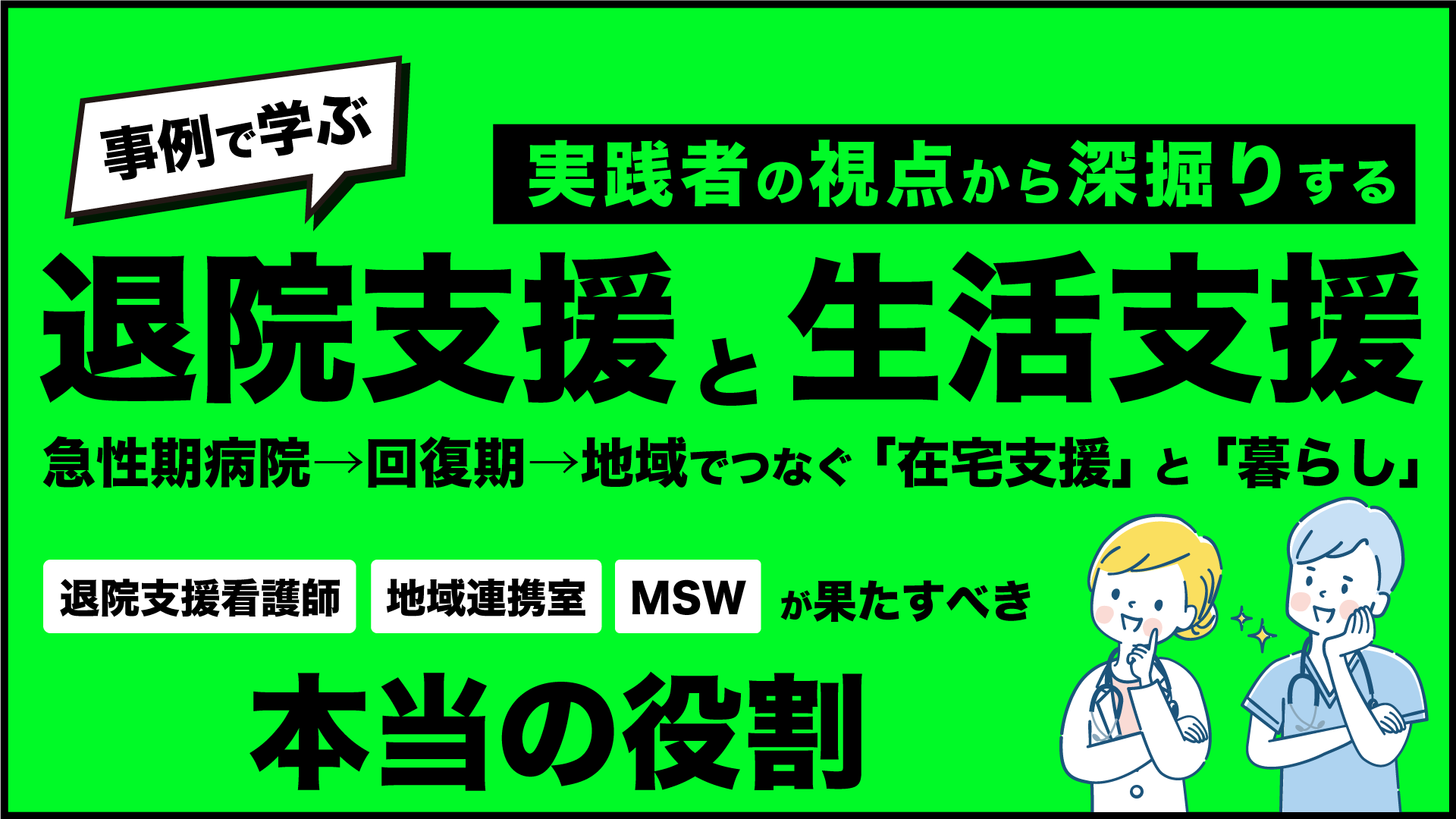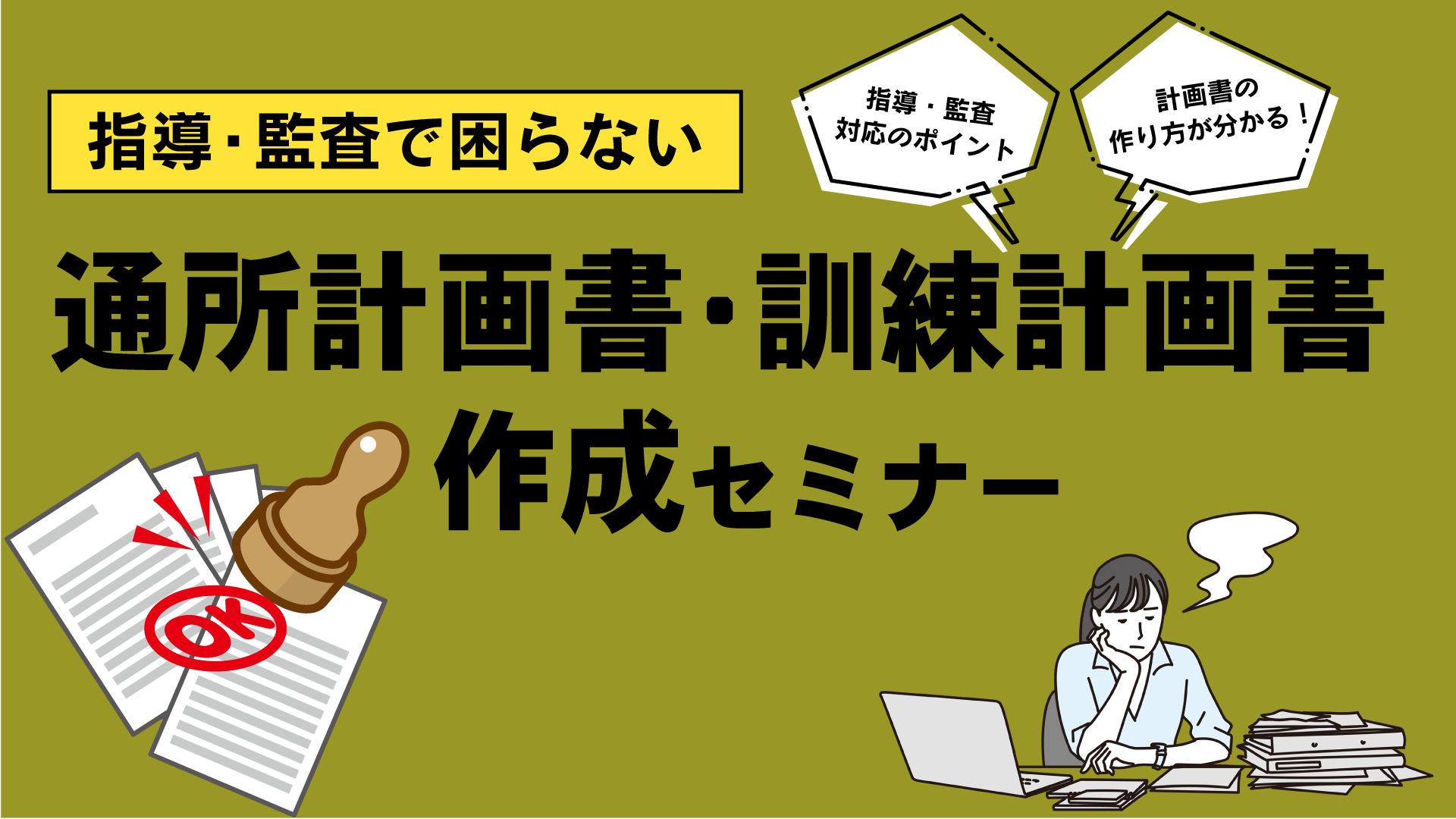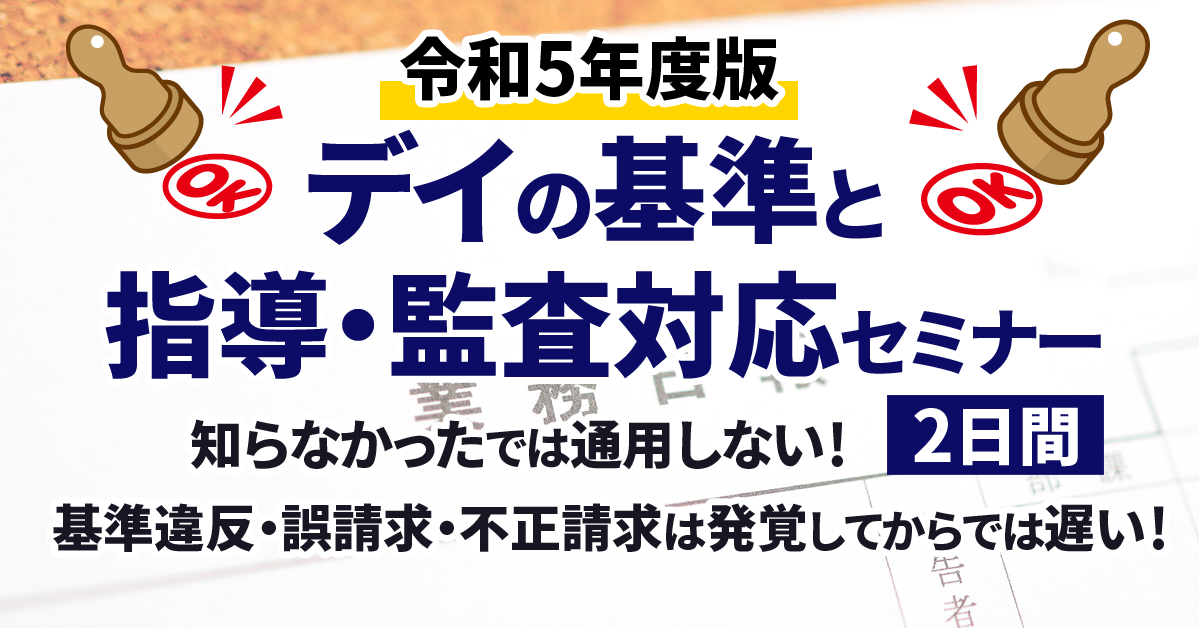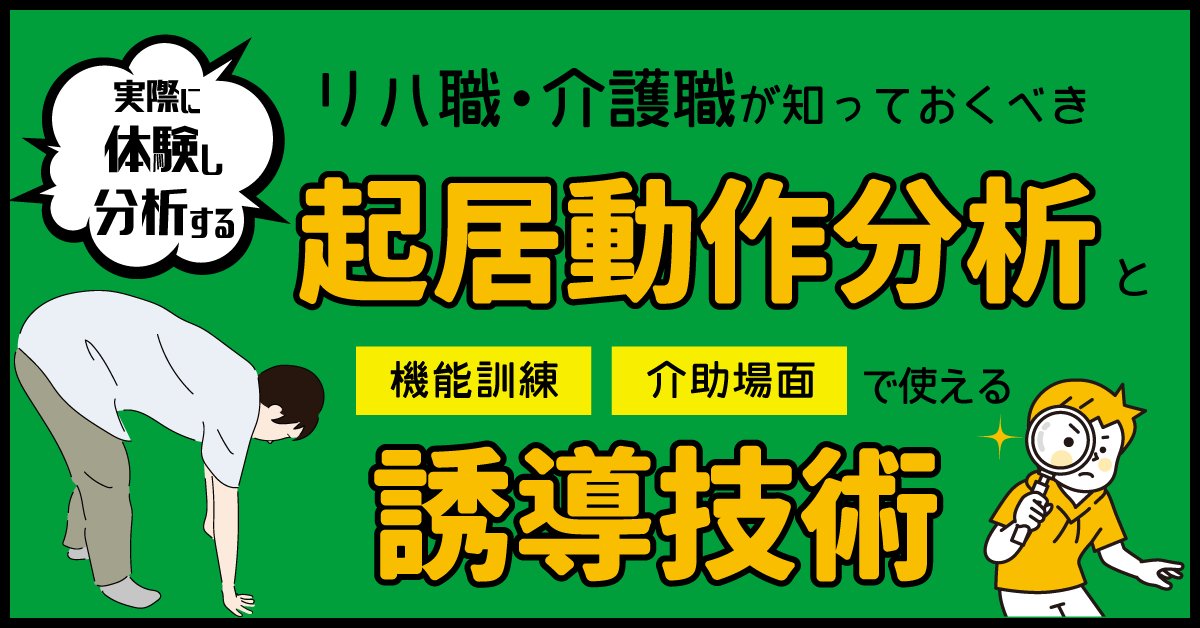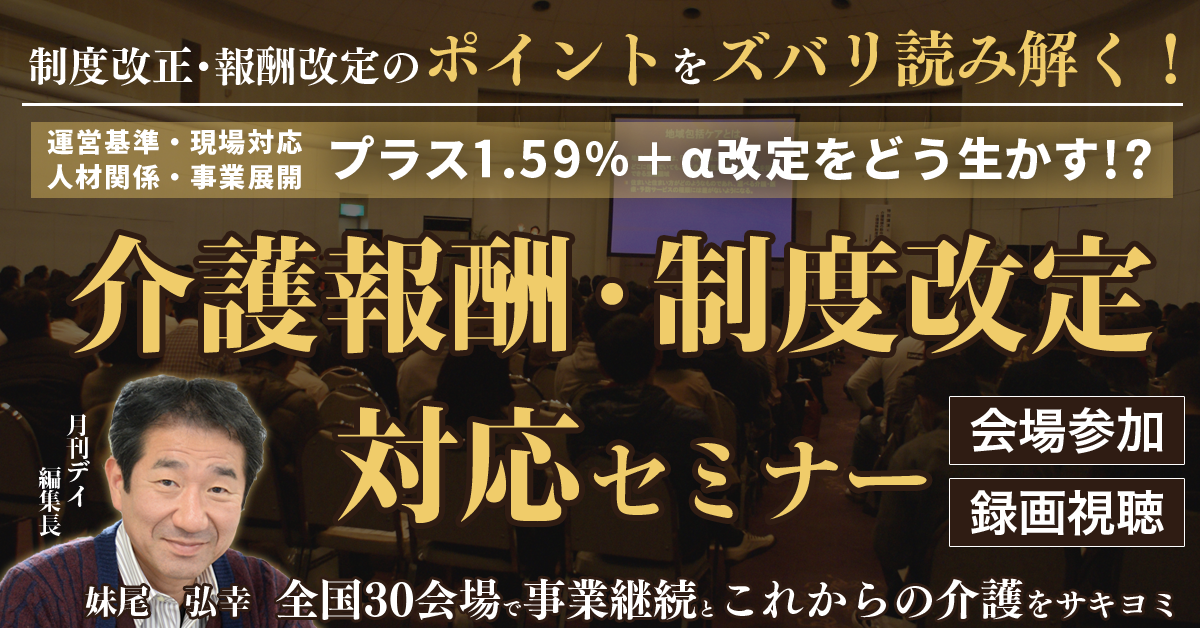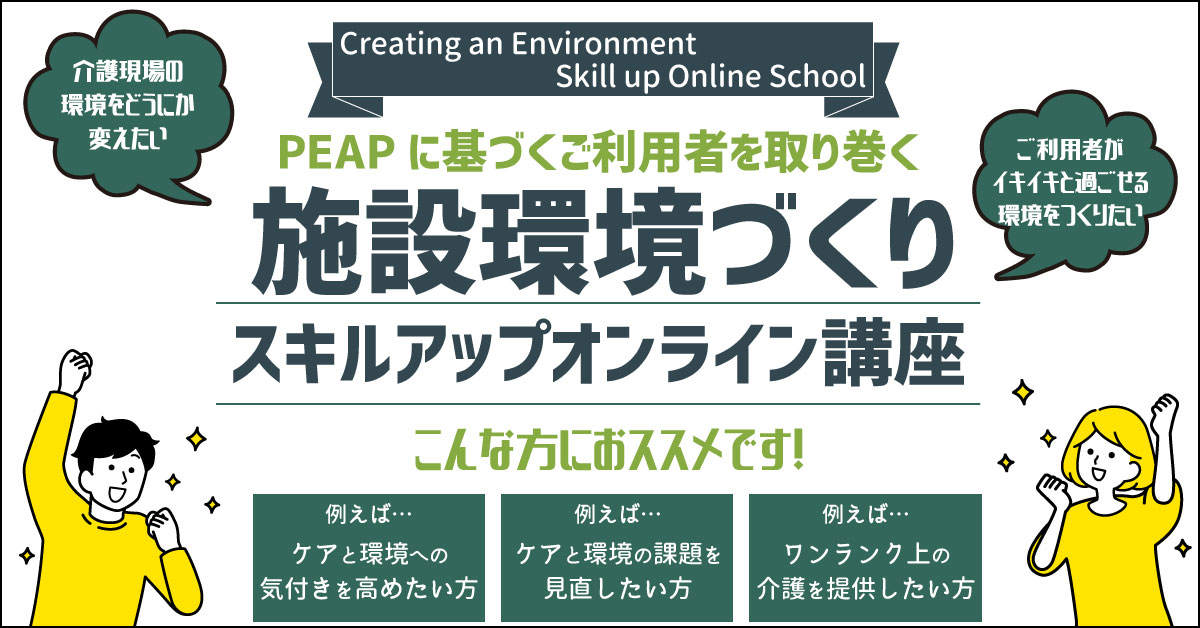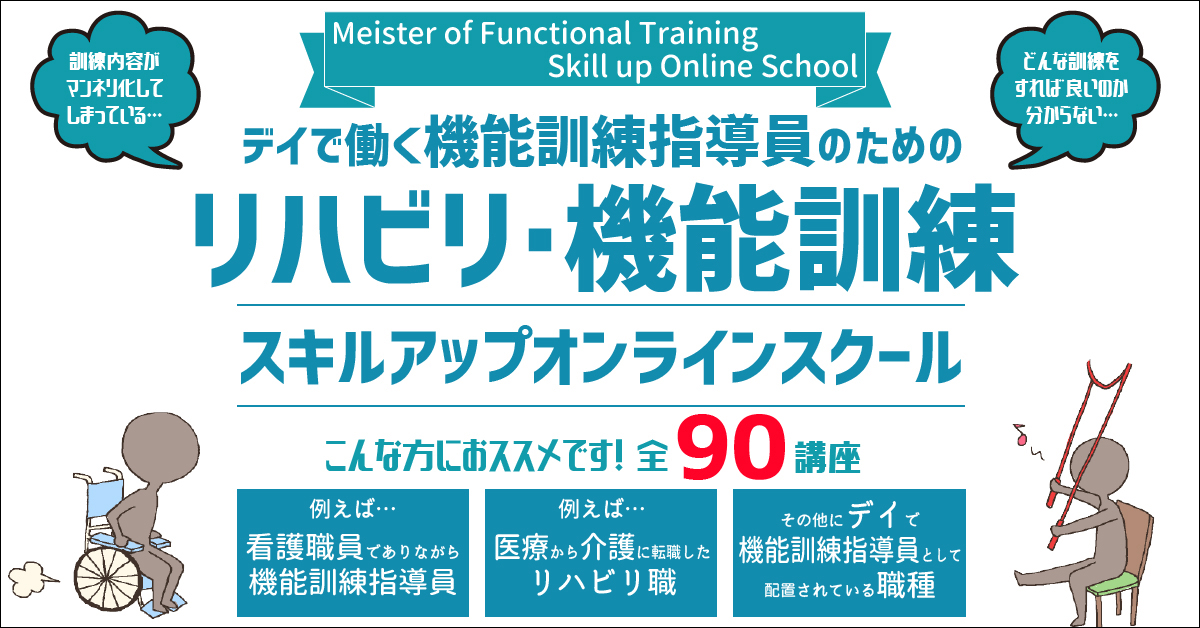レク・アクティビティに込めた想い…人間性を支える「場」づくりとして
介護、福祉、医療の現場で実施されるレク・アクティビティ。
そこには単なる「娯楽」や「気晴らし」とは異なる深い意味と多様な価値が込められています。
これまで、レク・アクティビティを「集団訓練」として位置づけ、身体機能の維持・向上を目指して取り組んできました。
もちろん、リハビリ職や看護職が治療的な視点を持つことの意義はいまも変わりません。
しかし、現場で多くの利用者と向き合ううちに、次第に見えてきたのは「人」という存在の奥深さでした。
「体を動かすこと」「感情を表現すること」「他者と関わり合うこと」「自分自身を肯定すること」
レク・アクティビティには、人間が人間らしく生きるための要素が自然に織り込まれています。
だからこそ私たちが計画し、提供する活動は、単なる「余暇」ではなく、人生の本質に触れる場なのだと感じています。
利用者の笑顔、活動量の確保、それだけでなく、誰かの人生にそっと寄り添い、関われること。
それがレク・アクティビティの醍醐味であり、介護の本懐です。
多職種でつくる意味のある時間
介護や福祉、医療の現場ではレク・アクティビティに関わる職種は多岐にわたります。
看護師、介護職、リハビリ職、管理栄養士、時には心理士も関わることがあります。
立場や専門性は違っても、利用者を「診る=見る」という視点は、職種を超えて共有できる感覚ではないでしょうか。
この共通意識をベースに連携を深めていけば、レク・アクティビティの質は格段に向上します。
また、こうした協働は、レクだけにとどまらず、他の業務でもチームワークを強化する好循環を生み出します。
レク・アクティビティが「連携のハブ」になる
そんな場面を何度も見てきました。
その意味でも、私たちが提供するレク・アクティビティは「効果的」でなければなりません。
ただし、ここでいう「効果的」とは、難解な計画書や高尚な目標を立てることではなく、「目的」をしっかり持って実施すること。
それだけで、十分な価値が生まれるのです。
「盛り上がる」だけが正解じゃない
研修でよく受ける質問に、「どうすればレクが盛り上がりますか?」というものがあります。
背景には、「盛り上がらない=失敗」という思い込みがあるようです。
しかし、本当にそうでしょうか?
確かに目的を持たずに行えば、参加者の反応は薄いかもしれません。
でも、「盛り上がらないレク」=「ダメなレク」とは限らないのです。
例えば、静かで落ち着いた雰囲気の中で、穏やかに交流が生まれていく。
そんな時間も、人生のひとときを豊かにする大切なレクリエーションではないでしょうか。
むしろそういった場にこそ、「目的」が明確に存在しているべきなのです。
あえて盛り上げすぎず、沈静な空気を演出することも、利用者の心理に寄り添う一つの方法です。
「人と人が関わること」「その人らしさに触れること」
こうした人間性にアプローチすることこそ、レク・アクティビティの真の役割であると考えます。
レクは関係性を育てる
普段行うレク・アクティビティは、身体機能や認知機能へのアプローチだけではなく、人と人との「関係性」を構築する営みでもあります。
それは利用者に対してだけでなく、職員同士にも言えること。
共に考え、悩み、笑い、支える。
そんな時間の積み重ねが、現場をもっと良くしていくのだと信じています。
【情報提供元】
日本ケアレク研修会2025
【お役立ち研修】