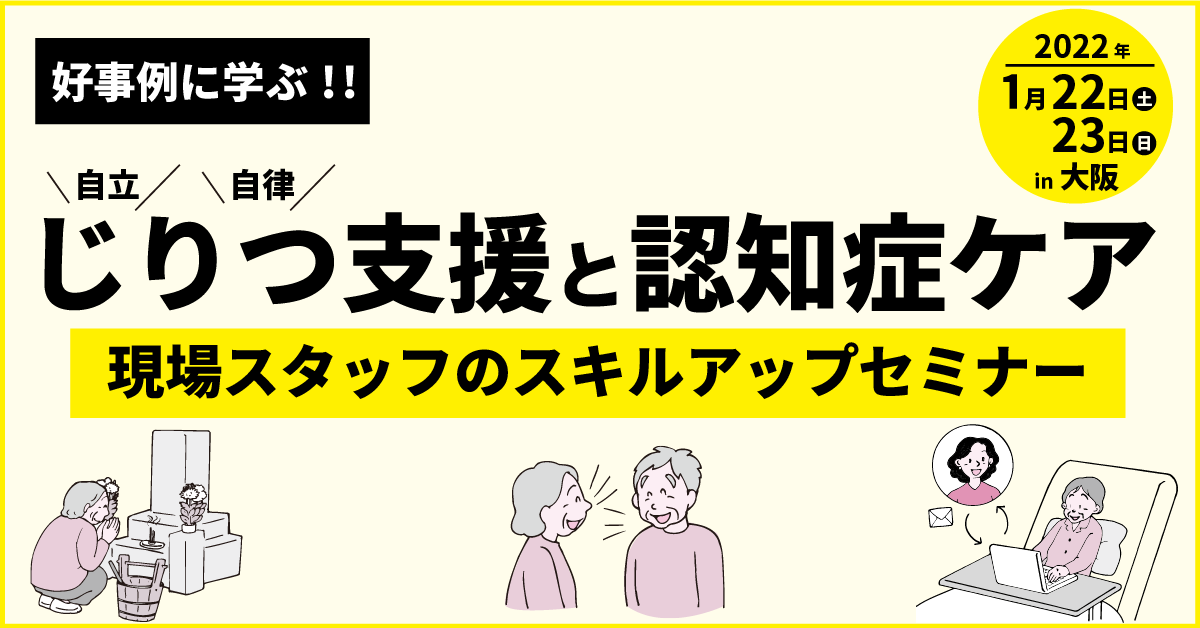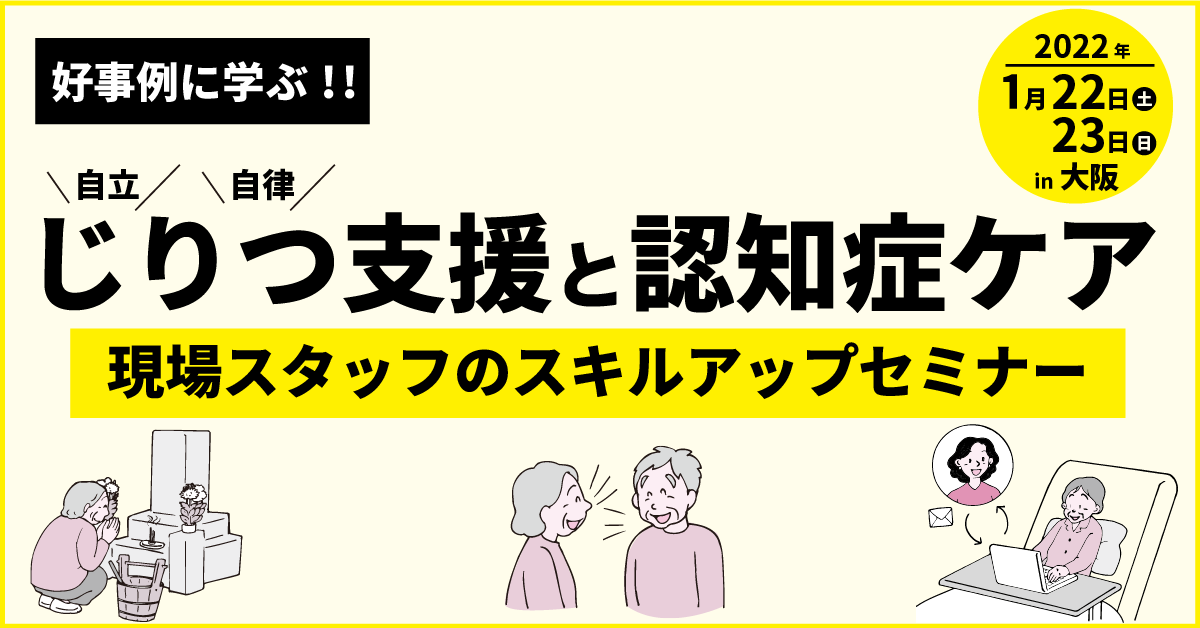研修内容
求められる介護力!!ワンランク上の「じりつ支援」・「認知症ケア」とは
2021年度の介護報酬改定で介護サービスにはより一層の「自立支援、重度化防止の取り組み」が強化され、介護現場ではご利用者の尊厳を保持したより質の高いサービスの提供が求められています。そもそも本当の意味での「じりつ」とは何か⁉を現場スタッフは理解した上でサービスを提供しているのでしょうか。「自立支援」「認知症ケア」という言葉だけが先行して一人歩きしていませんか?このセミナーでは本当の意味での「じりつ支援」を理解し、その上で「環境」「プログラム」「システム」など翌日からのワンランク上の介護現場での実践・認知症ケアに必要な支援のあり方を講師の実践事例から学びます。
【1日目】2022年1月22日(土)10:30~16:00
テーマ「じりつ支援」
[講師] 山下 総司氏(株式会社IDO コンサルティング事業部 介護部門ディレクター)
[講師] 山出 貴宏氏(株式会社NGU 代表取締役/生活維持向上倶楽部「扉」 管理者)
【山下氏が予定しているセミナー内容】
・施設の環境や習慣を変えたいけど変えれない!「分析」「原因」「対策」の方法を学ぶ
・地域とつながるために「施設内で行うこと」「地域で行うこと」の実践事例
・ご利用者のニーズに合わせた「自立」と「自律」に向けた取り組み実例集の紹介
・日々の「じりつ」に向けた活動が施設の稼働率アップに繋がる仕組みを知る
・活動の幅を広げるために必要なスタッフ育成の視点とポイント ほか
【山出氏が予定しているセミナー内容】
・自立支援の勘違いについて
・「自律と自立」の観点からご利用者のことを考えていますか?
・デイでのサービスやプログラムの提供を生活にどのように結びつけていくのか
・リスク管理の勘違いと考え方
・「自立支援」を見直し「○○支援」へ
・生活動作と日常生活動作への関わり方と考え方 ほか
【2日目】2022年1月23日(日)10:30~16:00
テーマ「認知症ケア」
[講師] 山下 総司氏(株式会社IDO コンサルティング事業部 介護部門ディレクター)
[講師] 山出 貴宏氏(株式会社NGU 代表取締役/生活維持向上倶楽部「扉」 管理者)
【山下氏が予定しているセミナー内容】
・認知症の方への環境設定の3本柱(「物的」「ケア的」「人的」)
・PEAPに基づいた施設環境創りの6ステップを学ぼう!
・職員の理解力と実践力を高めるためには
・日常生活におけるそれぞれの「場」を整える
・本当にそれBPSD!?自尊心(嫌なものは嫌だという気持ち)の表れは本人の元気の証拠 ほか
【山出氏が予定しているセミナー内容】
・認知症の方の「役割」のある生活の創造
・認知症ケアになぜ介護技術が重要なのか
・日常生活動作で必要な「知識」「技術」…全介助と部分介助の考え方
・介護技術が与えている「不安」と「不快」
・その場面ごとで終了してしまう単発の「イベント支援」にならない為に必要な事(生活場面で考える) ほか
この研修に参加する
関連セミナー動画(一部)を確認
この研修に参加する
講師紹介
山下 総司 氏(やました そうし)
・株式会社IDO コンサルティング事業部 介護部門ディレクター
・介護環境アドバイザー
奈良県出身。一般企業に勤務後、介護現場(デイサービス、障がい者施設、介護老人保健施設、在宅ヘルパー等)などで9年間勤務し、パート職員から管理者までを経験。「選択と自由」のある施設づくりをテーマにデイサービス管理者時代に自施設で実践。その取り組みは全国からの見学者を通して広がり、介護現場業務の傍ら「選択と自由の ある施設づくり」をテーマに依頼がある事業所へ伺い、現場に入りながら研修、指導などを行う。平成23年12月に大阪和泉市のデイサービスセンターを退職後、施設環境アドバイザーとして全国各地の介護施設・事業所などで実践を行う。現在は、株式会社IDOの介護部門ディレクターとして指導施設とともに地域づくり、循環型地域共生に携わる。「介護は職員、利用者、経営者、地域が一丸となって構築するもの」という考えのもと全国各地で希望が生まれる施設づくり、地域づくりを実践している。
山出 貴宏 氏(やまで たかひろ)
・株式会社NGU 代表取締役
・介護福祉士
・認知症実践者ならびにリーダー研修修了
・社会福祉主事
・福祉用具専門相談員
・認定自律介護技術1級
・認知症キャラバンメイト
東京福祉専門学校医療福祉課にて医療ソーシャルワーク、精神保健福祉について学ぶ。医療相談での介護や建築の知識がもっと必要と感じ、卒業後に建築会社に就職。一般建築とバリアフリーを現場で学ぶ。バリアフリーのリフォーム中心の仕事の中で、本当にその方に合った改修なのか疑問を抱き始め、介護の現状を知るために特別養護老人ホームへ転職。訪問入浴部門に配属され、在宅で入浴サポートと家族とのかかわり方を学ぶ中で、介護のスキルを高めなければと考え、別法人の特養の介護職として入職する。入所者の認知症の症状進行、機能低下・拘縮等が重度化して行く事に対し、病気や障がいを理由にケアを見直さない事、介護職の対応でその方の能力を奪っている事が当たり前のケアになっていることや退職者の相談を受ける中で、独立を決意。株式会社NGUを設立しご利用者の「じりつ」を意識した「見える活動」の実践で地域をつなぐ取り組みを行っている。神奈川県が行っている「かながわベスト介護セレクト20」を3年連続で受賞
し殿堂入り。また横浜市認定の「横浜市自立支援実践事業所認証」を2年連続で受賞している。個人の活動としては、「じりつ支援」「介護技術」「認知症ケア」をテーマとした研修依頼を全国各地から受け、自身の経験と現在の実践を現場目線で伝えている。
【運営】
・介護研修事業「ステップ」
・生活維持向上倶楽部「扉」(地域密着型通所介護)
・生活維持向上倶楽部「匠」(地域密着型通所介護)
・生活維持向上倶楽部「栞」(居宅介護支援事業所)
・生活維持向上倶楽部「心」(じりつ支援型訪問介護)
・NPO 認知症フレンドシップクラブ横浜事務局
この研修に参加する
会場アクセス
【大阪会場】
新大阪丸ビル新館
〒533-0033
大阪府大阪市東淀川区東中島1-18-27
・JR新大阪駅東口より徒歩2分
この研修に参加する
参加にあたっての注意事項
・お申し込み後のご案内は「メール」「郵送」「FAX」いずれかの方法にてお送りいたします
・お申し込み後、1週間を経過しても入金案内が届かない場合は、事務局までご連絡ください
・参加費の納付を持って正式申し込みとなります
・ご入金後のお客様都合での参加費の返金はいたしかねますが、参加者の変更は可能です
・お申し込み時にいただいた情報は、当会の管理・運営のみに使用いたします