
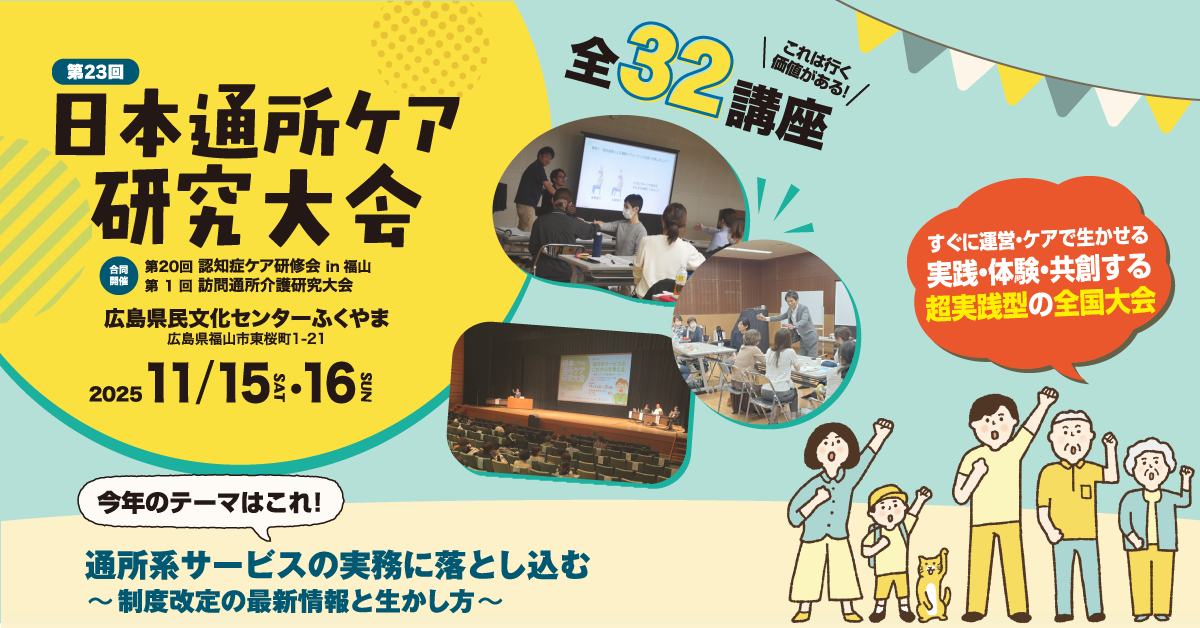


介護現場で日々のレクリエーションやアクティビティのアイデアに悩むスタッフは少なくありません。本実技分科会では、実際に体験しながら学べるワークショップ形式で、すぐに現場で活かせる「ケアレク」をご紹介します。手軽に準備できるものから、利用者の認知・身体機能を自然に引き出す工夫まで、幅広い活動を実践しながら理解できます。また、参加者同士で体験し合うことで、楽しさや効果を実感でき、現場での応用イメージも湧きやすくなります。「見るだけ」「聞くだけ」では終わらず、体験することで腑に落ちる学びが得られる時間です。楽しむだけではないケアの視点を取り入れたレク・アクティビティのバリエーションを増やしたいスタッフやご利用者の笑顔を引き出す工夫を日々探している方に最適な内容となっています。

通所介護・通所リハの現場で、「もっと効果的でご利用者が主体的に取り組めるトレーニングを取り入れたい」と感じているリハビリ職、機能訓練指導員などは多いと思います。本実技分科会では、日々の運動プログラムを「ウリ」に変える、新しいトレーニングアイデアを体験して学んでいただきます。効果や楽しさを実感し、そのまま翌日からすぐに現場で実践いただける内容です。機能訓練の要素を押さえつつ、ご利用者が「やってみたい」「続けたい」と思える工夫を盛り込むことで、満足度とリハビリの成果にも直結します。トレーニングをただの「運動」で終わらせず、デイの強みに変える…そんなヒントが詰まった参加実践型のワークショップです。

介護現場でよくある「ちょっとした違和感」や「利用者・家族の小さな不満」。見逃してしまうと、やがて大きなクレームや信頼崩壊につながりかねません。本分科会では、介護を「自分ごと」として考えるカードゲーム「CLUECARD」を使い、実際の場面を想定したロールプレイを体験します。小さなサインをいち早く察知し、チームで共有・対応する力を養うことが目的です。現場スタッフ一人ひとりが「気づく力」と「伝える力」を身につけることで、クレームを未然に防ぎ、利用者・家族からの信頼をより強固にすることができます。

「化粧が介護予防につながる?」その秘密は、手や肌を整える行為そのものが、身体と脳に心地よい刺激を与え、ADLやQOLの向上に結びつくことにあります。本セミナーでは、資生堂の化粧療法講座を活用した介護予防のレクリエーションを実体験。ハンドケアやスキンケア、メイクアップを実際に行いながら、その効果を体感していただきます。美容の楽しさと同時に「癒し」「交流」「自尊心の回復」といった効果も期待でき、現場のプログラムにすぐに取り入れられるヒントが満載です。高齢者がいきいきと輝く姿を引き出す新しい介護予防の形を、ぜひ体験してください。

介助する側も、される側も「しんどい」ままの介護になっていませんか?本分科会では、ご利用者の持つ力を引き出しながら、ご利用者・介助者双方の体への負担も大幅に減らせる「正しい立ち上がり・移乗技術」を学んでいただきます。実技体験を通してすぐに現場で実践できる介助のコツを体感していただきます。翌日からのケアがぐっと変わる超実践型の分科会です。

「最近、歩きにくそうだな…」そんな小さな変化を見逃していませんか?本分科会では、ご利用者の歩行の「質」に注目し、安全で安心できる歩行支援のコツをお伝えします。歩行の変化に気付く視点、正しい介助と補助機の使い方、さらに靴の履き方ひとつで変わる歩きやすさまで幅広く実際に体験しながら学べます。ご利用者を座りっぱなしにしない!楽しく体を動かすフットトレーニングも体験できます。翌日からの現場実践で、転倒予防や自立支援につながる「歩行改善のヒント」をぜひ見つけてください。

介護保険法にある「その有する能力に応じて」という視点は、自立(自律)支援において欠かせないキーワードです。本分科会では、その考え方をふまえ、認知症のご利用者への「関わり方・触れ方」を見直し、日々の関わりの中で「不安・不快(焦り)・負担」を和らげる介護技術を学びます。実際のケア場面を想定しながら、技術の工夫がどのように安心感や信頼関係につながるのかを体感しながら理解できる内容です。ご利用者にとっても介助者にとっても心地よいケアのあり方を再認識しましょう。

パーキンソン病や片麻痺のあるご利用者にとって、「立ち上がる」「歩く」「着替える」といった日常生活の動作には、多くの困難が伴います。しかし、その改善を「進行性の病気だから」「発症から半年以上経ったから仕方ない」と決めつけてはいないでしょうか。実は改善の糸口は【運動の教え方を工夫すること】にあります。本分科会では、脳卒中専門の保険外(自費)リハビリサービスを12年以上継続する中で培われた独自の「動きのコツ®︎」をもとに、理学療法士や作業療法士でも学んでいない実践的なトレーニング方法を体験形式で学びます。座学で動作の特徴や注意点を理解し、その後に実技を通して「現場でそのまま使える工夫」を身につけていただけます。リハ職に限らず、どなたでも実践可能な支援方法を学び、ご利用者に「できる喜び」を届けられる技術を持ち帰りましょう。

集団トレーニングにおいては、シンプルな運動であっても意識するポイントや体の設定次第で負荷や動作の質が大きく変わります。一言のアドバイスが痛みの軽減や動きやすさの向上につながることも少なくありません。本分科会では、立ち上がり動作や片足立ちを題材に、骨盤や股関節の使い方など指導時に押さえたいポイントを解説します。さらに、簡単なエクササイズ前後の動作変化を、症例動画やデモンストレーションを通じて体感いただき、日常生活に取り入れやすいホームエクササイズの選び方や導入の工夫もご紹介します。