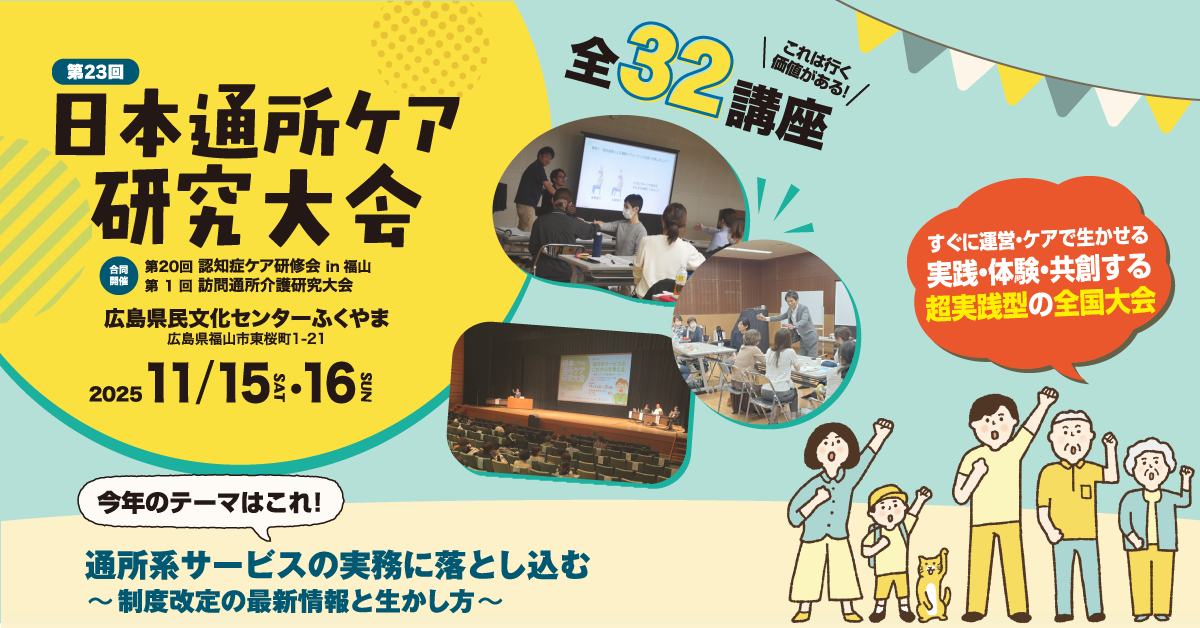


深刻な人手不足が続く介護業界。しかし実際には、「人が集まり、辞めない」施設も存在します。本セミナーでは、9年にわたり現場を運営してきた講師が、「なぜ人材が定着し、選ばれる施設になれるのか」を自身の実践をもとにお伝えします。採用広告や条件だけではなく、職員が「ここで働きたい」と感じる仕組みづくりや入居者・利用者の幸せはスタッフ次第であるという考えのもとに築かれた、「人を大切にする職場文化」の実例を余すところなく紹介します。「どうすれば選ばれる法人・施設になれるのか」。その答えを、実際に離職防止や人材定着に成功している事業所の取り組みから学ぶことができます。人手不足に悩む方も、これから職員の定着率を高めたい方も必見。現場で明日から実践できるヒントと気づきが詰まった内容です。

「どうすれば地域で信頼され、選ばれ続ける事業所になれるのか?」。本セミナーでは「地域で選ばれる通所リハビリ」を実現するために、マネジメントとマーケティングの視点から戦略的アプローチを解説いたします。まず、自事業所の通所リハの強みを見直し、地域資源との連携による価値創造の可能性を探ります。次に、組織運営におけるマネジメントの基本と、地域ニーズに応じたサービス展開を支えるマーケティングの考え方について事例を交えて紹介いたします。現場で即活用できる視点をお持ち帰りいただける内容です。

通所リハ・通所介護の現場において、利用者さんが「ただ参加する」存在から「誰かの役に立つ」主体へと変わる瞬間。そこに生まれるのは「役割」であり、まさに生きがいです。大切なのは、「やること」自体が目的ではなく、「その先にある社会とのつながり」をどう創り出すか。利用者さん一人ひとりがイキイキ・ワクワクと輝けるようなプログラムや社会貢献活動を、現場でどう形にしていくかが問われています。この挑戦を支えるのはスタッフの育成とチームの力。チャレンジする文化を根付かせ、切磋琢磨し合い、助け合う風土をつくること。そして、組織として工夫を重ねながら「まずはやってみる」挑戦の積み重ねが、厳しい時代に生き残り続ける力になります。淘汰の時代だからこそ、“ワイワイと利用者と一緒に楽しみながら挑戦する”ことが、地域から選ばれる施設の大きな原動力に。今回のセッションでは、利用者が主役となって輝くプログラムづくりの工夫や、現場を変えるマネジメントのヒントを共有します。

利用者数の伸び悩み、人材不足、コスト上昇…。厳しい経営環境を乗り越え、利益率を高めるには「ただ集客する」だけでなく、選ばれ続ける仕組みづくりが欠かせません。本セミナーでは、実際にデイを運営し、数多くの現場で安定した収益改善を実現してきた講師が「稼働率が伸び悩む典型的な原因とその打破法」「「紹介が増える営業」と「NG営業」の違い」「ケアマネ訪問で必ず伝えるべき内容」「稼働率を30%以上向上させた営業ツール」「「キラープログラム」の事例」など、現場で成果を出してきた すぐに実践できる具体的手法 を余すことなくお伝えします。売上アップとコスト管理を両立させ、通所サービスの未来を切り開くヒントをぜひお持ち帰りください。

リハビリテーションマネジメントは、単なる書類作成や定期モニタリングの管理だけではありません。計画書の内容をどう「伝える」か、モニタリング結果をどう「つなげる」か、そして情報共有をどう「活かす」かで、利用者支援の質も、事業所全体の評価も大きく変わります。本セミナーでは、実際に成果を上げている通所リハの取り組みをもとに、計画書作成、モニタリング、情報共有の質を高める手法を現場での具体的事例を交えて紹介し「伝える」から「つなげる」支援へステップアップします。リハビリマネジメントを「こなす仕事」から「利用者の変化と満足につながる実践」へと進化させるヒントを得ていただけます。

介護現場における最大の課題の一つが「人材の確保、定着と育成」です。離職の理由として多く挙げられるのは「職場の雰囲気」「人間関係」「育成不足」。いくら採用しても辞めてしまえば現場は安定しません。本セミナーでは、「なぜ人は辞めるのか?」という問いに正面から向き合い、“人が育ち、人が辞めない職場づくり”の工夫を具体的に実践してきた事業所の実際を紹介します。机上の空論ではなく、現場で実際に取り組み、成果を上げてきたリアルな実践例を共有します。

リスクはベネフィット(利益)と表裏一体の関係であり、ベネフィットとリスクのバランスをマネジメントする(どうにかする)ことがリスクマネジメントである。事後対応より事前対応が重要です。本セミナーでは、リーダーシップ・フォロワーシップを発揮するうえで必要なのは、自らの責任と権限を理解し、自責思考で「できることを考え、行動する」ことについて学びます。管理者・リーダーにはできることがたくさんあります。

長時間デイケアから「短時間デイケア」へシフトしたことで、事業所は大きく変わりました。利用枠が広がり、待機者が出るほどの人気に。さらに、収益は大幅に改善し、水道光熱費や消耗品コストも削減。利益率がアップするだけでなく、集中型リハビリによって利用者の効果も向上し、満足度も高まりました。また、栄養補助食品の販売を組み合わせることで、運動効果をさらに高め、副収入の確保にも成功。「経営の安定」と「リハビリ効果の向上」を同時に実現した実践事例を通じて、短時間デイケアの未来戦略をお伝えします。

訪問通所介護は、制度設計がまだ確定していない新しい分野だからこそ、先進的に取り組む事業所の知見が非常に貴重です。本セミナーでは、全国の現場で実際にサービスを運営している事業者の報告をもとに、経営・運営のリアルを共有します。合わせて訪問サービス側ならではの課題や工夫、スタッフの役割分担、利用者・家族との関わり方、収益性確保の具体策などについても言及いたします。これから取り組む事業者にとって、先行事例から学ぶ貴重な機会となります。
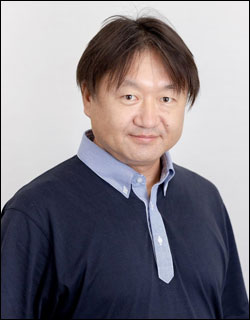
介護現場では、新人・中堅・ベテランそれぞれの立場で直面する「つまずき」があります。新人は業務理解や自信不足、中堅は指導や役割の広がり、ベテランはモチベーション維持や後輩育成といった課題に悩むことが少なくありません。本セミナーでは、心理的変化や成長モデルを踏まえた教育的アプローチを紹介しつつ、各階層で実際に起こる悩みをどのように見極め、解決してきたかを現場視点で共有します。 また、組織全体で求められる課題や役割を整理し、自分の現在の立ち位置や業務と照らし合わせることで、今後の成長に必要な視点を明確化。参加者は、階層ごとのつまずきを乗り越える具体的なヒントと、組織全体の力を底上げするマネジメントの実践策を持ち帰ることができます。

介護現場で求められる相談員の役割は、ご利用者や家族、地域の声を丁寧に引き出し、支援に生かすことにあります。しかし現実には「言われたことへの対応で精一杯」「本音を聞き出せない」と悩む声も少なくありません。本セミナーでは、地域で活躍する講師が実際に取り組んでいる相談員の実践を紹介しながら、信頼関係の築き方、傾聴のコツ、課題や希望を引き出す質問の工夫を具体的に解説します。さらに近年注目される「意思決定支援」の観点から、意思とは何か、対話は単なる話し合いと何が違うのかを考えます。ロールプレイを通じて自身の相談技術を振り返り、実際の支援場面で生かせるヒントを得ることができます。地域・家族の「本音」を引き出し、利用者満足度と事業所の信頼を同時に高めたい相談員にとって必見のスキルアップ講座です。


認知症ケアの出発点は、「認知症の診断名のある人」ではなく「目の前のひとりの人」として向き合うこと。本セミナーでは、若年性認知症の診断を受け、デイサービスのスタッフとしても介護現場で働かれていた当事者を講師に迎え、診断から現在に至るまでの思いや日々の気づきを直接お話しいただきます。「どんな支援が心強く、どんな対応が負担になるのか」…。当事者だからこそ語れる感覚や思いを共有しながら、認知症ケアの基本を整理。現場で活かせる具体的なかかわり方や、安心できる環境づくりのヒントを体験的に学ぶことで、単なる知識ではなく、現場での「気づき」と「対応力」を高め、認知症の方にとって今よりもさらに安心で心地よい環境づくりに繋げていただけます。

認知症ケアの現場で、多くの職員が悩むのが「拒否」や「感情の混乱」への対応。優しく声をかけたつもりが不穏な反応につながり、どう関わればよいのか戸惑った経験は誰もが持っているのではないでしょうか。本セミナーでは、認知症の方が「どのような世界を感じているのか」を理解し、そのうえで安心感を高めるためのコミュニケーション技術を学びます。声かけや表情のちょっとした工夫で、不安や拒否が和らぎ、信頼関係が深まる具体的な方法を体験的に習得できます。さらに、認知症ケアを「実践する難しさ」や「人に伝える難しさ」にも焦点を当て、仲間と共有しやすい工夫や伝え方もご紹介。認知症の方の気持ちに寄り添いながら、会話が難しい場面でも安心できる関係を築くための“エッセンス”を、一緒に学んでいきましょう。

認知症ケアを実践する為に必要な知識である、中核症状とBPSD(行動・心理症状)といった専門用語、その“つながり”を理解することが大事です。専門職に求められる《心身の状況に応じた介護》を現場で実践するために、【認知症】という病気の理解を深めつつ、利用者さんの心の動き、《安心・焦り・不安》など【人の気持ち】に焦点をあてながら、明日から現場で活かせるBPSDの捉え方、対応の仕方など、適切なケアのあり方を一緒に学びましょう。


団塊の世代ジュニアが全員高齢者となり、高齢化のピークを迎える2040年に向け、今後の制度設計や報酬のあり方がどのように変化していくのかを正しく理解することは、経営者にとって欠かすことはできません。本セミナーでは、2027年制度・報酬改定に向けた最新の政策動向を踏まえ、具体的に「今から準備すべきこと」「これからの方向性」を明らかにします。制度改定をチャンスに変える視点を持ち、本大会での学びをより実践的に活かしていただける時間といたします。

介護現場では、日々の「ヒヤリ」とした瞬間を軽視したり、情報共有を怠ったりすると、重大な事故やクレーム、さらには事業所全体の信頼崩壊へと発展することがあります。ご利用者の安全・安心を守り、ご家族や地域からの信頼を得るためには、「ヒヤリハット」を成長のきっかけとして活かす視点が欠かせません。本セミナーでは、まずヒヤリハットを誰でも簡潔に記録・共有できる仕組みづくりを学びます。そのうえで、事故・クレーム発生時にお互いが納得できる対応方法や、トラブルをチャンスに変える考え方を具体的な事例を交えて紹介します。さらに、管理者・スタッフ一人ひとりが対応力を高めるための実践的トレーニングや、家族・ケアマネへの丁寧かつ信頼を得る対応手順についても解説します。また、法人全体として前向きにリスクマネジメントへ取り組むための仕組みや、職員が「守られている」と感じる安心の組織風土づくりのポイントを共有。トラブルを恐れるのではなく、信頼を築く機会へと変えていくための具体的なヒントをお届けします。ヒヤリの段階で止める力、チームで支え合う力、そして信頼を積み重ねる力を養い、「事故・クレーム・トラブルに強いデイ」を実現する第一歩をともに学びましょう。

介護事業を取り巻く環境は、制度改定や人材不足、物価高騰など、かつてないほどの厳しさを増しています。安定した経営を維持するためには、介護保険サービス一本に依存せず、新たな収益の柱を築くことが求められています。今後、地域の中で生き残り・選ばれる事業所となるためには、「課題は地域にある」という視点で、自社が貢献できる社会資源を見つけ出し、地域とともに歩む仕組みを構築することが鍵となります。本セミナーでは、まず地域のニーズを正確に捉え、潜在的な社会資源を発掘する方法を具体例とともに学びます。そのうえで、通所サービスを中心とした既存事業に“もう一工夫”を加え、保険外サービスや新たな事業展開を通じて収益の柱を増やし、経営をより安定化させるための実践的なアプローチを紹介します。また、業務の見直しによって管理職・スタッフが動ける時間を確保し、効率的な運営を実現するためのヒントを提示します。さらに、「スタッフが主でなく、利用者が主」となる仕組みづくりを支える人員配置や役割分担の工夫についても、現場での成功事例を交えて解説します。制度や環境の変化に翻弄されるのではなく、自らの手で地域と未来をつくるために。本セミナーは、経営者が「守り」から「攻め」へと舵を切るための第一歩となる時間です。通所サービスに新たな価値を生み出し、持続可能な経営を実現するための実践的な視点と戦略をぜひお持ち帰りください。

介護事業を続ける上で、経営の赤字は避けて通れない課題です。特に近年は、人件費や光熱費の上昇、加えて制度改定による収益構造の変化など、従来の運営方法だけでは黒字を維持することが難しい状況にあります。しかし、着実に黒字転換を実現している事業所も存在しています。その違いは「戦略的な具体策を実行しているかどうか」にあります。本プレセミナーでは、赤字からの脱却を図り、黒字経営へと舵を切るための「10の具体策」を徹底解説します。たとえば、①稼働率を上げるための利用者獲得戦略、②職員のモチベーションと生産性を高める仕組み、③単価を下げずに提供できるサービス効率化の工夫、④加算算定の見直しと取りこぼし防止、⑤ICT導入による業務削減など、すぐに実践できる手法を整理してお伝えします。単なる理論ではなく、現場で成果を上げている具体的な実践事例を交えながら、経営者や管理者の皆様が「明日から取り組める」アクションプランを共有することが本セミナーの大きな特徴です。赤字を黒字へ転換するためには、一気にすべてを変える必要はありません。まずは「できることから一歩を踏み出す」ことが重要です。その積み重ねが経営を安定させ、事業の持続性を高めます。