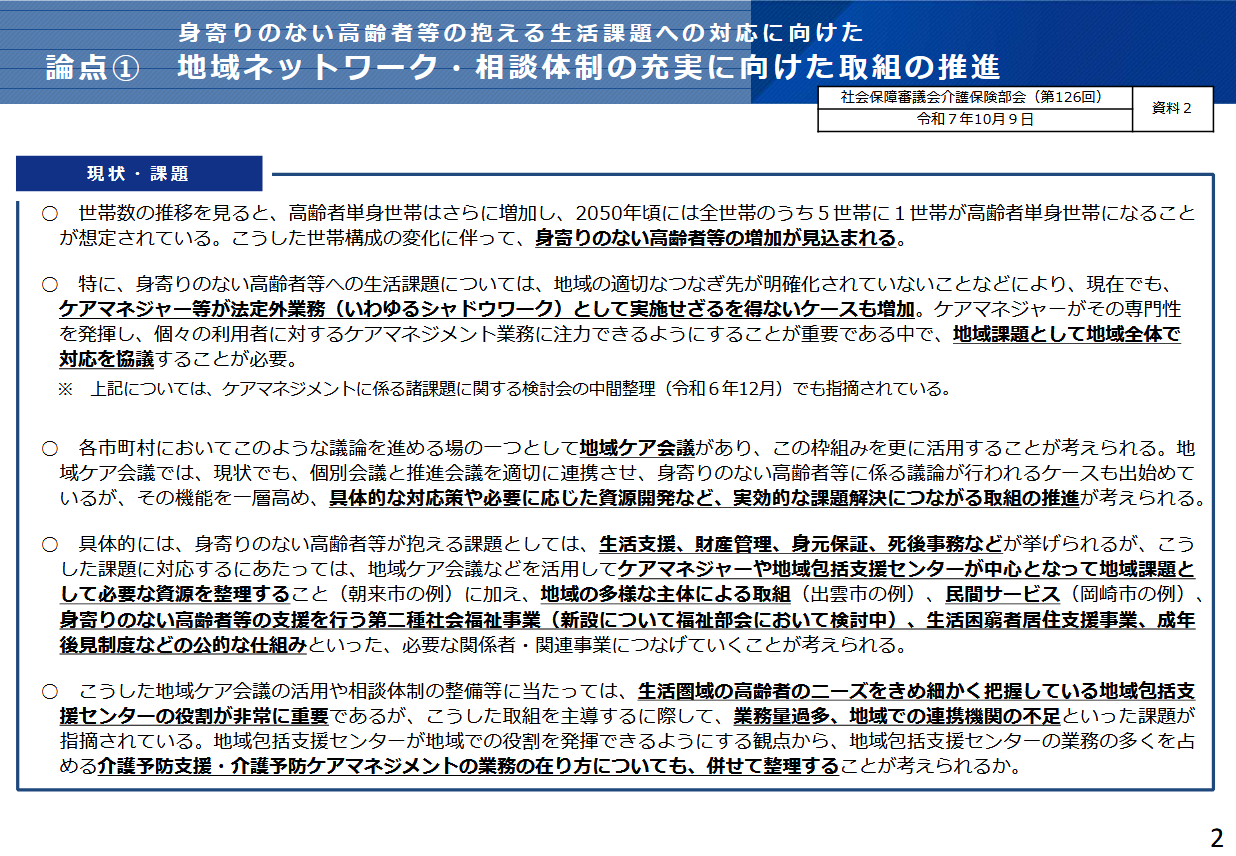
2025年11月17日(月)に開催された「第31回社会保障審議会福祉部会」の議論をまとめました。
今回の主なテーマは以下の5領域でした。
(1)地域共生社会
(2)身寄りのない高齢者支援・成年後見
(3)法人制度
(4)災害福祉体制
(5)共同募金制度の見直し
■地域共生社会の深化
[課題]
・相談支援は整備が進んだ一方で地域づくりは遅れ
・小規模自治体の人材不足、2040年に向け担い手が減少
[今後の方向性]
(市町村)
・地域側の“つなぎ役”を強化
・窓口設置方法は柔軟化
(都道府県)
・市町村の学び合いを支援
・こども、若者支援の機能強化
(過疎地域)
・配置基準の緩和、AI活用のモデル事業、都道府県の後方支援の明確化
(負担軽減)
・事務作業の簡素化、移行も丁寧に実施
[委員の主な意見]
・“見えにくい成果”も含めた柔軟な評価指標を
・人口密度など細かい指標で過疎地域を判定
・小規模自治体を都道府県がより具体的に支援
■身寄りのない高齢者支援・成年後見制度
[背景]
・単身高齢者の増加で、日常の手続きや死後事務の担い手が不在に
・成年後見制度も検討中
[新たな第二種社会福祉事業(案)]
(提供内容)
・日常生活支援、入退院手続き、死後事務の一部
(対象者)
・「身寄りのない」に限定せず、家族がいても支援が得られない人も含む
(利用料)
・高額化しない仕組みが必要
・無料・定額も選択肢
(チェック体制)
・届出制+都道府県・国の監督、ガイドライン整備
(論点)
・医療同意は原則扱えない(医行為の判断が必要なため)
・民間参入も想定しつつ質・倫理の担保が必要
・相談殺到や業務過多への懸念→人員・財政支援の強化が必須
(介護保険部会との連携)
・地域ケア会議を活用し、生活支援・身元保証など地域課題を整理
・通いの場、地域拠点を多世代交流の場として強化(介護予防・障害・子育て等を一体化)
・後見終了後や認知症の意思決定支援のルール化が必要
■社会福祉法人制度・連携推進法人
・連携推進法人が 第二種事業+福祉サービスの共同運営を可能に
・代表理事の再任手続き緩和、資産貸付の柔軟化など 事務負担を軽減
・解散時の残余財産は、地域の福祉事業継続のため公共団体等への帰属を認める方向
・ガバナンス強化(評議員会の権限見直し)を求める意見あり
■災害時の福祉支援体制
・能登半島地震を踏まえ、DWATなど災害福祉支援を 法的位置付けする方向
・平時からの研修・登録制度の整備、迅速派遣やフェーズ別対応のルール化
・派遣中の施設の人員基準緩和などの制度整備を検討
・支援情報を地域へ戻す仕組みや国・省庁間の連携強化が必要
■共同募金事業の見直し
・地域福祉の基盤として評価
・寄附募集禁止規定の見直し、準備金の使途柔軟化を検討
・事務負担に配慮しつつ、寄付者への成果フィードバックを強化
■福祉人材確保
(現状)
・2040年に向けて人材不足が深刻
・ニーズの多様化
(方向性)
・地域プラットフォームを都道府県に設置し、情報共有・課題解決を統合的に進める
・広報、体験の強化、テクノロジー活用、働き方改革、副業可、週休3日など新しい働き方を推進
・介護助手の活用によるタスクシフト
・介護福祉士の届け出義務化を強め、潜在人材の把握と支援へ
・外国人材支援も地域単位で強化
・国家試験義務化(養成施設)
・質を担保すべきvs人材確保上延長すべき→両論併記で継続検討
(その他意見)
・賃金・処遇改善なしに人材確保は不可能
・福祉全体で横断的に人材を育成し、支え合いの文化を社会全体で育てる必要
【情報提供元】
第31回社会保障審議会福祉部会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html
【お役立ち研修】




















