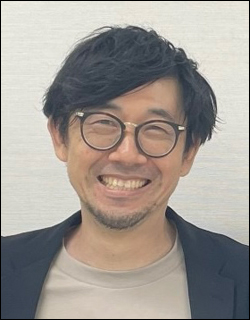認知症のご利用者が自立した日常生活を長く継続していただくために、私たちに求められる関わり方は、現状のケアに満足しそのケアを続けていくだけでよいのでしょうか。生活機能が徐々に低下していくご利用者にとって、ケアスタッフの適切なサポートや関わり方によって、認知症の症状進行を緩やかにし生活機能の維持に繋がります。また、認知症のご利用者が失いかけていた自信や意欲の向上から自己効力感が維持され、生活における自立心が高まり、ご利用者にとって大きな尊厳の維持につながります。そのために私たちは、ご利用者が自立した生活を営むための支援がより効果的に行えるよう日々のケアを振り返り再考していく必要性がるのではないでしょうか。
講座【1】[東京]2月23日(日)9:30~10:45/[大阪]3月9日(日)9:30~10:45/[福岡]3月16日(日)9:30~10:45
介護現場で働くスタッフのための認知症ケアの基本
認知症の正しい理解と関わりが出来てますか
[東京会場]講師:鈴木 望 氏(社会福祉法人元気村グループ 運営支援本部 サブマネージャー/きらめき認知症トレーナー)
[大阪・福岡会場]講師:渡辺 哲弘 氏(株式会社きらめき介護塾 代表取締役/認知症介護指導者)
認知症の理解を深めつつ、「目の前の人は今、どんな気持ちでその瞬間、どんなことを考え、行動しているの?」といった、「人」の気持ちに焦点をあてながら認知症ケアの基本をしっかり落とし込んでいただきます。専門用語を覚えることももちろん大事ですが、明日 から現場で活かせる考え方を一緒に学んでいきます。
【内容】
・“介護職に必要な能力”って!?~心身の状況に応じたケアの実践~
・“寄り添う”って!?~私達はいったい何をしたらいいの?~
・“記憶障害”って!?~認知症の進行度合いによって異なる特徴を理解しよう!~
・“脳の仕組み”パート(1)~ふだん私達は、どんな風に考え、行動しているのか~
・“脳の仕組み”パート(2)~その不可解な行動は、すべて脳の中で起こっている!~
・“どうして拒否するの?怒り出すの?”~良かれと思ってやっているケアが上手くいかない理由を探る~
講座【2】[東京]2月23日(日)10:55~12:10/[大阪]3月9日(日)10:55~12:10/[福岡]3月16日(日)10:55~12:10
認知症の人への伴走支援
認知症の人が認知症の人を支える「ピアサポート」での活躍の場づくり
[東京会場]講師:峯岸 正樹 氏(銚子市西部地域包括支援センター センター長/きらめき認知症トレーナー)
[大阪会場]講師:堀川 悟 氏(株式会社永桜会 代表取締役/社会福祉士/介護福祉士)
[福岡会場]講師:川畑 智 氏(株式会社Re学 代表取締役/理学療法士)
認知症になっても希望を持って⽇常⽣活を過ごせる社会を⽬指し、認知症の⼈や家族の視点を重視しながら「共⽣」と「予防」を⾞の両輪とした施策が現在、推進されています。今までの「本人不在、意見の反映がない、支援する側の視点中心」から「本人参画、意見を反映、本人の視点重視」の支援が今求められています。認知症になった本⼈の声に⽿を澄ませ、仲間づくりや安心して話ができる環境づくりに向けた取り組みとはどんなものなのか。認知症の本⼈のチカラを活かした取り組みについて学びます。
【東京会場内容】
・MCIになる前の予防の為の地域環境づくりの活動
・身体面、認知機能面を含めた馴染みのメンバーでお互いの地域で助け合うグループづくりや認知症への偏見をなくす場所づくり
・なぜ、地域環境?始めた切っ掛け
・地域活動?地域の集いの場
・地域でできる活動
・自分の老後のために
【大阪会場内容】
・地域における介護事業所の本当の役割
・認知症になっても地域社会で役割を持って暮らす
・地域で暮らし続けるためにできる伴走支援の実際
・地域住民を巻き込む!ためにしていること
【福岡会場内容】
・知ってるつもり…認知症基本法って?
・共生社会の実現のための認知症偏見チェック
・認知症が及ぼす介護への影響と介護原因との関係
・MCI、初期認知症の時期の取り組み 「For」から「with」への意識改革
・[対談]経験専門家(=認知症当事者者)が語る 「わたしが大切にしていること」
【ランチョンセミナー】[東京]2月23日(日)12:20~13:05/[大阪]3月9日(日)12:20~13:05/[福岡]3月16日(日)12:20~13:05
[参加自由]総合的認知症ケアの理解
講師:妹尾 弘幸 氏(日本通所ケア研究会 会長/総合介護施設ありがとうグループ 総施設長)
理解しにくいといわれる認知症ケアについて、総合的にわかりやすく解説します。
【内容】
・今さら聞けない認知症の基礎
・具体的ケアからヒントを学ぶ
・明日から使える認知症ケア
・ご利用者へのアプローチ事例 ほか
【みんなで情報交換】[東京]2月23日(日)13:10~13:50/[大阪]3月9日(日)13:10~13:50/[福岡]3月16日(日)13:10~13:50
[参加自由]今わたしが感じている認知症ケアの現場での困りごと
【内容】
認知症ケアの現場で働く多くの方が共通して抱えている困りごととして「コミュニケーションの難しさ」「行動の理解と対応の難しさ」「家族との関係・期待のズレ」「スタッフ間の連携」「業務の多忙さとバーンアウトのリスク」「知識不足と教育の必要性」を感じられています。この情報交換会では他事業所の方と情報交換をしていただくことで、日々のケアの悩みを共有し意見交換をすることで、自分たちのケアを再確認していただきます。また研修終了後も情報交換ができるきっかけづくりとしてもご活用ください。
講座【3】[東京]2月23日(日)14:00~15:15/[大阪]3月9日(日)14:00~15:15/[福岡]3月16日(日)14:00~15:15
間違いだらけの認知症ケア!
認知症の人を不安・不穏にさせないコミュニケーション技術
講師:椎名 淳一 氏(9612G Project代表/認知症介護指導者)
認知症の人の不安や不穏な気持ちを軽減し、安心して過ごせる環境(物的環境・人的環境)をつくれていますか。認知症の人の反応を観察しながら、心地よく感じてもらえ、不安・不穏にさせない、少しの工夫で大きな効果を得られるコミュニケーションの取り方について、介護現場での「あるある事例」を基に学びます。
【内容】
・認知症の人がなぜズレた行動や言動をしてしまうのか?
・認知機能障害(中核症状)との関連を考える
・認知症の人への介護職員のケアがズレた対応(一見いつも通りだが、声掛けが伝わらない、不安で混乱!ケアをしようとしてさらに興奮!、普段は行動的だが、最近ボーっとしている)
・どうやってコミュニケーションを取ればいいか
・認知機能障害(中核症状)に応じた関わり方
・「注意障害」「失認・実行機能障害」「記憶障害」「見当識障害」を理解した対応方法 など
講座【4】[東京]2月23日(日)15:30~16:45/[大阪]3月9日(日)15:30~16:45/[福岡]3月16日(日)15:30~16:45
事例から具体的ケアの支援方法が分かる!
介護現場で「困難事例」とされる認知症利用者への介護場面の対応から
その時困ったのは「誰」なのか?
[東京会場]講師:坂本 孝輔 氏(株式会社くらしあす 代表取締役/東京都認知症介護指導者)
[大阪会場]講師:中島 健 氏(株式会社コスモ 代表取締役/認知症介護指導者)
[福岡会場]講師:上村 尚之 氏(社会福祉法人白寿会 常務理事/福岡県認知症介護指導者会 執行部)
正解がない認知症ケアだからこそ、認知症ケアを行っていく中で、不安に思うこと、ケアの方法など、どのように対応したら良いかわからないことが起こっているのではないでしょうか。しかし、その場しのぎの対処ケアだけだと解決していきません。本講座では、事例を活用しながら学ぶことで、認知症ケアの一つの方法、ヒントとして、今後のケアの参考として引き出しを増やしていきます。
【東京会場内容】
・困難事例とレッテルを貼られた認知症の人と相対する時
・「認知症だからしようがない」とあきらめのような割り切りで納得していませんか?
・現場でよくある特徴的な事例をひも解く
・「急に怒る」「帰りたいと強く訴える」「介護を拒否する」といった行動・心理症状の原因と目的を探究するプロセスを体験
・認知症の人の行動心理の「原因」と「目的」を理解する視点と技術
【大阪会場内容】
・人として必要なこと
・認知機能の低下で難しくなること
・思いと感情も機能と一緒に低下する?
・ケア環境の修正はチームで取り組む
・「真実」と「事実」…どちらで支援するのが正しい?
・フィルター(色眼鏡)を意識する
【福岡会場内容】
・認知症ケアの目的
・専門職の評価的な理解から分析的・共感的理解へ思考が変わることで、認知症高齢者の捉え方が変わる
・「なぜ、入浴を嫌がるのか?」
・中核症状の影響とBPSDの症状に整理しながら支援方法を検討する
・専門職の認知症に関する理解不足
・拒否や抵抗の多くは「認知症だから仕方がない」という偏見や諦めの対応が原因