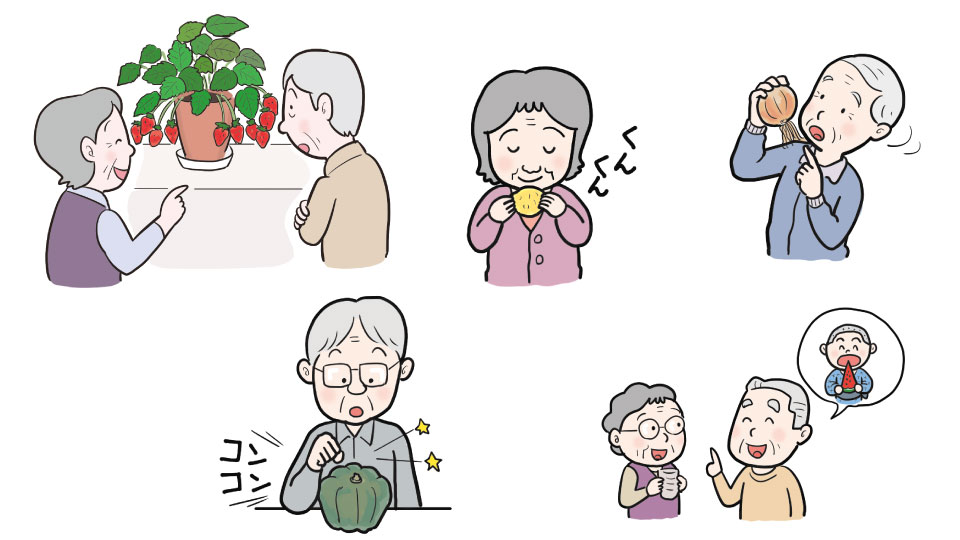
「リハビリケア」は、リハビリは「セラピスト等の指導により機能の維持・改善を目指した認知症の人が行うトレーニング・練習」、ケアは「認知症の人の理解を助ける周囲の人のかかわりや物品の工夫・環境設定」と位置づけています。
認知症の症状は進行するものであり、リハビリテーションによって治るというものではありませんが、認知症により障害された機能を理解し、できること・できないことを評価することで、介入のポイントが明確になります。
リハビリにより進行を緩やかにし、ケアを工夫して理解を促し不安を軽減することで、その人らしい生活が自立して行えるようになるのではないでしょうか。
認知症の定義
精神疾患の診断統計マニュアル(DSM-5)によると、認知症とは「注意」「学習と記憶」「言語」「実行機能」「知覚-運動」「社会的認知」の一つ以上の分野に障害があり、そのために、「複雑なIADL(手段的日常生活活動)に援助を要する状態」と定義されています。
すなわち、何らかの高次脳機能障害に生活機能障害が合併した症状であるといえます。
従って、認知症のリハビリは、「高次脳機能障害」に対するリハビリと「生活機能障害」に対するリハビリに大別できます。
[DSM-5では、以下の条件を満たした状態を認知症と定義]
(1)注意
(2)学習と記憶
(3)言語
(4)実行機能
(5)知覚- 運動
(6)社会的認知
(7)(1)~(6)のため日常生活に支障をきたす
(8)脳などの身体的な原因があるか、あると推測できる
(9)意識障害はない
※(1)~(6)の一つ以上の分野で障害が起こると「高次脳機能障害」
※(1)~(6)のため日常生活に支障をきたすと「生活機能障害」
認知症のリハビリ・機能訓練の考え方
高次脳機能障害に対するリハビリ・機能訓練は、一次的障害である脳の各機能、その機能の低下の緩和・維持・改善を目指します。
本人の機能に対する直接的なアプローチが中心となります。
生活機能障害に対するリハビリ・機能訓練は、二次的障害である活動・参加低下の緩和・維持・改善を目指します。
本人への直接的アプローチだけでなく、道具や設備などの物理的環境や地域の受け入れといった社会環境などの間接的アプローチも重要となります。
■高次脳機能障害へのリハビリ・機能訓練
[1]評価
高次脳機能の状況について評価します。
[2]障害の分析
(1)改善の可能性、生活の中での重要性などについて考えます。
(2)障害が進んだときに出現する症状・状況・生活での影響度を推測します。
(3)どの高次脳機能に対してアプローチしていくか決めます。
[3]リハビリ・訓練の実施
どの機能をどのような方法、難易度で訓練するか決めます。
[4]再評価
変化、改善、低下の遅延具合などを評価します。
[5]改善しない場合の代替法の検討
改善しない場合の代替法(器具を使うなど)を考えます。
■生活機能障害へのリハビリ・機能訓練
[1]評価
(1)どの活動・参加ができないか大まかに評価します。
(2)支援、介助が必要な活動の中から、重要かつ改善可能な活動をピックアップします。
(3)より詳細な評価をします(活動を細分化し、できるかできないか評価)。
[2]できない原因を推測
細分化評価のできない部分について、なぜできないかを推測します。
[3]できない原因に対するリハビリ・機能訓練の実施
推測した原因に対して、それを補うリハビリ・訓練を実施します。
同時に、できない活動に対し、現在の心身機能でもできるような工夫をし、その環境下で活動を行います。
[4]できない活動そのものの練習の繰り返し
環境の工夫がなくてもその活動ができるように、練習します。
[5]できない場合の代替法の検討
上記のリハビリ・訓練を検討・実施しても生活機能が改善されない場合、環境面や福祉用具・介助を含めた代替法を検討します。
【情報提供元】
リハージュ
【お役立ち研修】




















