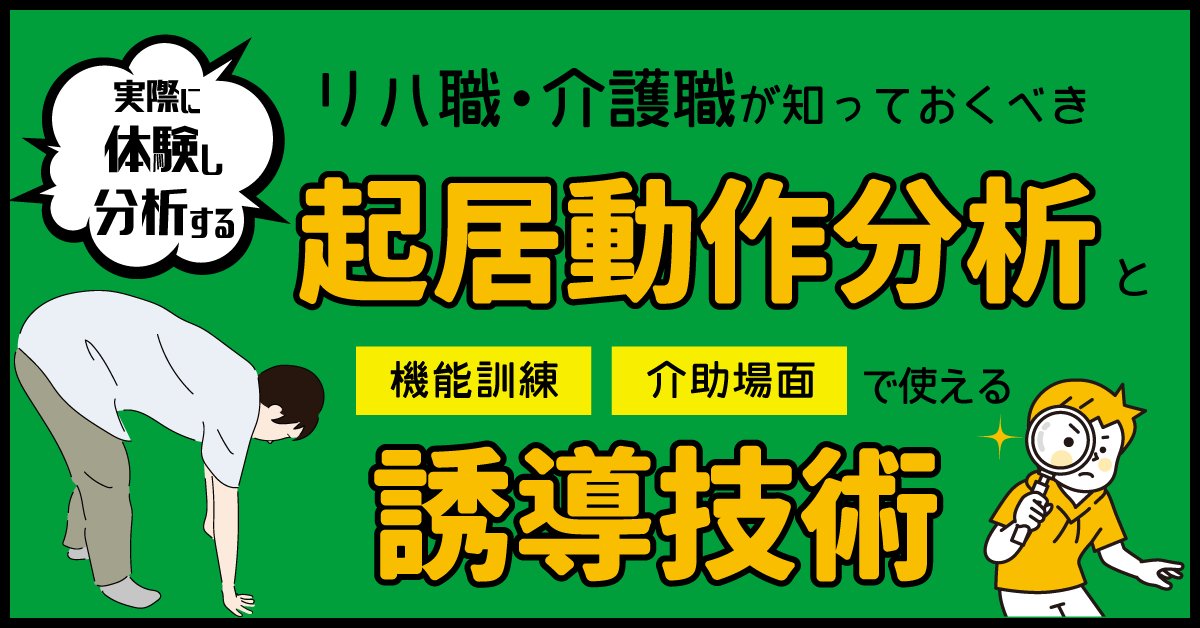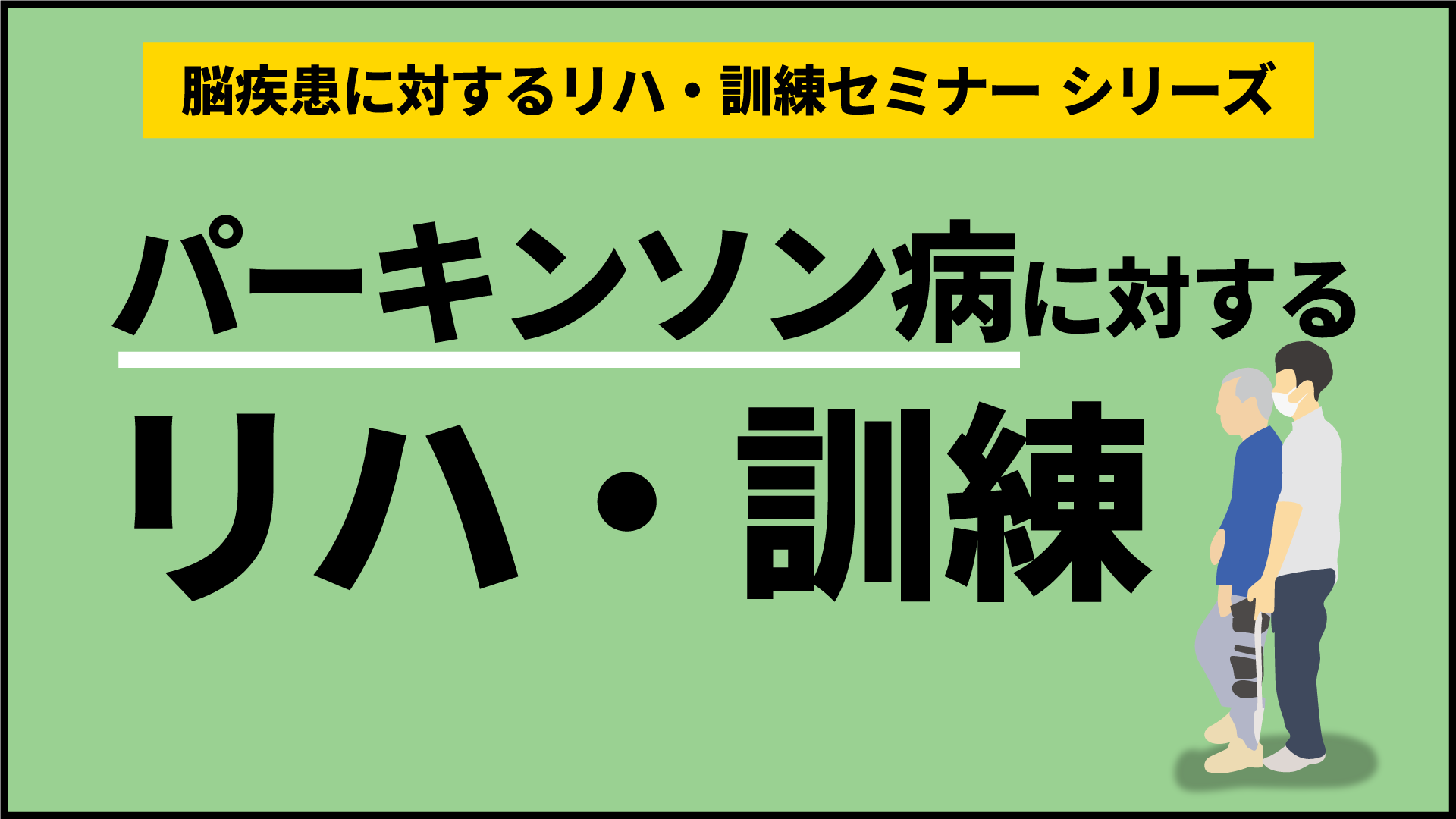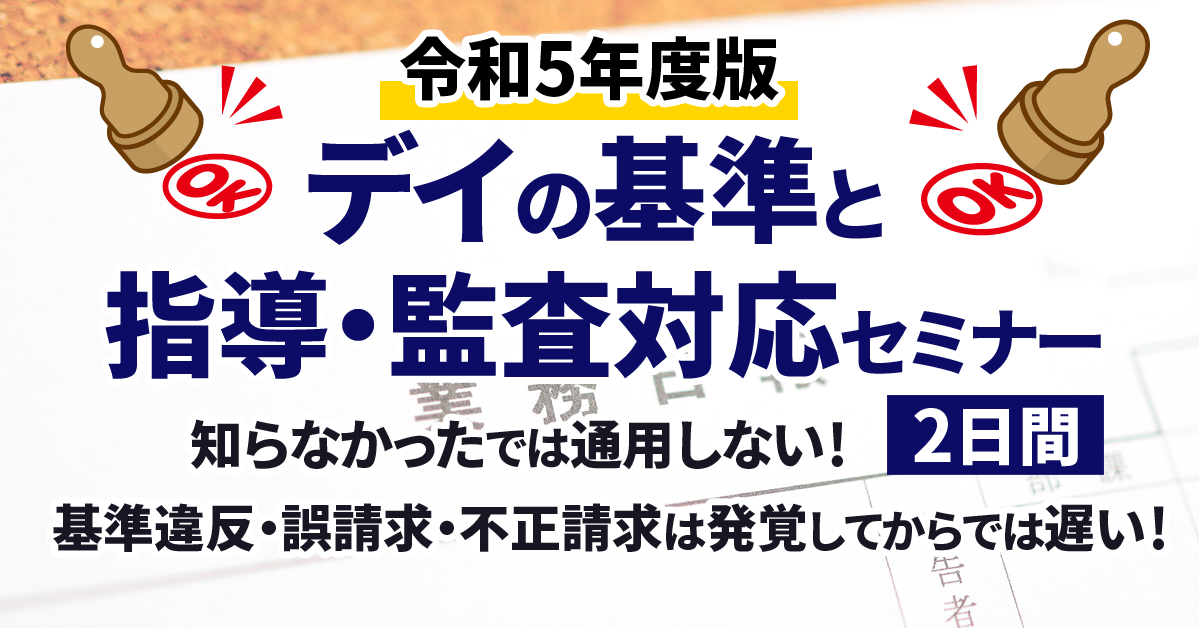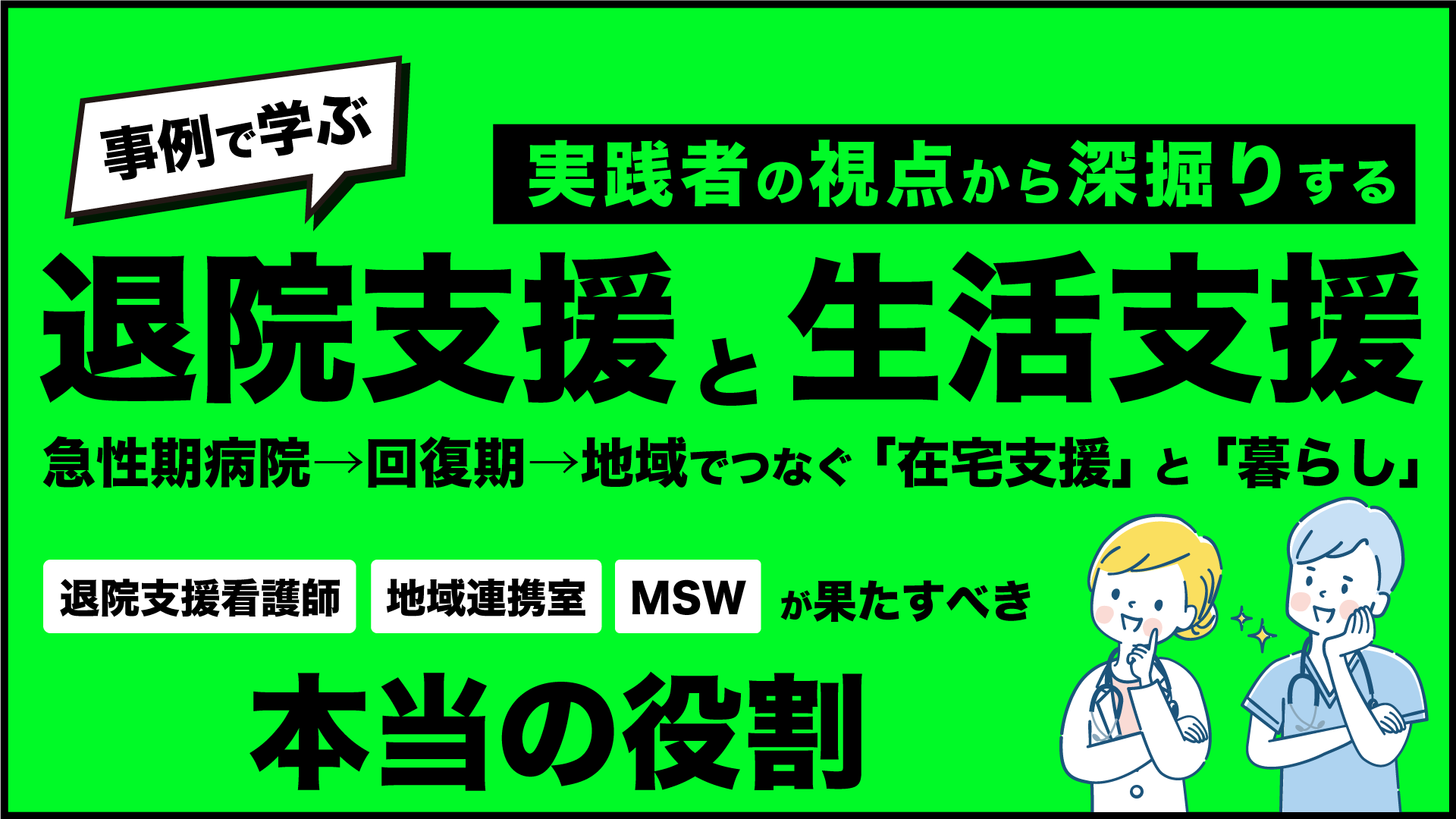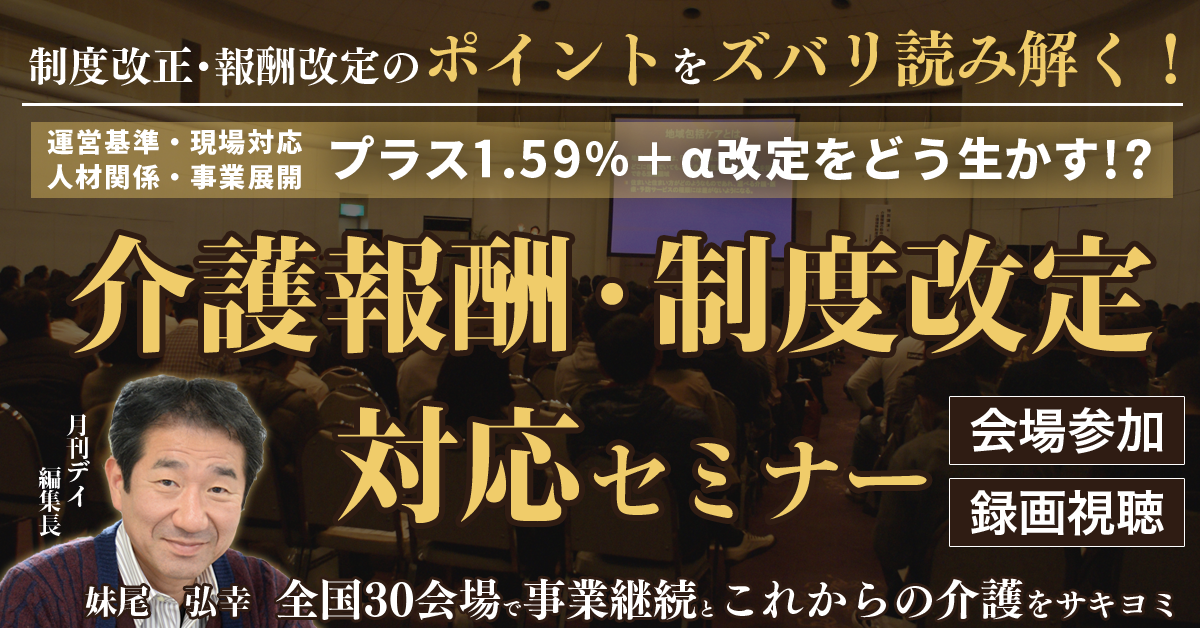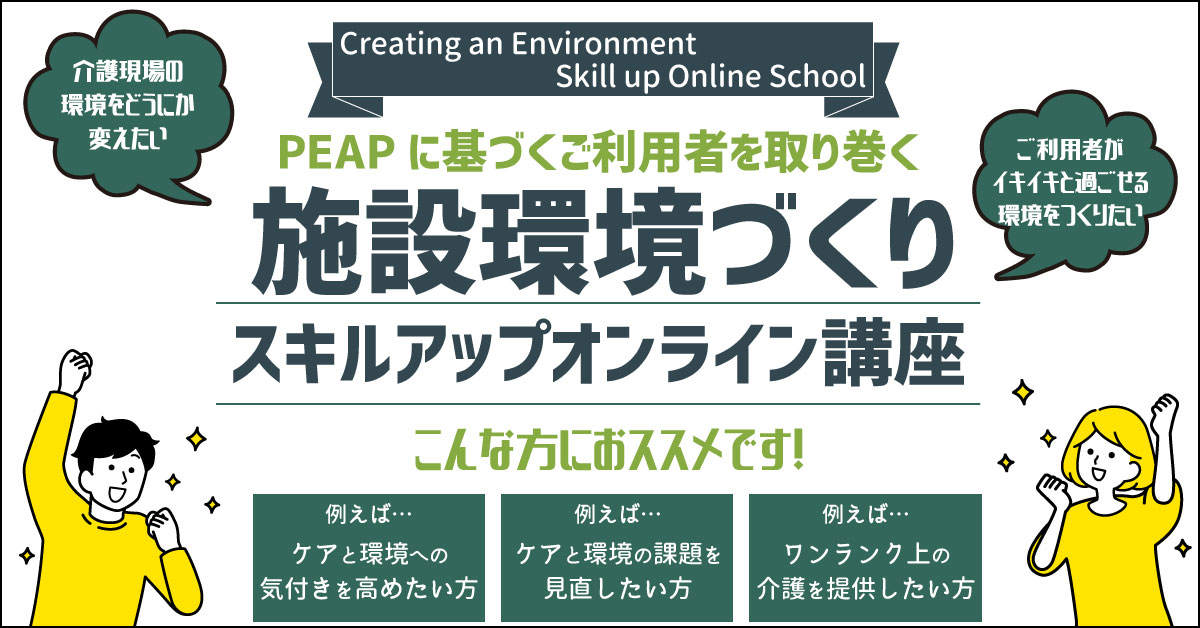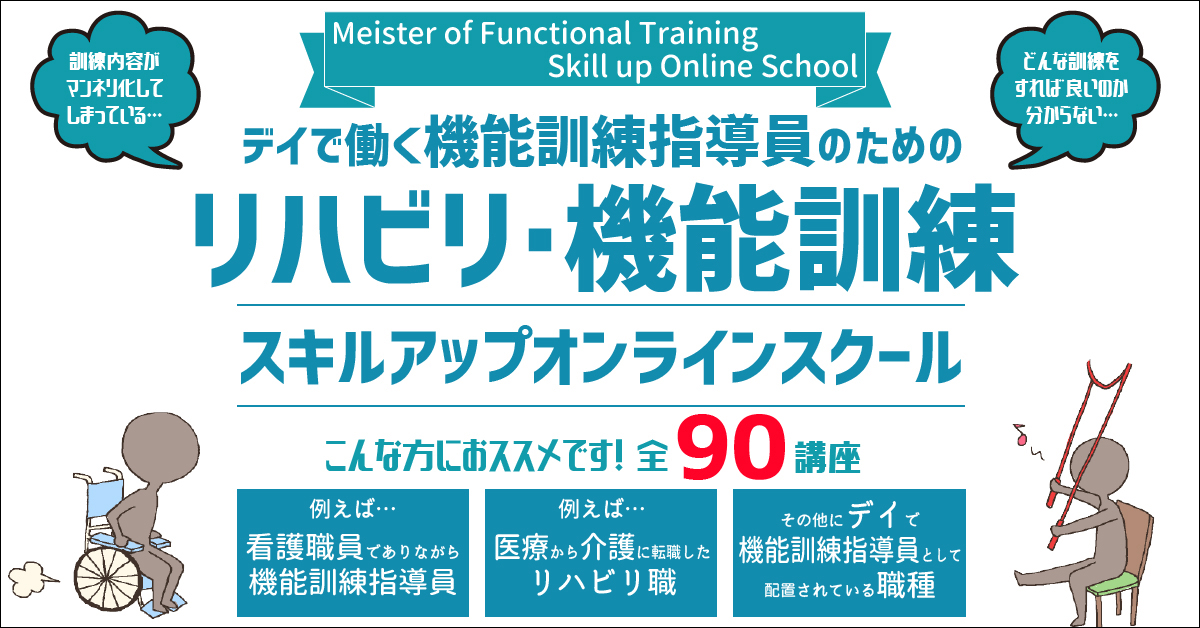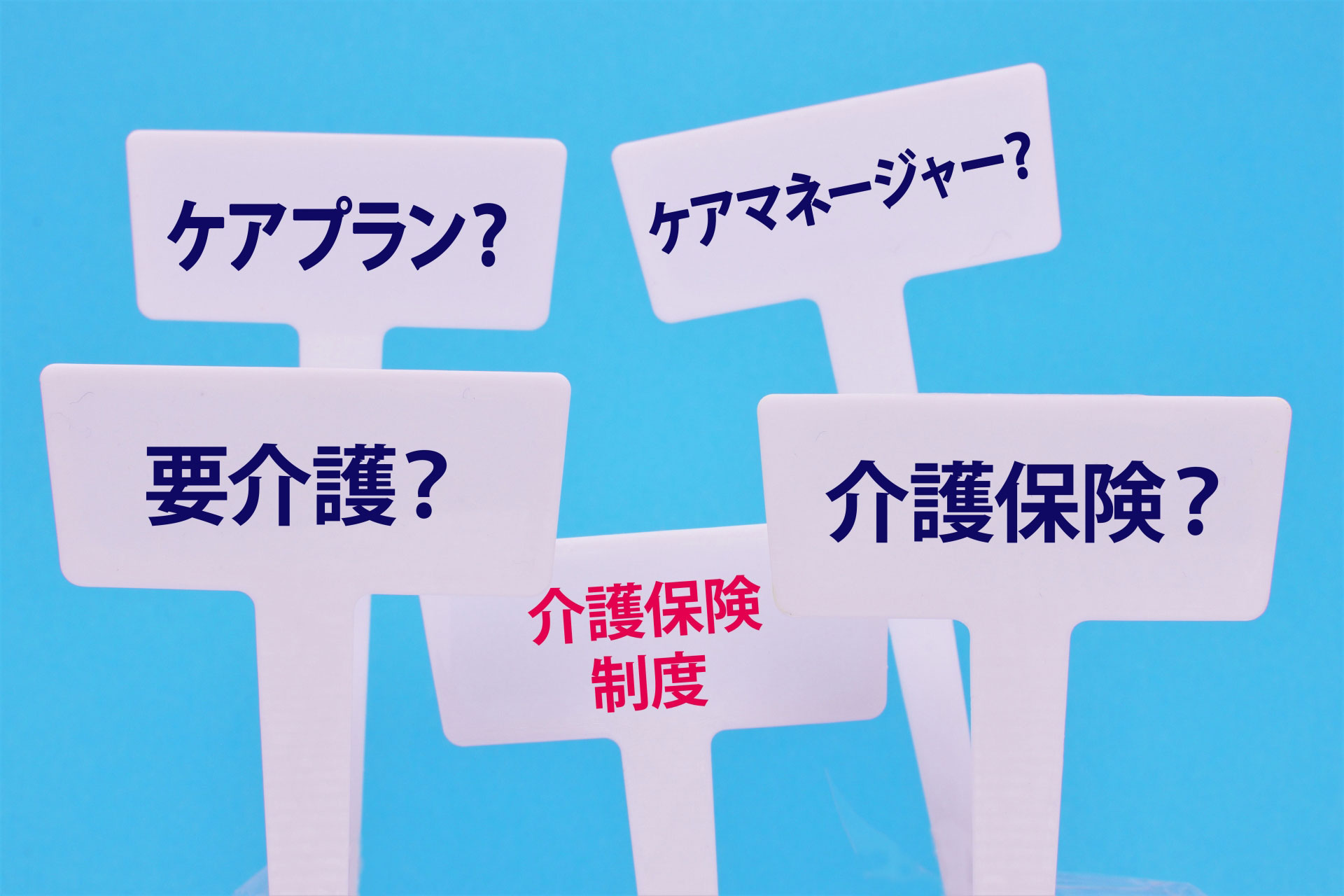
先日、2027年度の介護保険制度改正に関するセミナーに参加しましたので、事務局の私感ではありますが、ポイントをわかりやすく整理してまとめて、お伝えします。
ポイント[1]
自己負担「2割負担」の拡大
現在は一定以上の所得がある人は2割を負担していますが、その基準を下げる案が検討されています。
厚労省は「280万円 → 220~270万円に下げる」複数案を提示。
220万円案だと対象者は約554万人に増え、600億円の抑制効果がありますが、生活への影響が大きく政治的にハードルは高めです。
与党内からは「大幅な引下げは難しい、小幅なら可能」との声も上がっています。
見通しとしては、2027年度に小幅引下げ、2028年度に上限制を組み合わせた拡大など、段階的導入が現実的だと思われます。
ポイント[2]
ケアマネジメント有料化
「ケアマネは無料で使えて当たり前」という現行制度に対して、有料化の議論が出ています。
財務省は導入に前向きですが、法律改正が必要であり政局的にも合意形成が難しいため、今回もこの話は進捗しない可能性が高いです。
ポイント[3]
総合事業の対象拡大
地域の支え合いを軸にした「総合事業」を、要介護1・2の人まで広げる案が前回改正の時からあります。
現行の仕組み(住民主体の通いの場(B型)や短期集中リハ(C型))が十分に普及していないため、拡大の実現性はまだまだ、低いと見られています。
■インフレと賃上げへの対応
物価や人件費が上がる中、介護現場では「赤字」「人材不足」が深刻です。
政府の対応策としては以下を検討しています。
・社会保障費の伸びは抑える(年4,000億円程度)
・その一方で、介護職の賃上げは別枠で対応する仕組みを整える
つまり、「歳出抑制」と「賃上げ促進」という相反する課題を同時に進めているというのが現在の状況です。
■政治的影響
政令や省令で進めやすいもの:2割負担の基準見直しなど
法律改正が必要なもの:ケアマネ有料化、総合事業拡大など
2025年9月時点で与党は国会で過半数を割っており、野党との協力が欠かせない現状ではりますが、賃上げは与野党共通テーマであり、この合意形成がカギになりそうです。
■2040年問題を見据えた体制改革
2040年問題に向けては、地域ごとに異なる課題へ対応する方針が出されています。
・人口減少地域
→訪問介護を包括報酬にして、人員基準も柔軟に対応
・都市部
→高齢者の需要増にどう対応するか
・その他地域
→需要ピーク後の急減への備えをどうするか
介護・医療・福祉改革とも足並みを揃え、総合的な地域体制をつくっていく方向が示されています。
■これからの対策へのヒント
事業者
→賃上げの予算措置に注目し、自社の給与・人材戦略を着々と準備する必要性あり
→インフレ対応としてコスト構造を見直しが必要
→将来的に各種サービスが包括報酬払い・人員等の基準緩和に備えて地域連携や共同化を検討する必要性あり
自治体
→総合事業の普及促進の強化
→人材育成や制度横断の仕組みづくりに事業者と取り組む必要性あり
■今後の流れ
・2025年度:補正予算で賃上げがどこまで反映されるか
・2026年度:当初予算でインフレ・賃上げ対応がどう整理されるか
・2027年度:2割負担の小幅拡大の可能性
・2028年度以降:上限制を組み合わせた拡大や制度改革が本格化
■事務局のまとめ
今回のセミナーから見えてきたのは、「財政抑制と処遇改善という矛盾をどう両立させるか」「短期の負担増と長期の体制改革が同時並行で進む」という大きな流れです。
介護事業者にとっては、制度改正を待つのではなく、いまから経営や人材戦略を柔軟に整えておくことが生き残りのカギになりそうです。
【お役立ち研修】
医療・介護の現場で活かせる実践的リハビリ評価&介入セミナー
第23回日本通所ケア研究大会
https://tsuusho.com/conference/