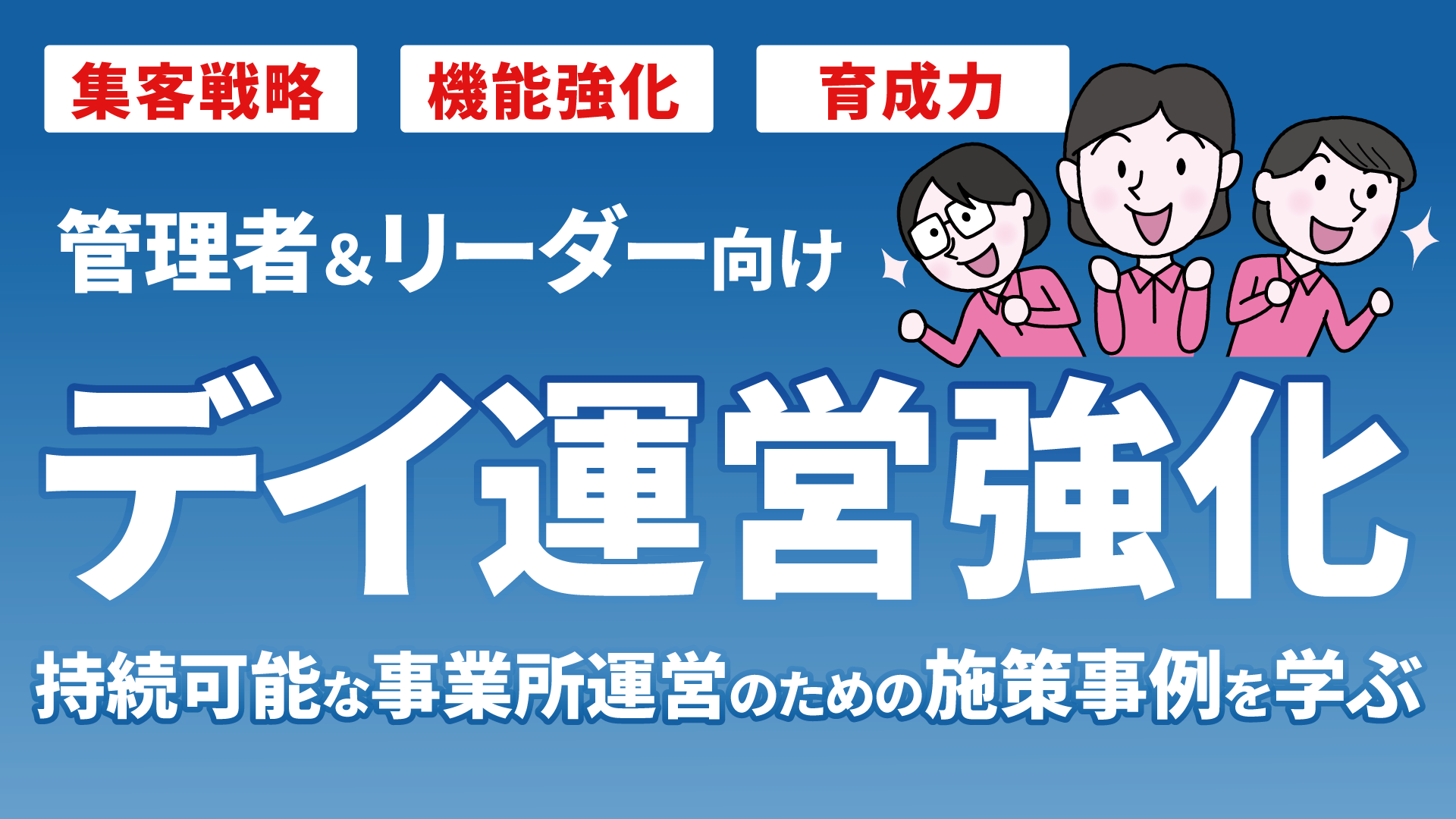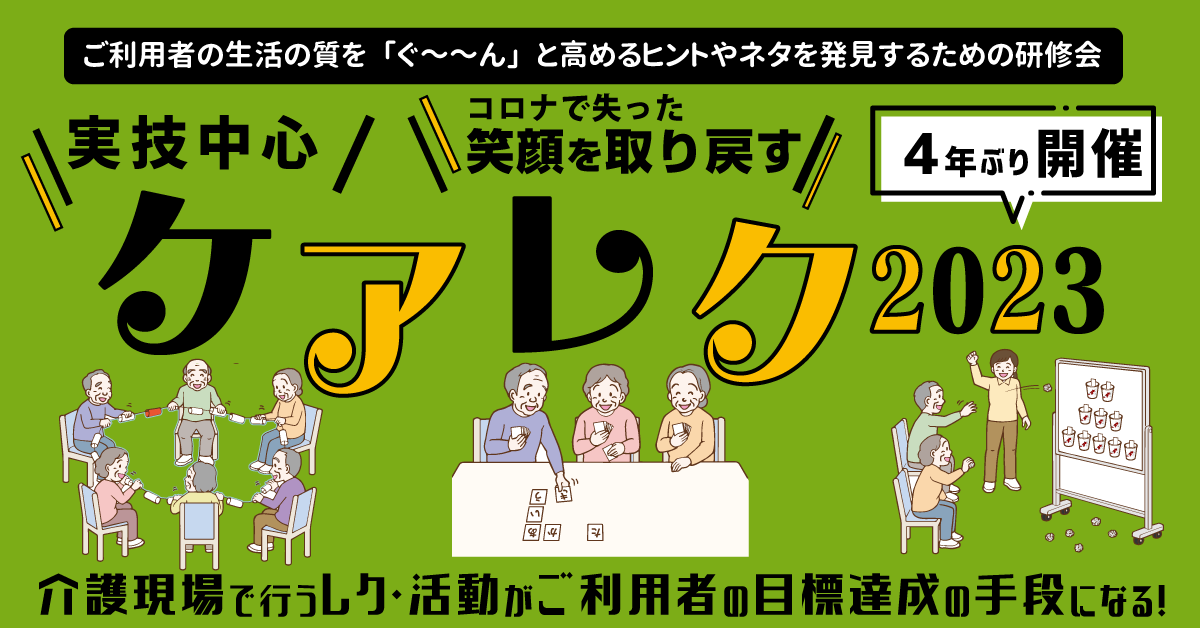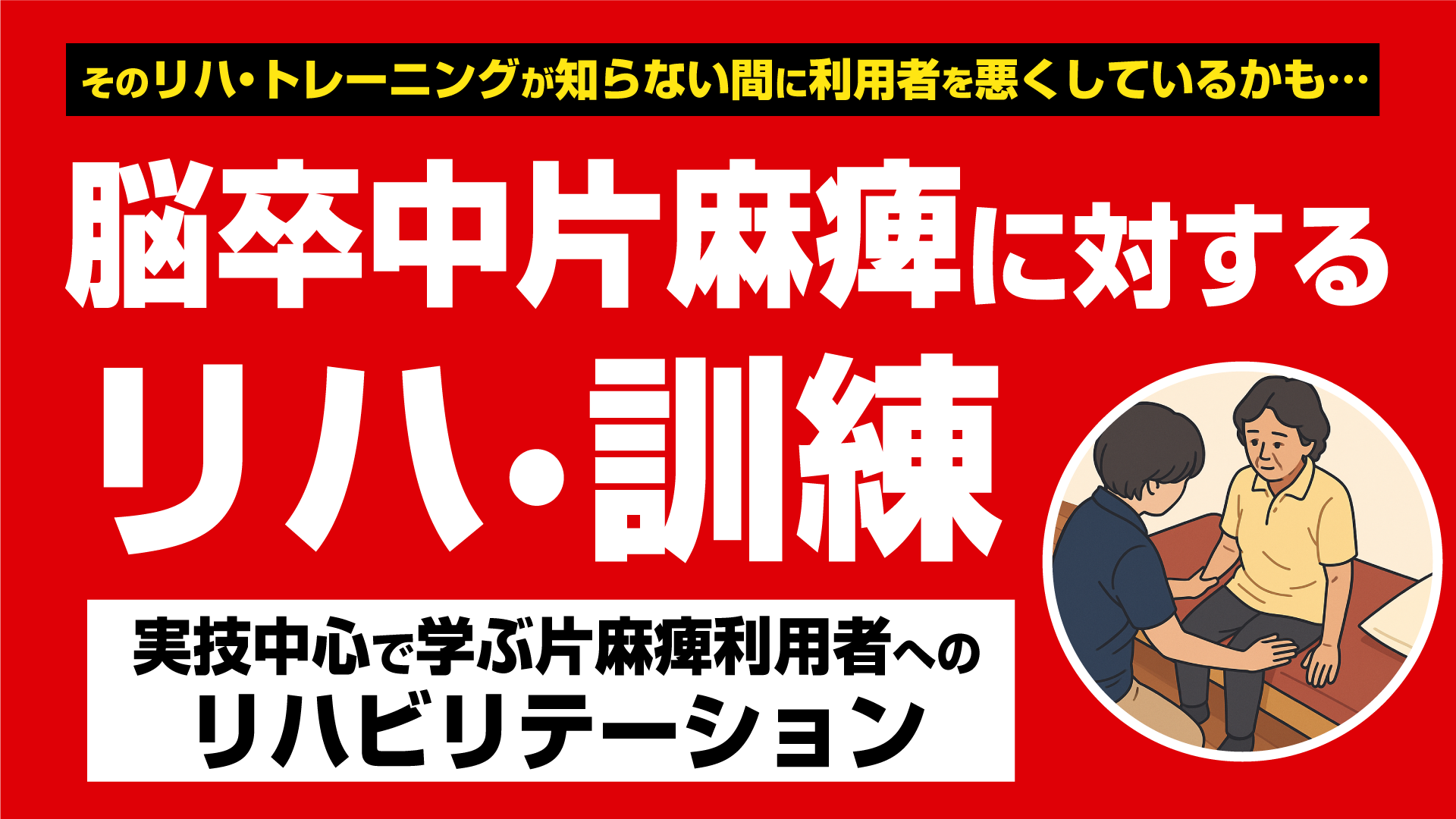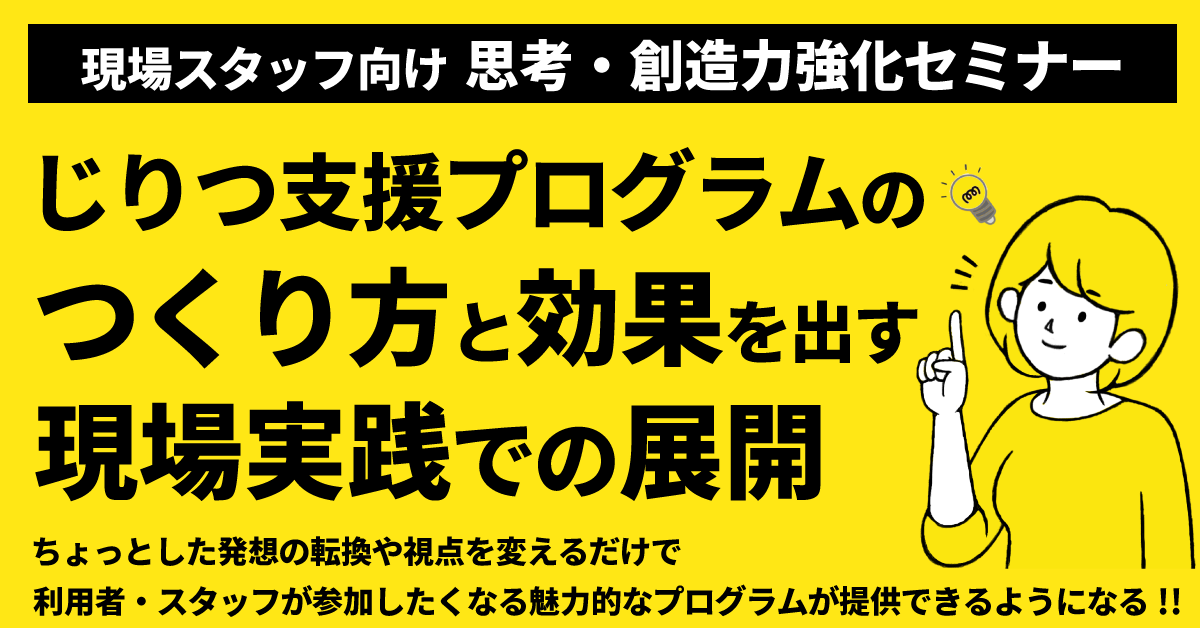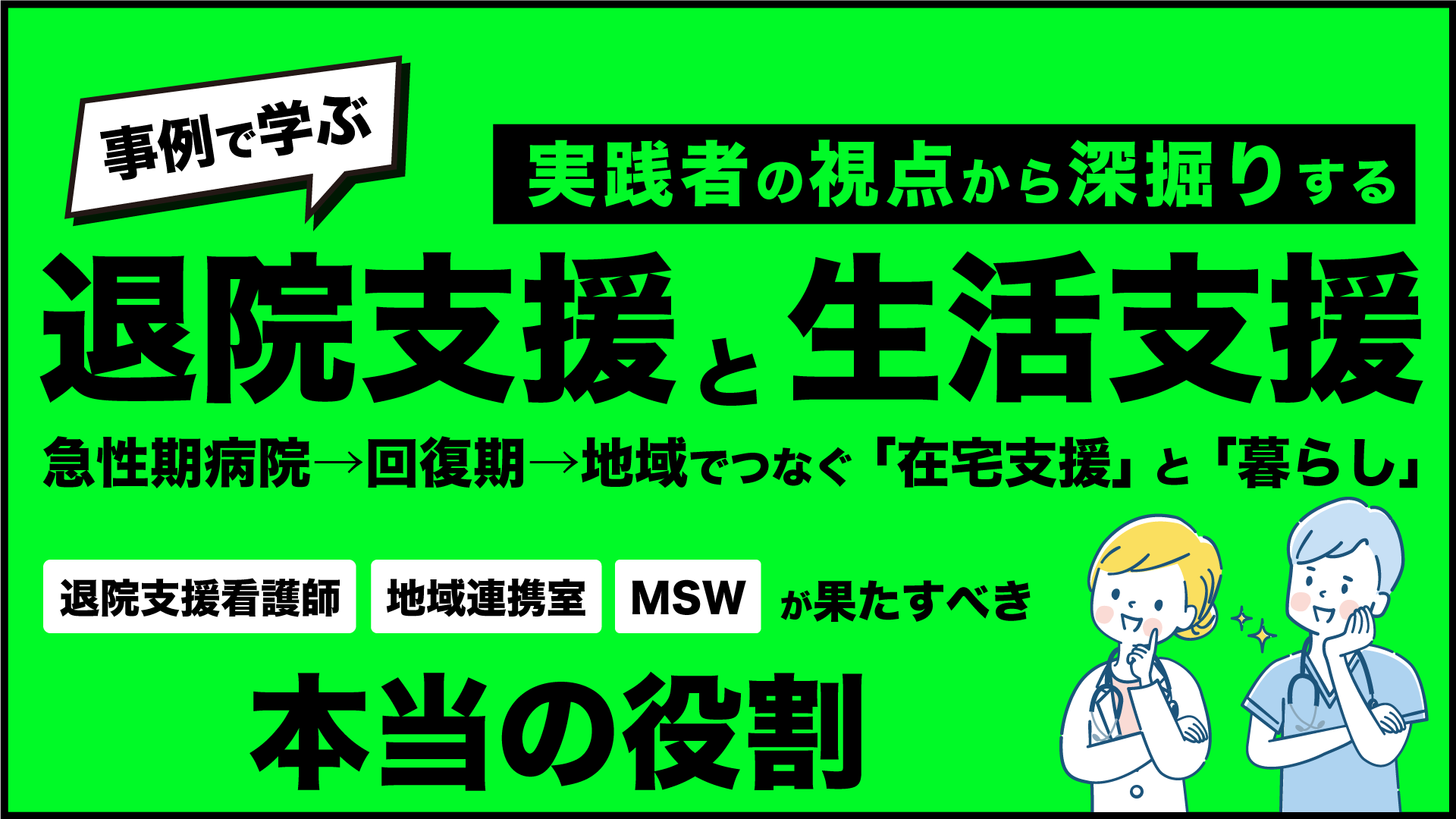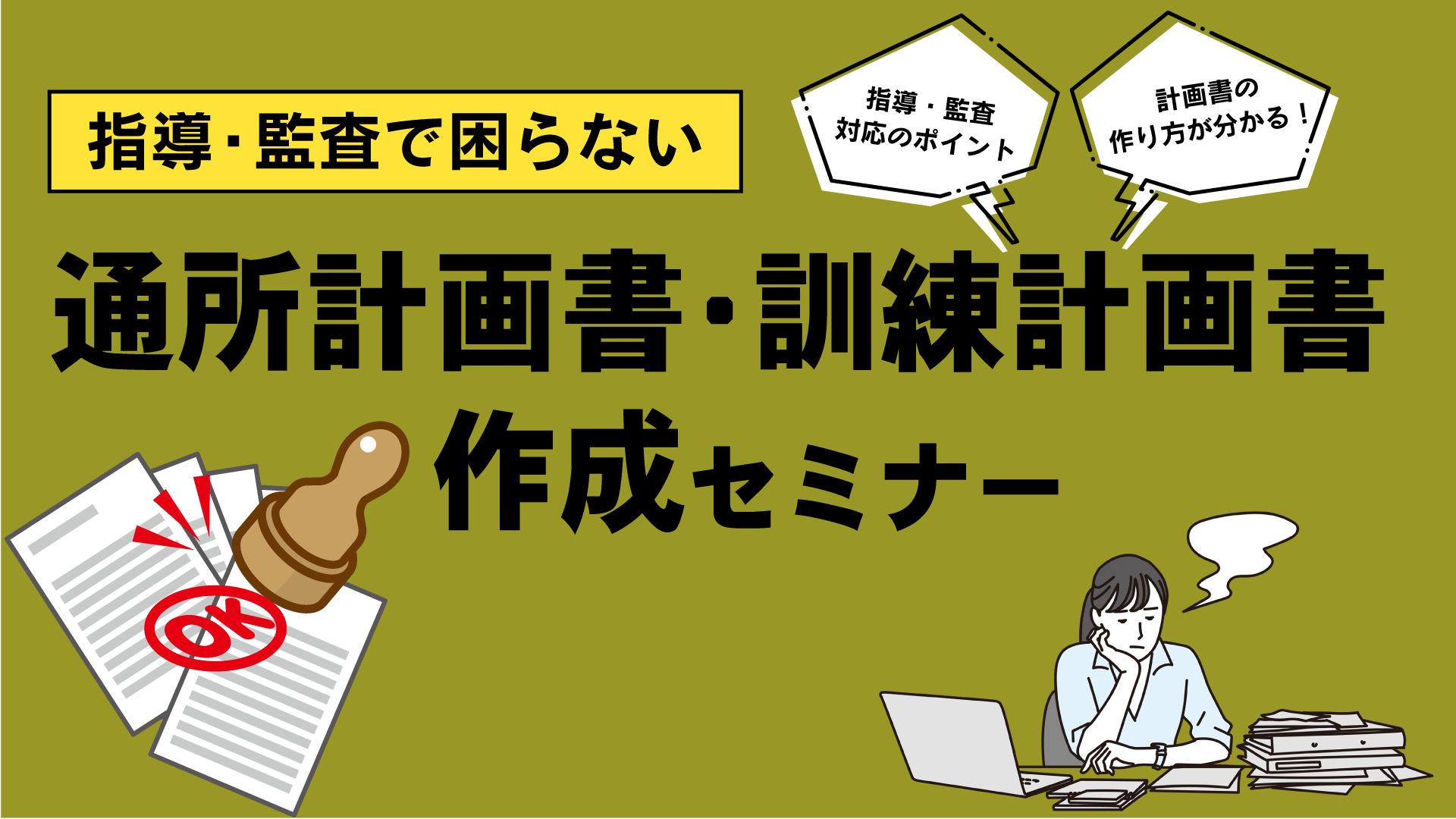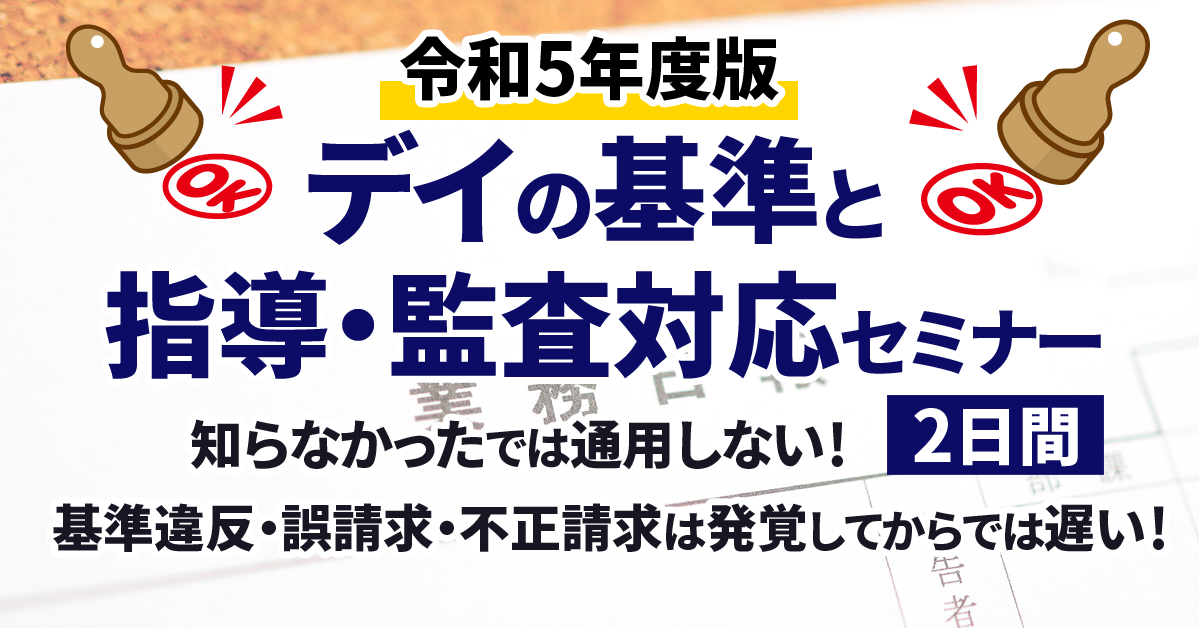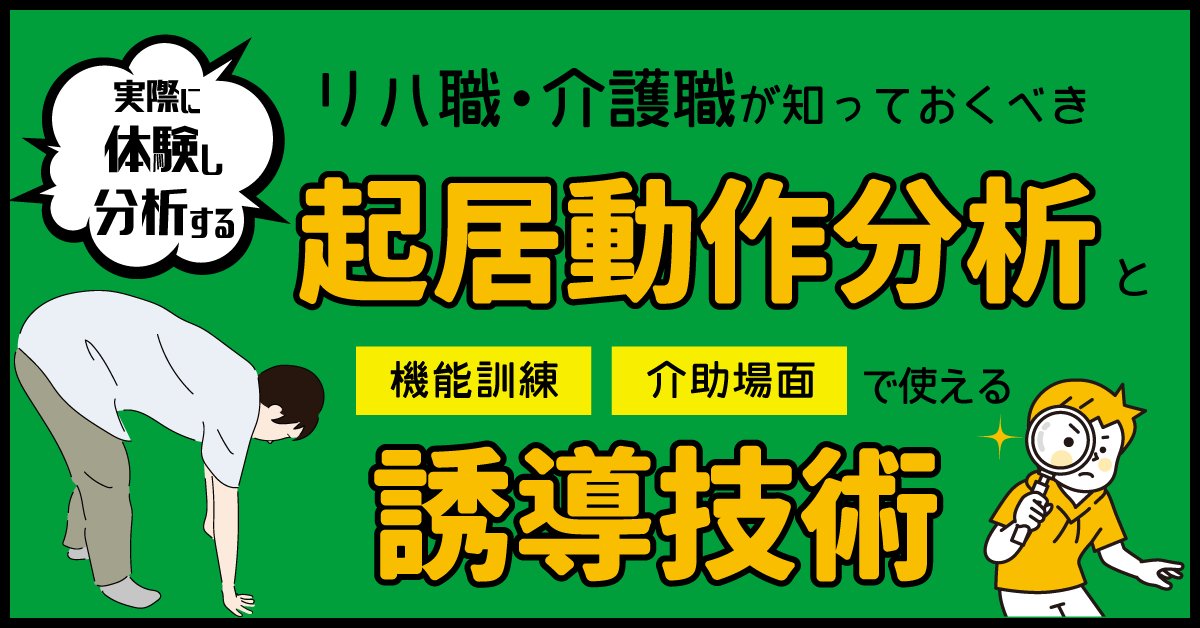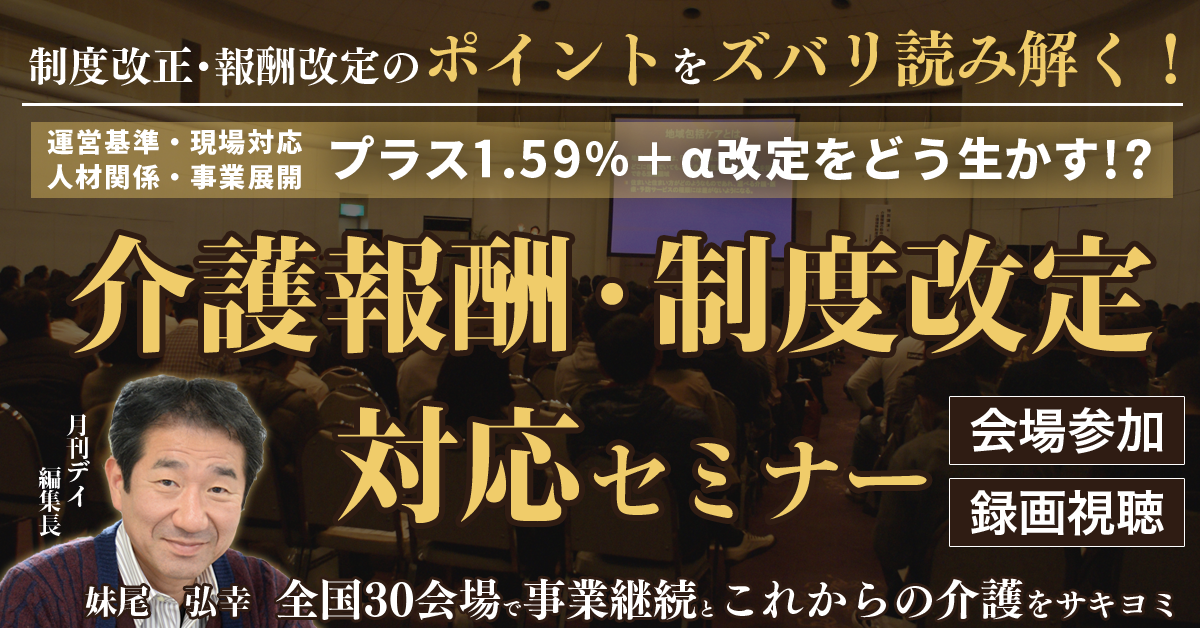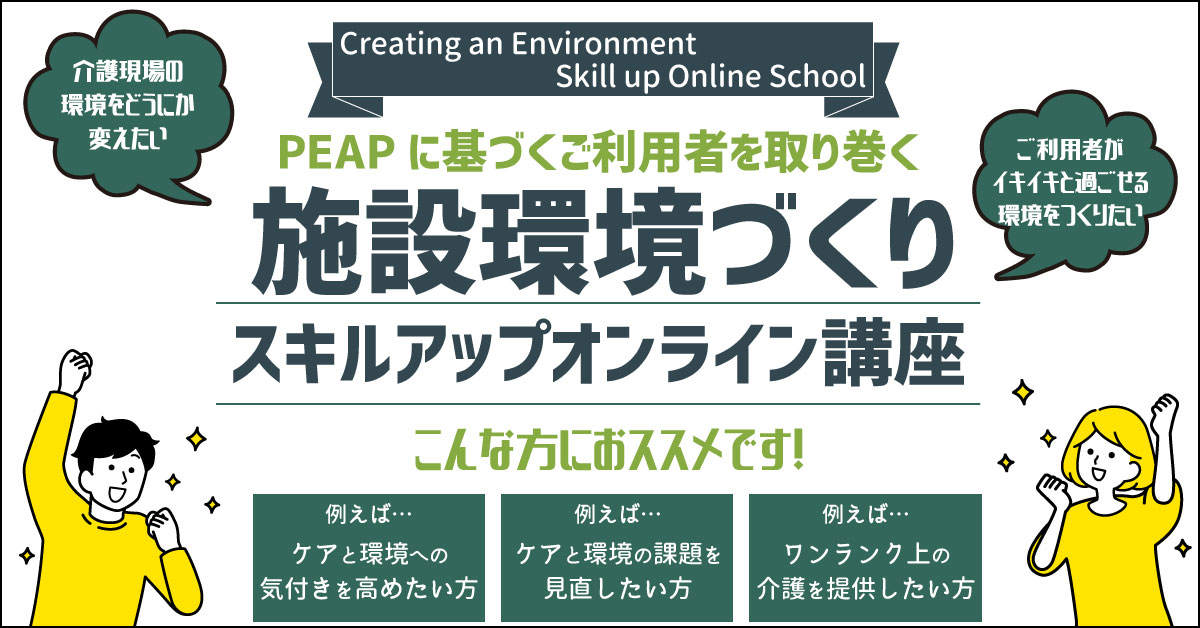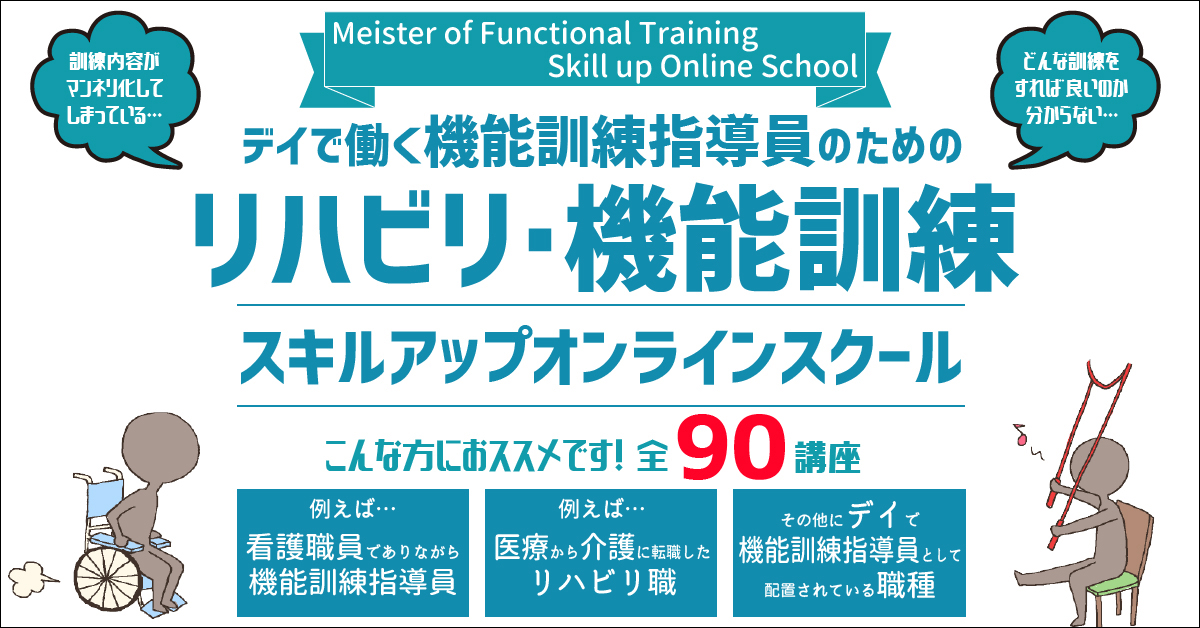「やらされレク」から「意味のあるレク」へ
■活動概要
山下氏はコンサルティング会社に所属しつつ、副業で法人を立ち上げ、現場改善や地域を巻き込む仕組みづくり(例:ペット用ジャーキー製作、新聞紙で作るエコバッグ)を展開している。目的は、施設の特色づくり、収益性の向上、採用や離職対策、地域との継続的な関係づくりなど多岐にわたる。
■ケアレクの考え方
山下氏は「誰もが参加でき、職員にも続けられるプログラム」を重視しており、集団レクではなく「個別性」に焦点を当てている。
理由としては、利用者の身体機能・認知症の度合いが多様である中、同一の活動を提供するのは無理があるため。
■活動の本質と継続性
例として挙げたエコバッグやジャーキーづくりも、「楽しさ」や「利用者の満足感(CS)」、職員の意識改革(質の高いものを提供する意識づけ)につながる取り組みである。
レクは単なる「イベント」ではなく、「価値ある体験」にする必要があると指摘。
■「おやつの時間」への疑問
山下氏は「おやつを15時に出す」という慣習を問い直す。
多くの施設では理由もわからず習慣的にこの時間におやつを出しているが、これはスタッフ都合であり、パーソンセンタード(利用者中心)とは言えない。
本来は「食べたい時に食べる」べきであり、活動を中断してまで出す意味は薄いと主張。
例として「保育園のしつけ」と同じような発想だと問題提起。
■「レク」という言葉への違和感
「○○レク」といった名称が多用されているが、レクリエーションという言葉自体が日常生活からかけ離れている場合もある。
「自分が利用者だったらどう感じるか」という視点を忘れてはいけないと警鐘を鳴らす。
■メッセージ
従来型の介護の枠にとらわれず、「利用者主体」「本質を捉えたプログラムづくり」を再考することが重要。
職員の意識や組織の体質の変化が、より良いケアと働きがいのある職場づくりにつながる。
【動画】
【お役立ち研修】