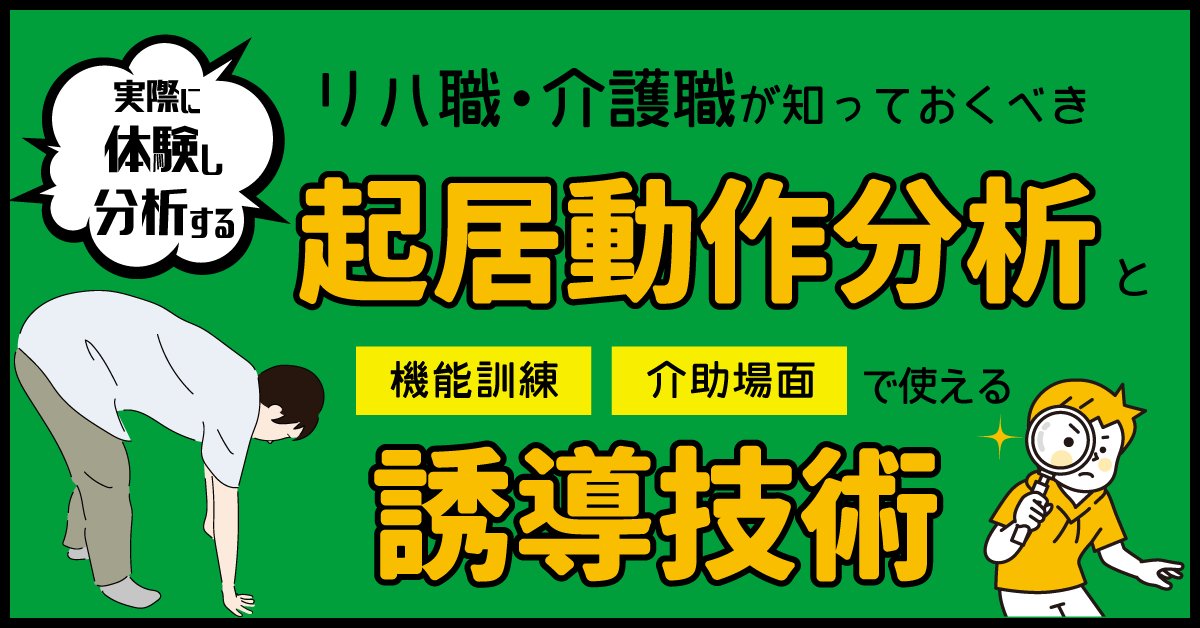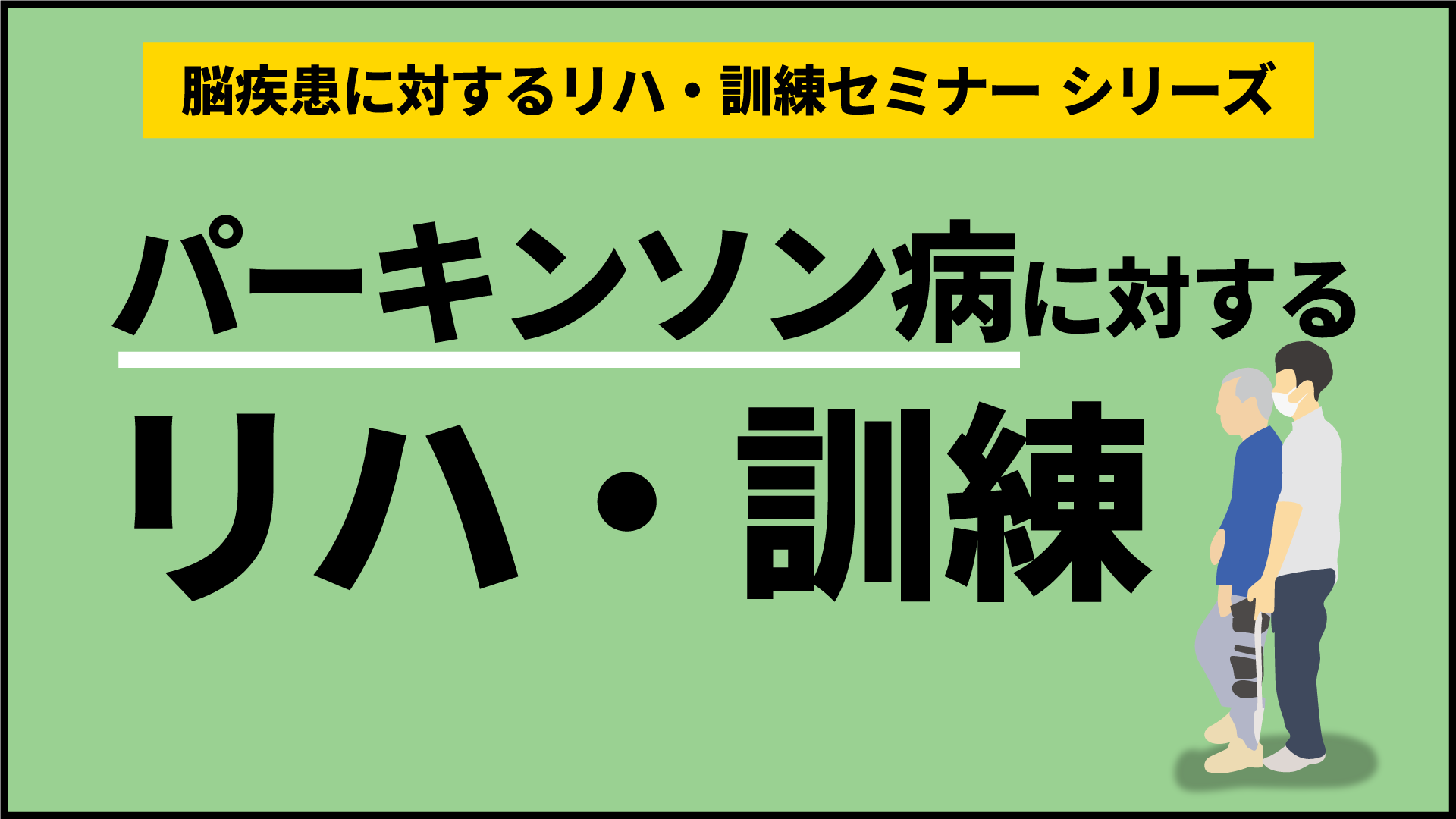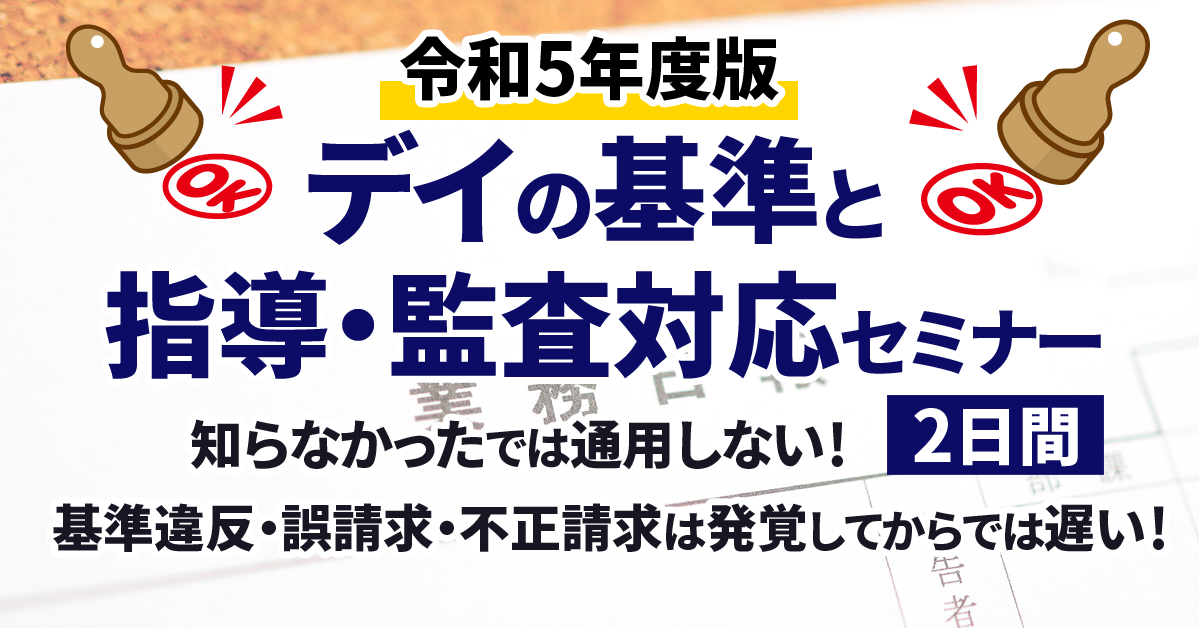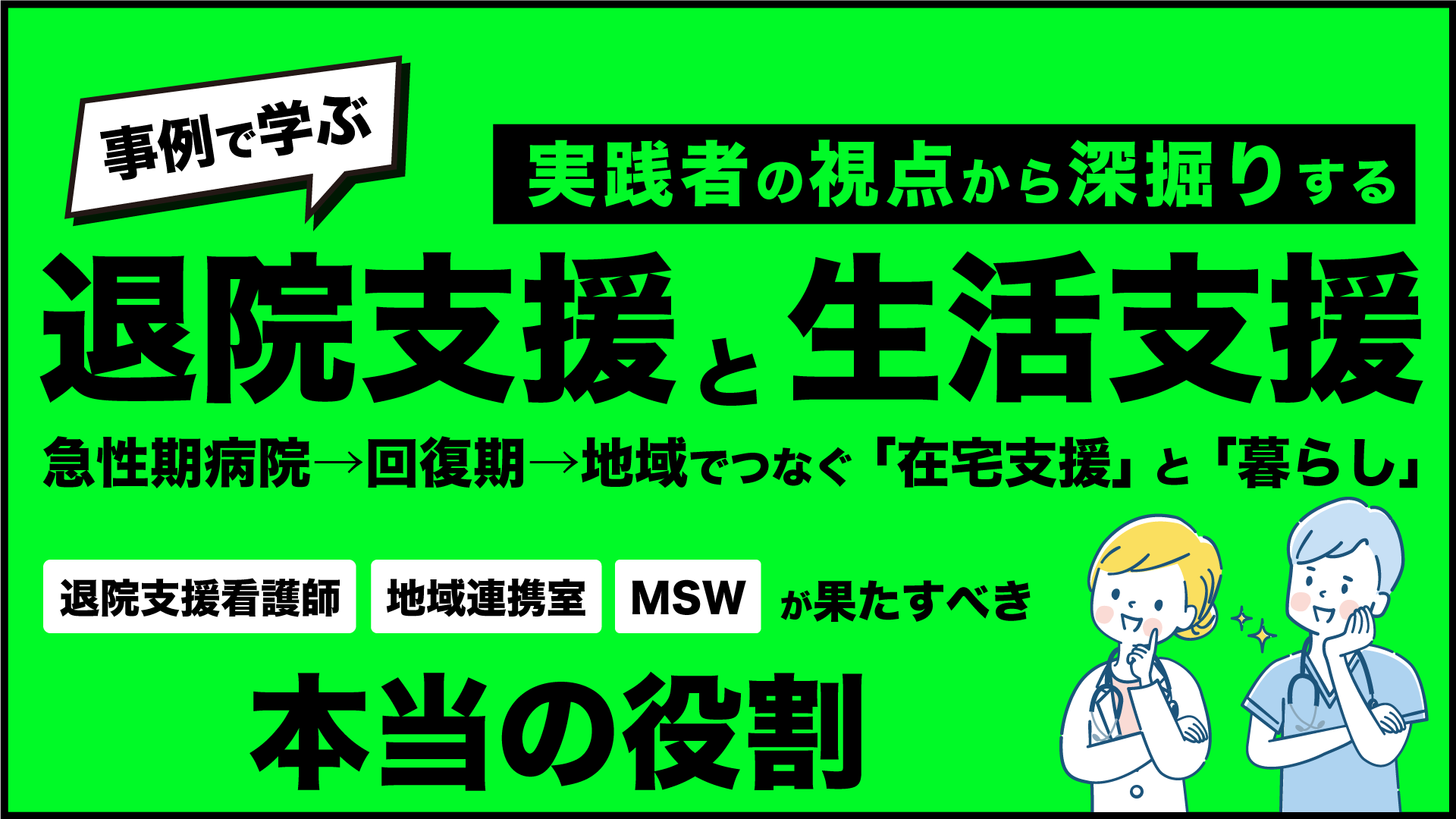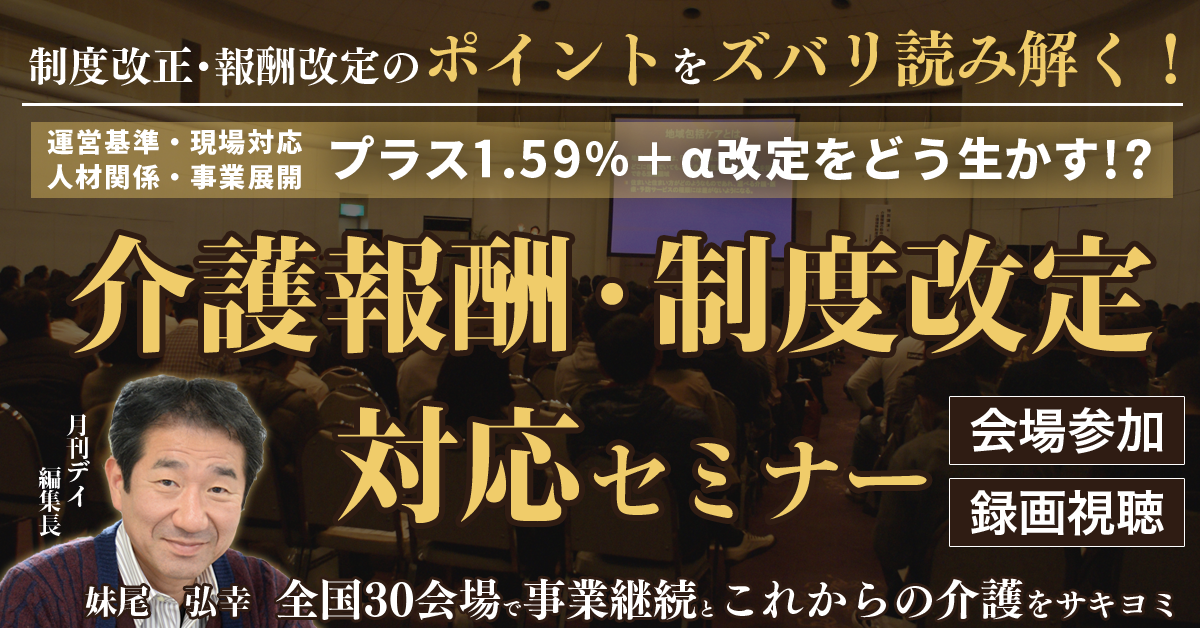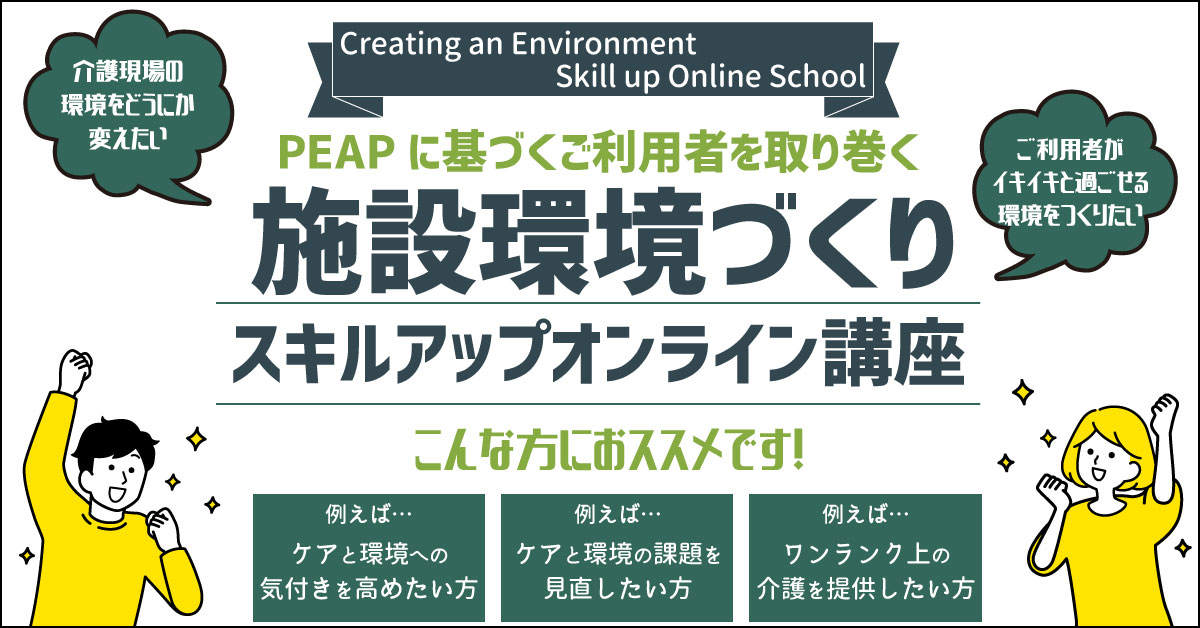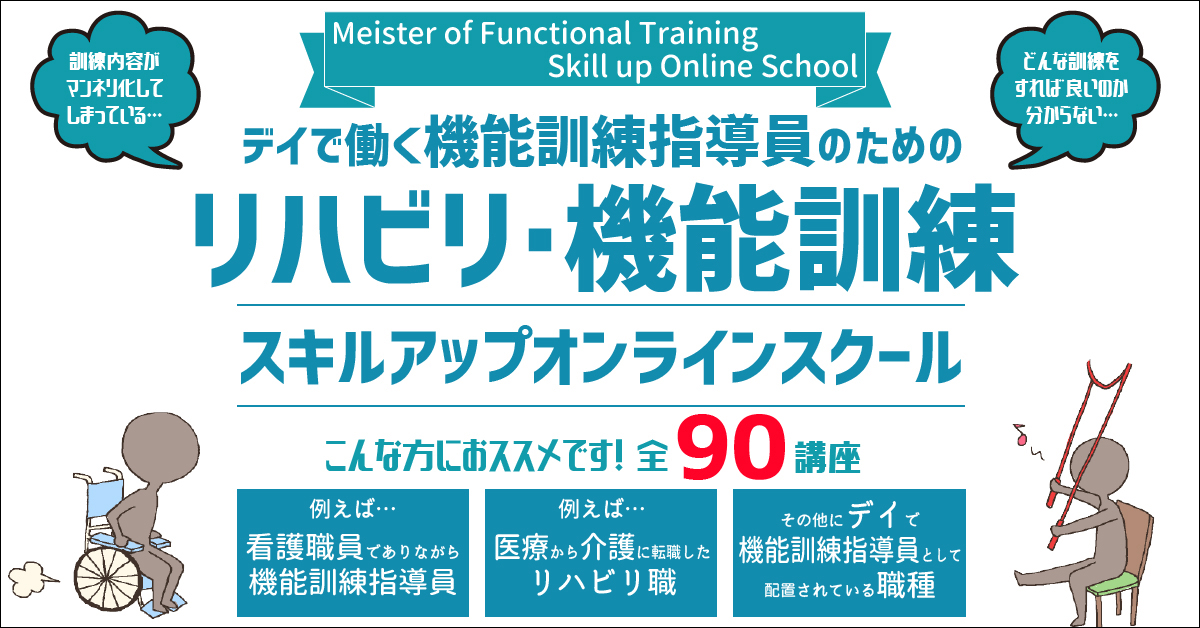健康寿命”を延ばすために、今できること
要介護の原因ランキングから見える現実
在宅に戻った高齢者の多くが、「要支援」「要介護」の認定を受けています。
その背景には、さまざまな病気や生活要因があります。
データをもとに、その原因をランキング形式で見てみましょう。
1位:認知症
2位:脳血管障害
3位:転倒・骨折
4位:高齢による衰弱
5位:関節疾患
1位の「認知症」は高齢化の進行とともに確実に増えています。
2位の「脳血管障害(脳卒中など)」は減少傾向にあるものの、3位の「転倒・骨折」は今後も増えると予測されています。
意外な落とし穴…第5位「関節疾患」
一見、割合としては少なく見える「関節疾患」。
しかし、要介護の前段階である「要支援」の原因としては第1位を占めています。
つまり、関節疾患は「最初のつまずき」と言える存在です。
膝が痛い、腰が重い
こうした症状が続くと、外出がおっくうになり、家事や買い物などの生活動作も減っていきます。
その結果、活動量が低下し、心身の機能がじわじわと衰えていく。
この流れこそが、要介護へとつながる“見えない坂道”なのです。
重度化を防ぐために「自分でできる間」に行動を
関節疾患の怖いところは、「痛みを我慢して動かない」ことで進行が早まる点です。
だからこそ大切なのは、本人が自分でできるうちに予防や運動を続けること。
認知症が進行してからでは、セルフケアが難しくなります。
少しでも早く対策を始めることで、健康寿命を“先送り”できる可能性が高まります。
「触るだけ」ではない、リハビリの新しい考え方
関節疾患のリハビリというとどうしても「施術」や「マッサージ」といった「触る支援」を思い浮かべがちです。
しかし実際には、「触らないアプローチ」も重要です。
たとえば「生活動作そのものを見直す」「痛みの少ない姿勢や動きを指導する」など本人が自分の体と向き合い、日常生活の中で調整していく支援です。
これは生活期リハビリテーションの本質とも言える部分。
つまり、医療者が支えるだけでなく、本人が「自分で動ける時間」をどう伸ばすかに焦点を当てることが、今後ますます求められていくのです。
最後に…健康寿命を伸ばす一歩を
要介護の原因を見ていくと、どれも日常生活の延長線上にあることが分かります。
「認知症」「骨折」「関節疾患」。
どれも「気づいた時には進んでいた」と感じる人が多いもの。
だからこそ、今のうちから身体を守る習慣を始めてほしい。
関節の痛みを軽視せず、正しい知識と予防の意識を持つことが、これからの健康寿命を大きく変えていきます。
【情報提供元】
【要介護になる原因ランキング】第1位は認知症、第5位に意外な落とし穴
【お役立ち研修】
医療・介護の現場で活かせる実践的リハビリ評価&介入セミナー
第23回日本通所ケア研究大会
https://tsuusho.com/conference/