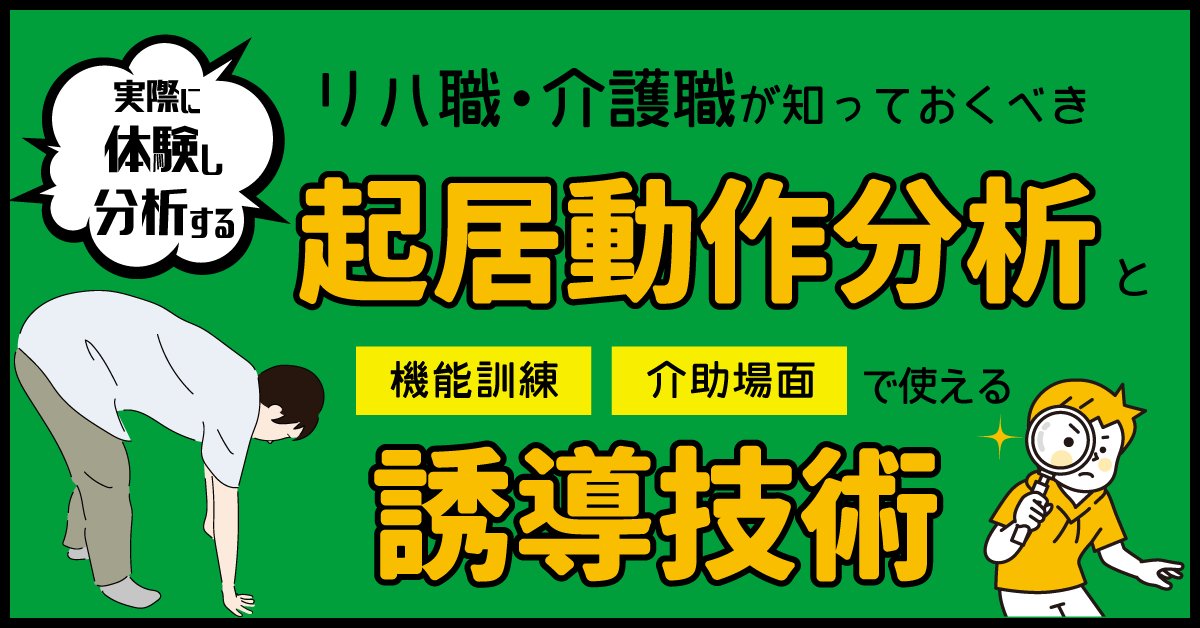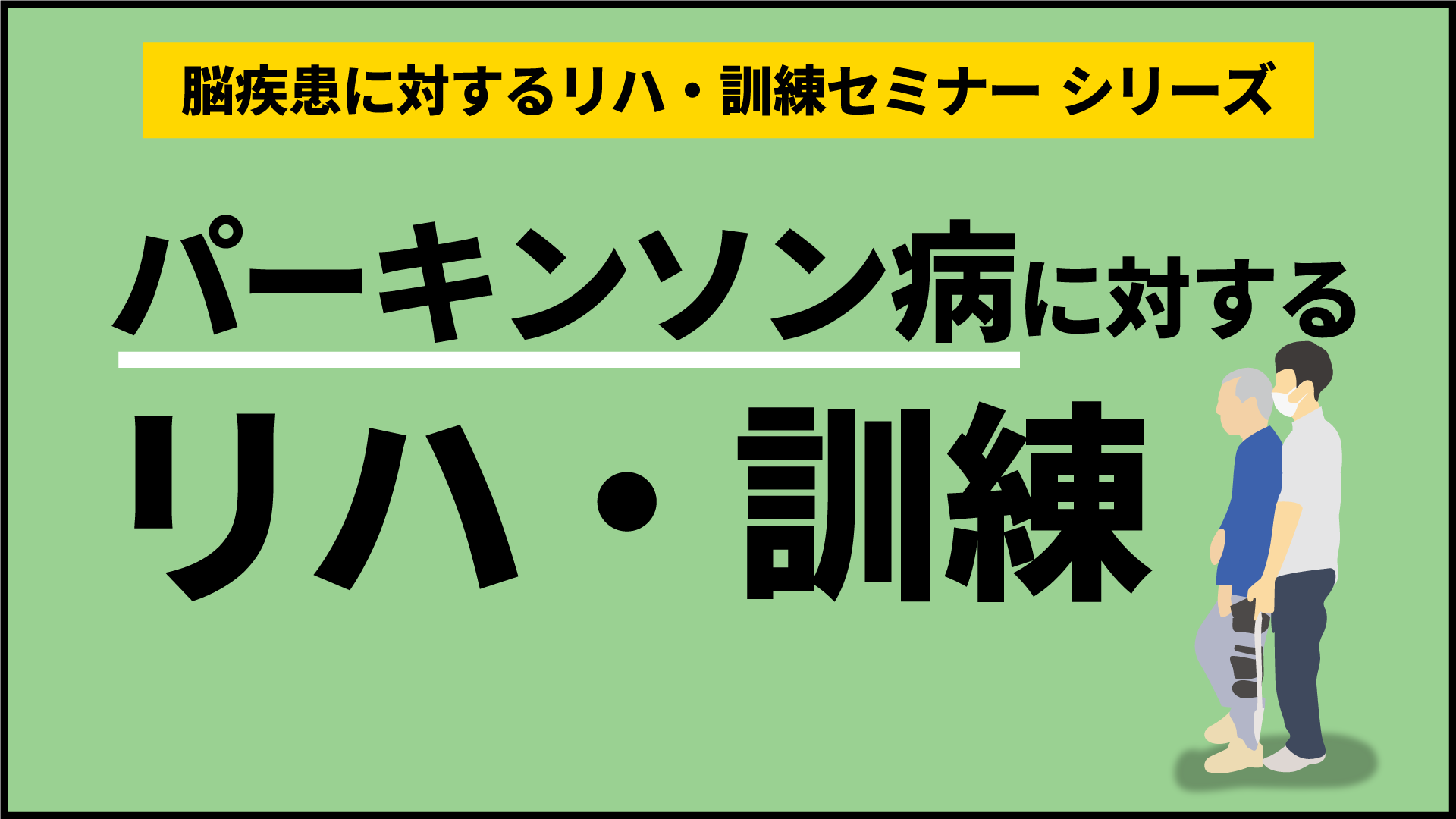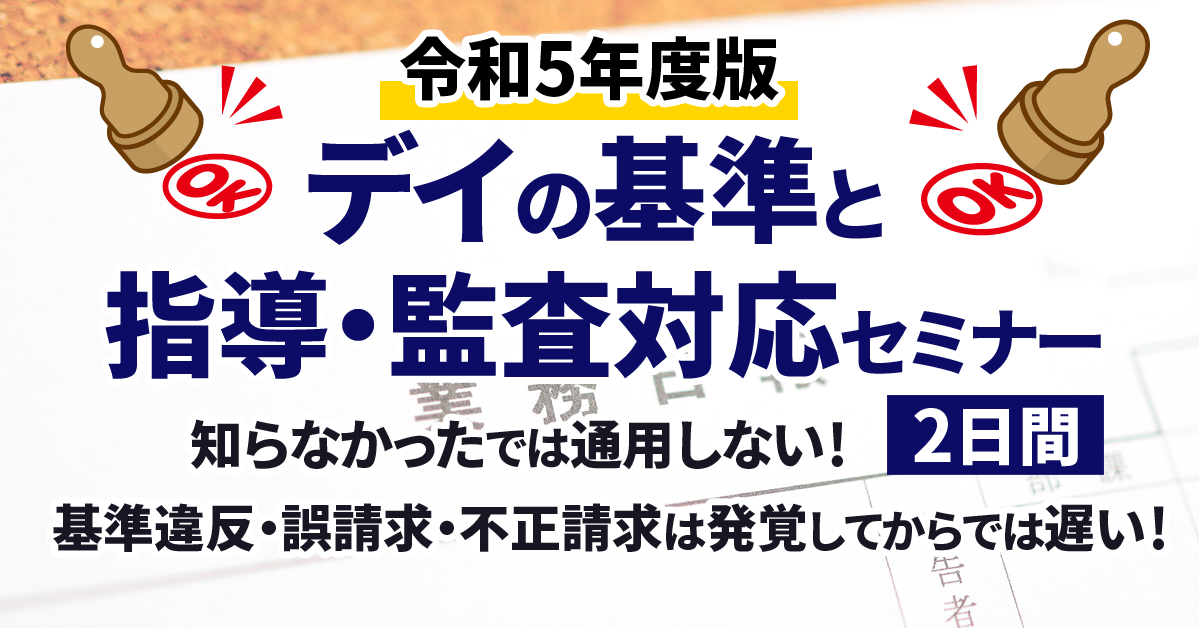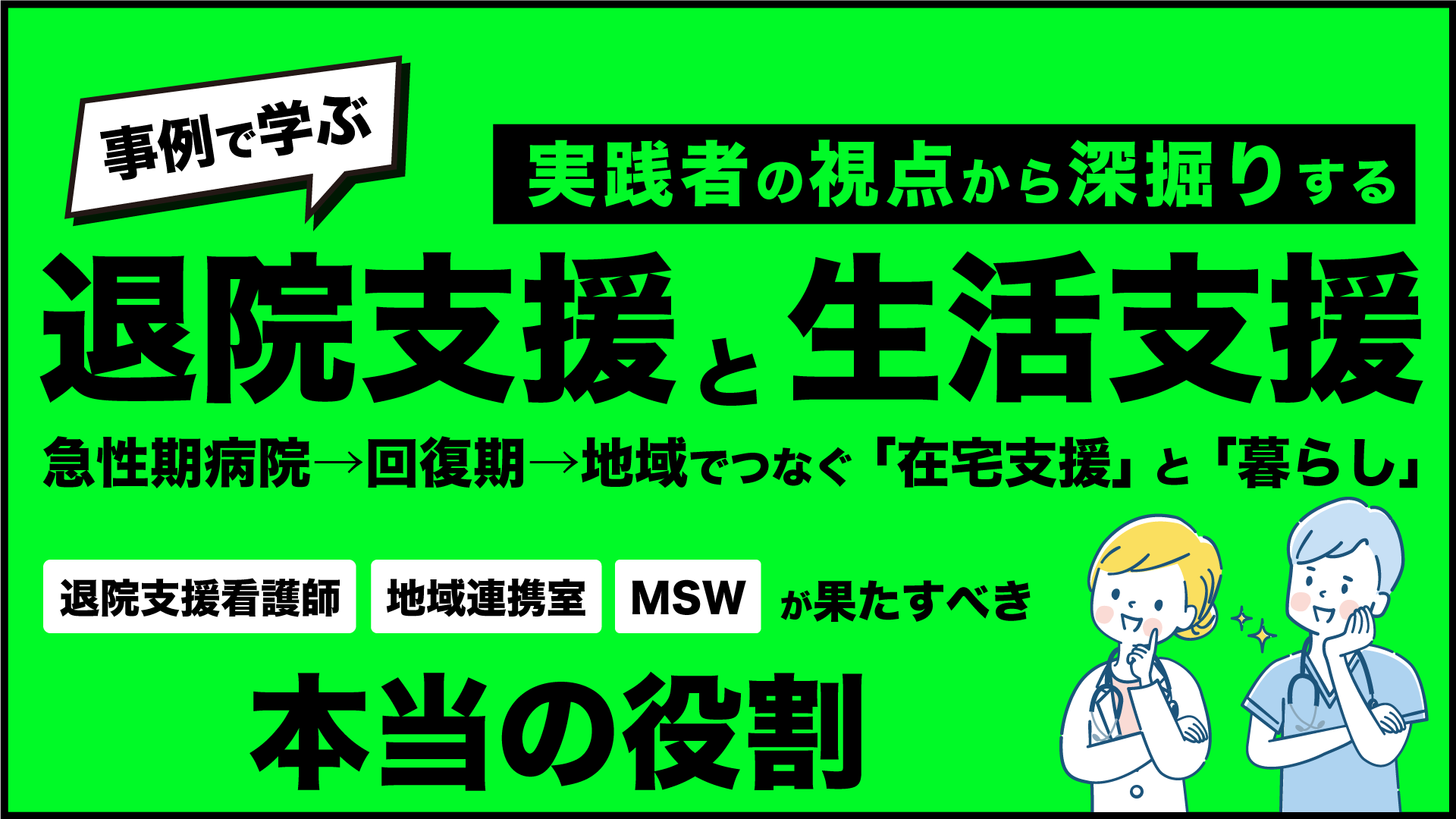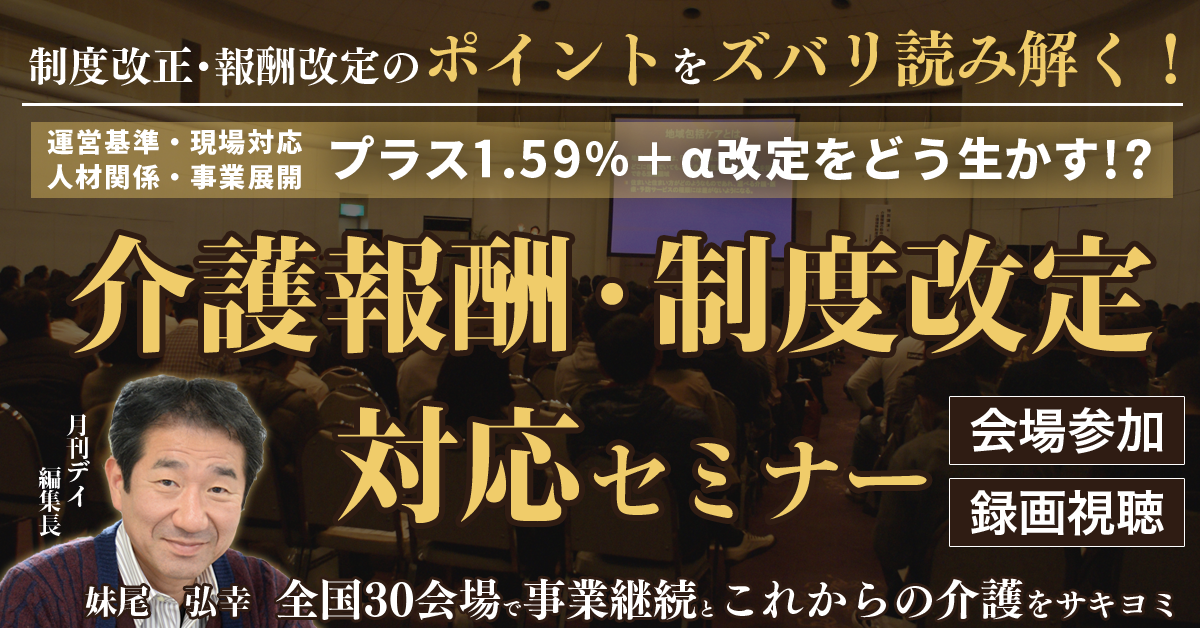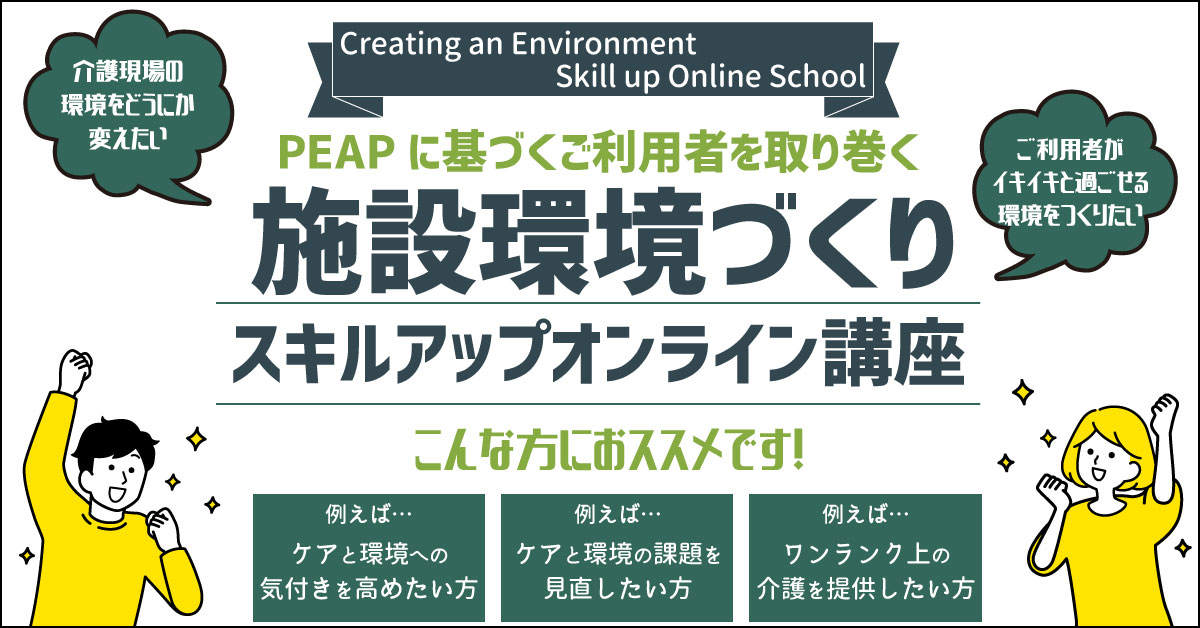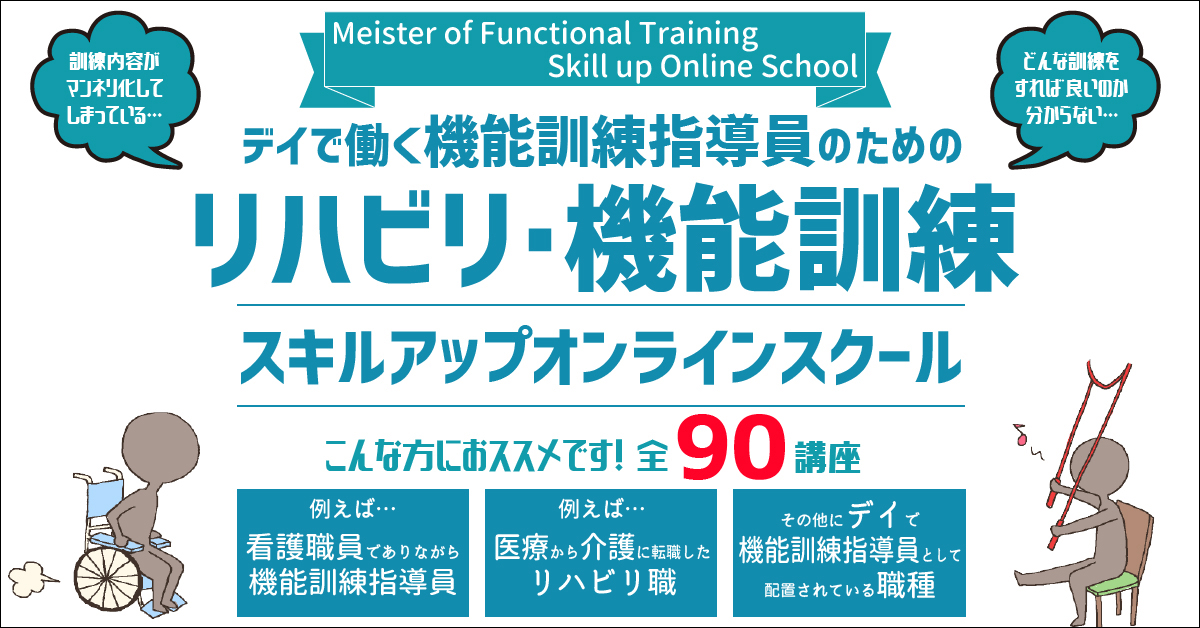2025年9月30日、事務局の小川がサービス付き高齢者向け住宅(住宅型)3棟の住宅課・介護保険課による立ち入り検査(運営指導)に立ち会いましたので、立ち入り検査で指摘されるポイントなど最新の情報を一部共有させていただきます。
ネット上にはあまりサービス付き高齢者向け住宅の立ち入り検査における具体的で有益な情報がなかったため、この情報を共有することが、サービス付き高齢者向け住宅を運営される事業者にとっても有益と考えていますので、ぜひ参考にしてください。
※自治体によっては指導の視点が違うかもしれませんので、ご注意ください
【サービス付き高齢者向け住宅の定義】
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき都道府県、政令市、中核市の登録を受けた賃貸等の住宅。
一定の規模や設備、バリアフリー構造を備え、状況把握サービスと生活相談サービスを提供。
入居できるのは60歳以上の方、要介護・要支援を受けている方の入居を対象。
同居者についても、配偶者や60歳以上の親族などの条件あり。
一方で、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)でも、有料老人ホームの定義に該当するサービスを提供している場合は有料老人ホームと見なされ、有料老人ホームとしての指導監督の対象となる。(食事の提供、介護の提供、家事の供与、健康管理の供与のうち、いずれか1つでも実施している場合、老人福祉法に基づく有料老人ホームに該当)
【住宅課によるハード面の確認】
・手すりの高さや居室の構造、食堂の通路幅(通路確保:75cm)を実測
・指定を受けるために提出している図面と現地の整合性
・バルコニーの寸法も測定
※提出している建築図面と実測値に相違がないかを要確認される
※机やイスの配置は細かくチェックされる
【介護保険課によるソフト面の確認】
※老人福祉法に基づく点検(介護保険法については問わない)
[1]食事・献立について
献立表と実際の提供内容の確認
[2]料金・契約関連
・重要事項説明書・入居契約書・料金表に相違がないか徹底チェック
・食費等の値上げ実施分の届出やサービス付き高齢者向け住宅情報提供システムへの反映漏れがないか
・料金表には「住宅に入居しているからこそ受けられるサービス内容」を整理して記載すること(介護保険の上乗せ分で受けれるものと一緒に記載しない)
・介護保険サービスでかかる費用との区別を明確にすること
※パンフレット等にモデル例として「要介護○の方は1ヵ月にかかる費用は○○円です」などの記載例を良く見かけるが、この表示では不適切。
→掲載するなら「※介護保険サービスを受けられる場合は介護保険事業所と別途契約が必要」と明記する必要あり
<ポイント>
・入居者、家族と料金に関連するトラブルが近年多く見られる傾向にある
・誇大広告や景品表示法などに該当しないよう「住宅で受けられるサービス」と「介護保険適用サービス」を明確に分ける必要がある(家族や身元保証人などに法律の専門家などが多くなっているケースやネット上に様々な情報が出回っているため、そういった方々の知識がついてきている)
[3]重要事項説明書の確認
・職員数は常勤換算ではないので、住宅サービスにかかわる人数を実人数で記載する必要あり
・「サービス等の内容」について、「入浴、排せつ又は食事の介護」「食事の提供」「洗濯、掃除等の家事の供与」「健康管理」「安否確認又は状況把握サービス」「生活相談サービス」の欄は、住宅が行っているものを正しく選択して記載すること
→ここの選択を正しく選択できていない、理解していない事業者が多いとのこと
・重要事項説明書のテンプレートにある「別添2」の料金表が使いにくい場合は、自社で用意した別紙料金表を合わせて添付することで、代用することができる
・家賃やメンテナンス料の根拠を正しく明記すること(管理規定等への記載でOK)
・事故発生時の対応方針を記載する必要あり
・「有料老人ホームの設置運営標準指導指針」の変更部分など国・行政などの通知にしっかり対応すること
[4]入居契約書・サービス内容の契約等について
・夜間対応は「緊急通報システム」なのか「夜勤職員配置での対応」なのか、正しく表現すること(夜勤者配置と誤解されないよう注意)
・生活支援サービスについては「どこまで対応するか」を明確化しないとトラブルになる可能性がある(例:入居者が把握できるチェック表などを用意するのも一つの手段)
[5]運営関連について
・年間研修計画(施設内外・個別の研修など)の確認
・運営懇談会は同一法人内の他部署開催の運営推進会議等と同時開催をしても良いが、記録物としては「住宅に特化した開催記録」等を残す必要あり
・苦情や事故対応についても「住宅に特化した記録」として保存すること
・個人情報の教育・メンタルヘルス対応、ハラスメント、高齢者虐待(身体拘束含む)、業務継続計画、新興感染症対策についての医療連携などのヒアリングあり
・重要事項説明書や契約書等内の表記方法(配薬・内服、管理費・共益費など)は行政の指導に合わせて整理するのが望ましい
・入居者、家族目線で分かりやすい料金表やサービス内容の提示を心掛けること
【お役立ち研修】
医療・介護の現場で活かせる実践的リハビリ評価&介入セミナー
第23回日本通所ケア研究大会
https://tsuusho.com/conference/