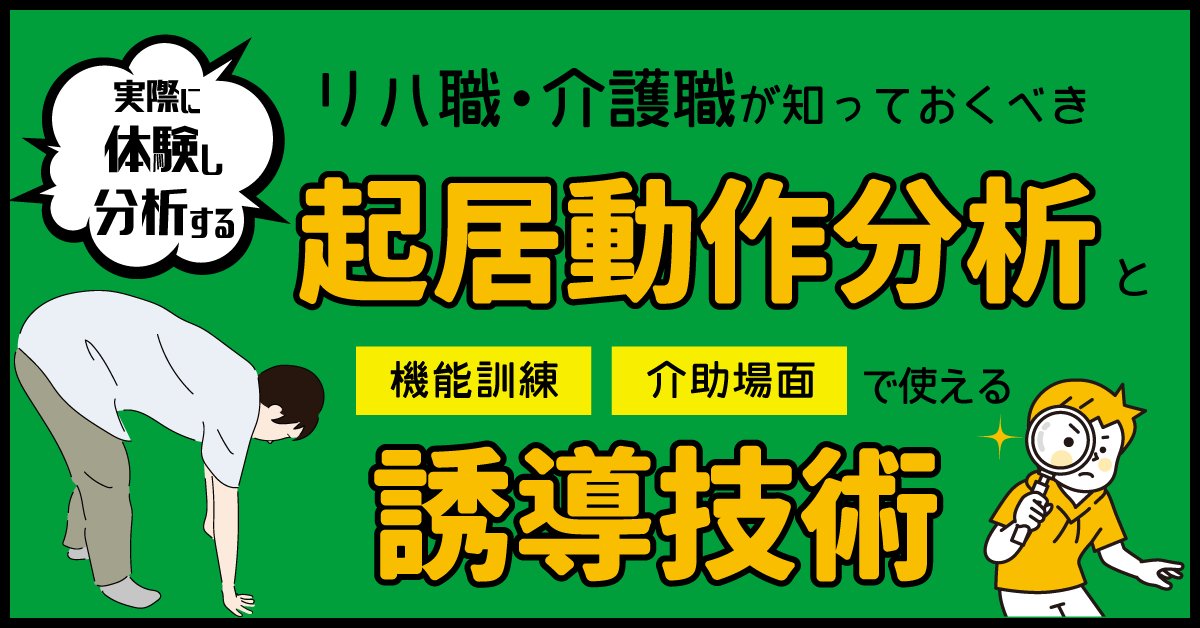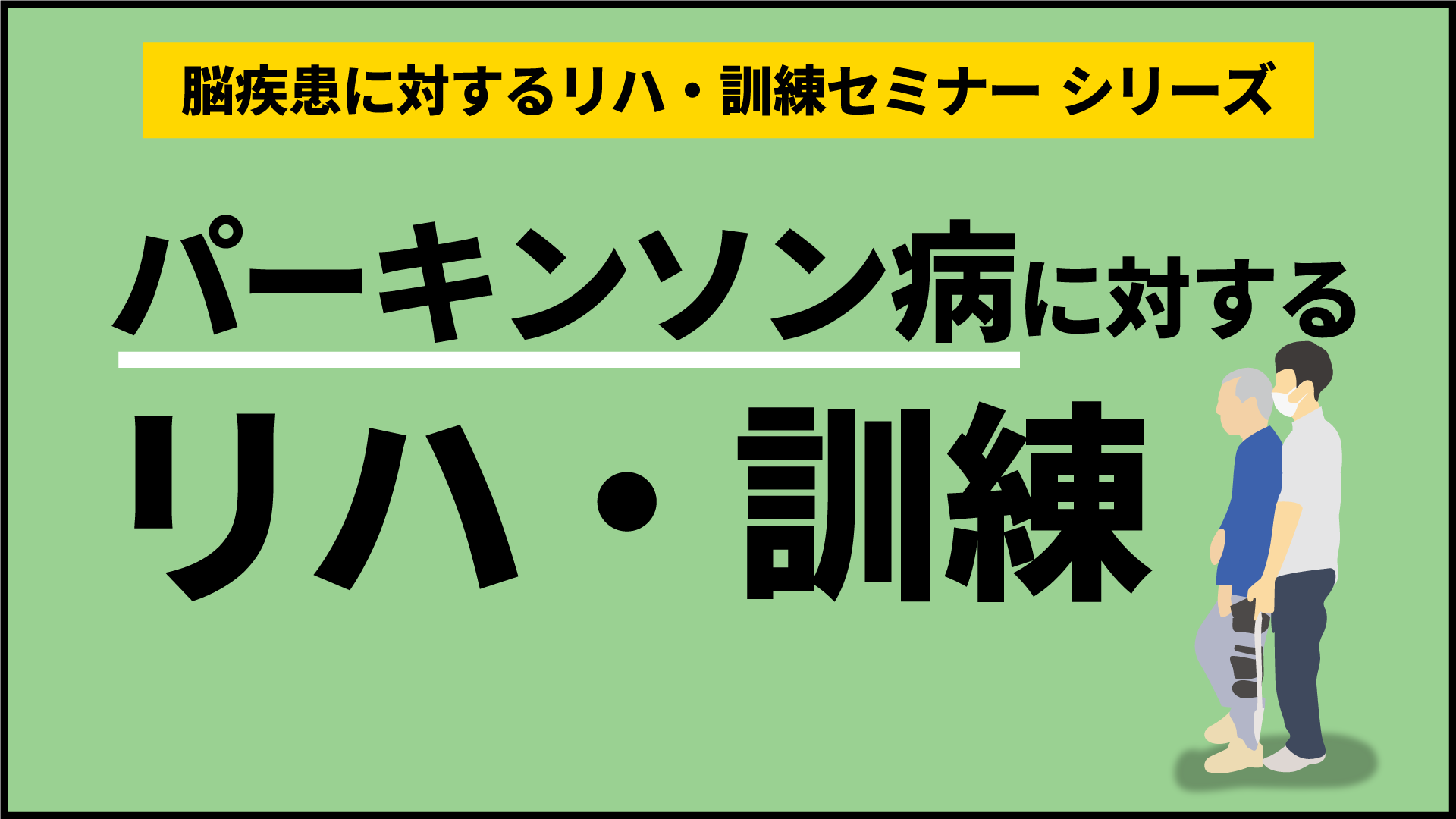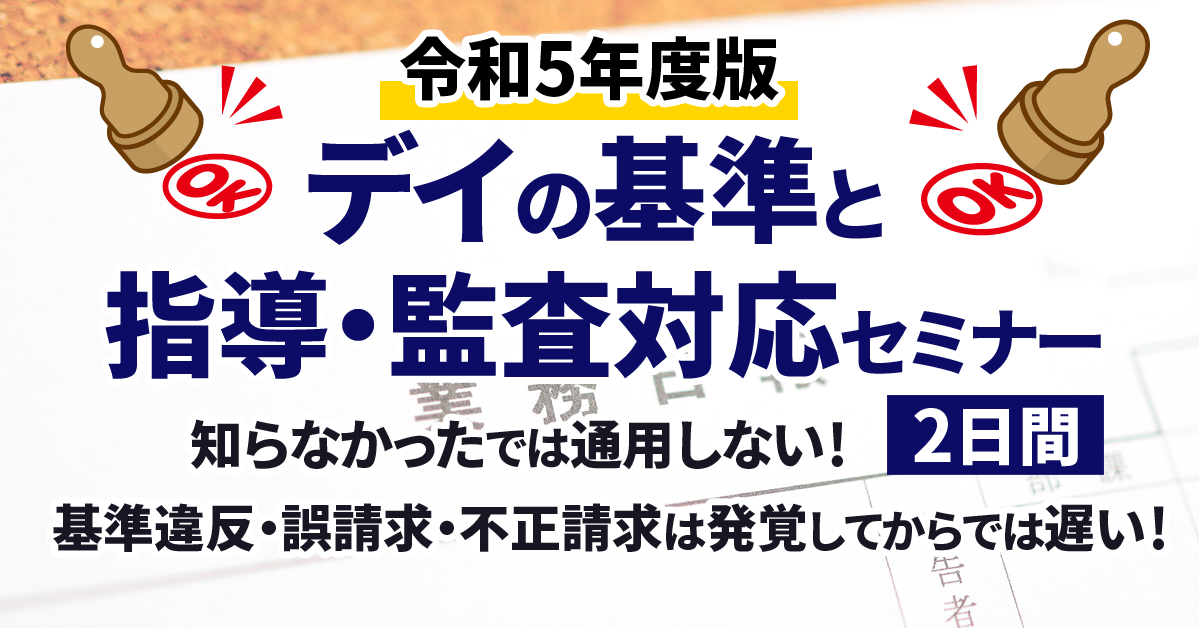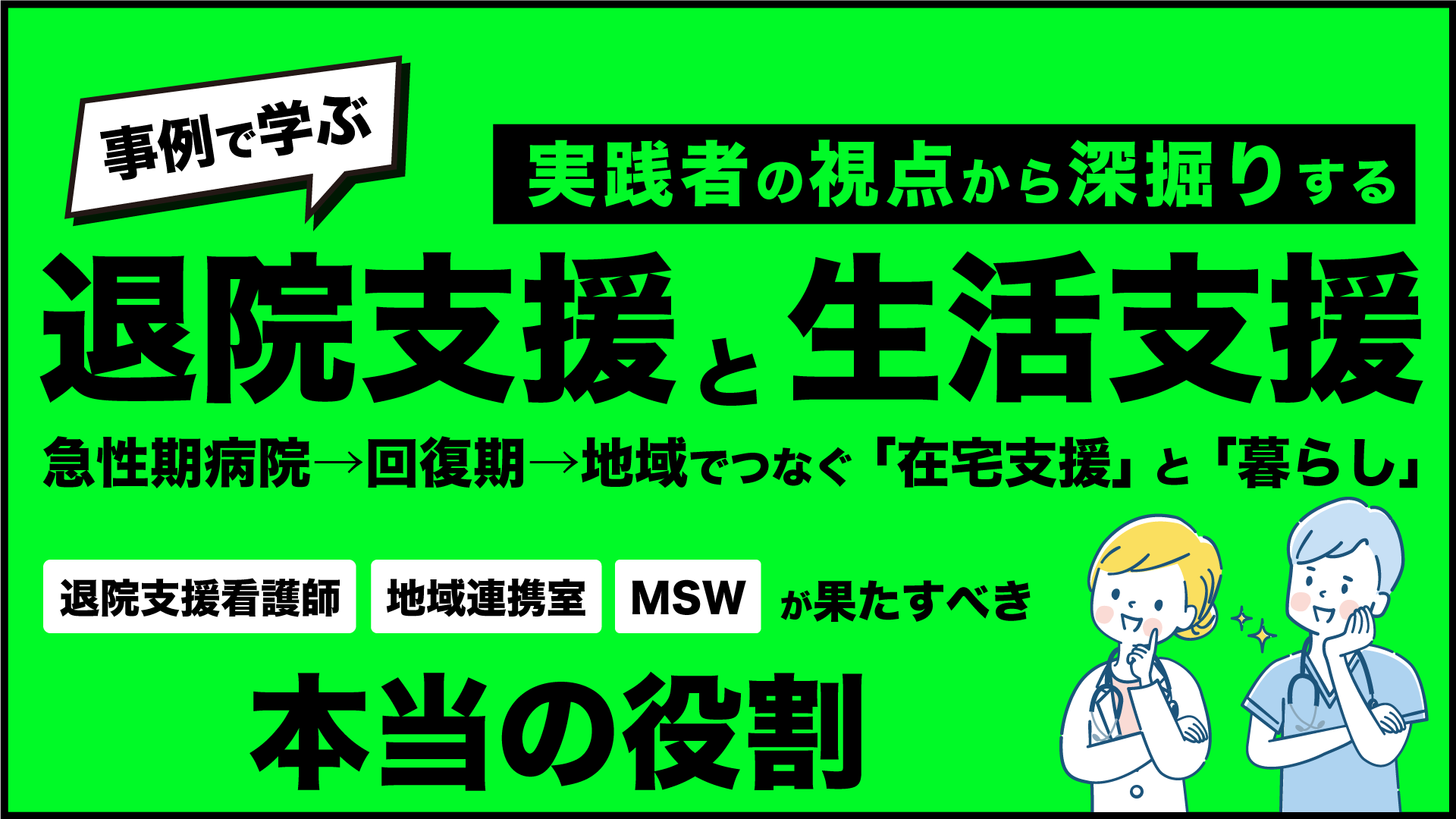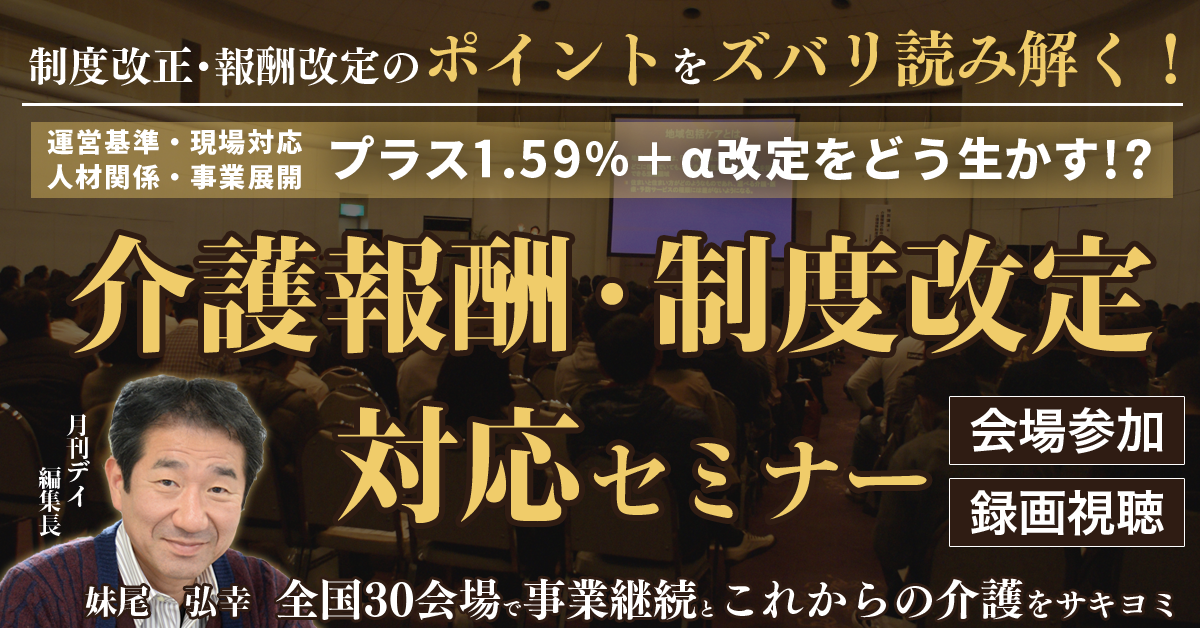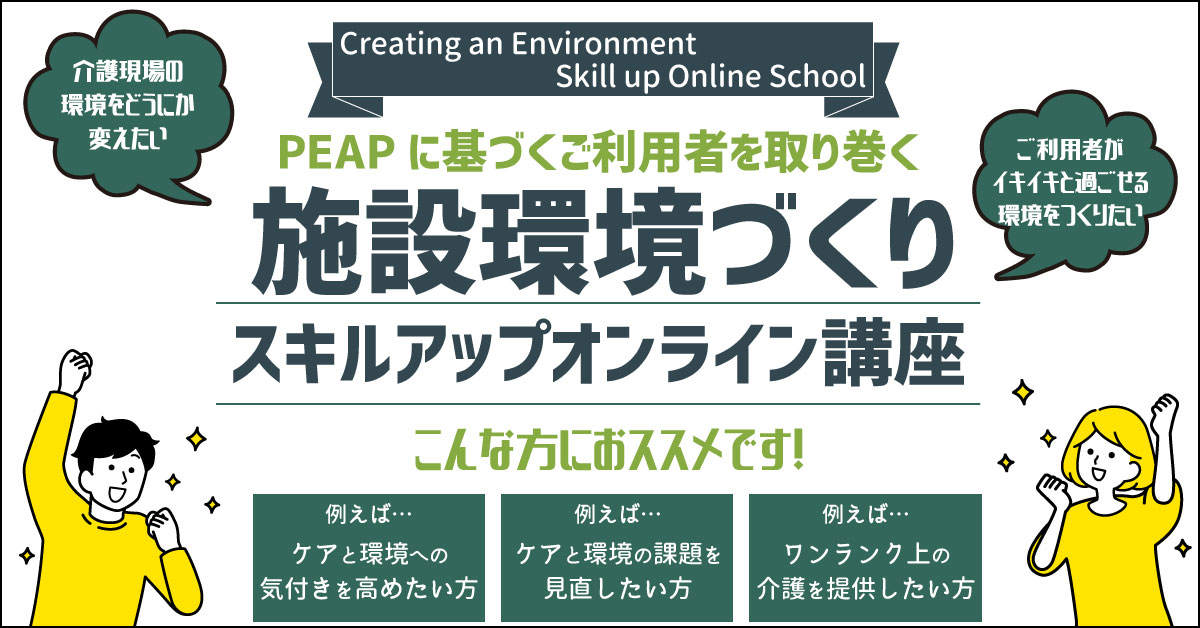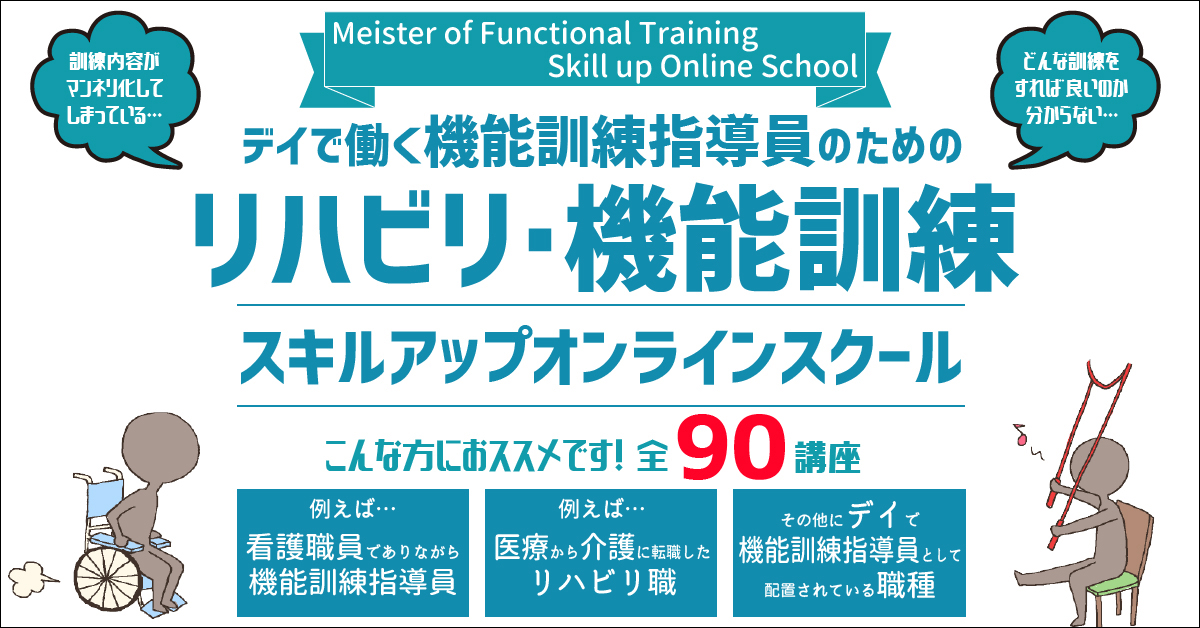厚生労働省は、2026年度の診療報酬改定に向けて、訪問看護の過剰提供に対する規制を強化する方針を2025年10月1日に打ち出しました。
背景には、有料老人ホームやホスピス型施設などで「必要性に乏しい頻回訪問」が行われ、不正な診療報酬請求が疑われるケースが増えていることがあります。
中には、実際のケアというよりも「見守り」に近い短時間訪問を繰り返したり、報酬が高くなる時間帯(早朝・夜間)を狙って訪問を設定するなどの事例も指摘されています。
こうした構造的なグレーゾーンを是正しようというのが、今回の動きです。
どんなルール改定が想定されているのか?
厚労省が示した方向性は次の通りです。
「主治医が訪問看護指示書に必要性を具体的に明記している場合に限り、頻回な訪問を認める」
つまり、これまでのように「指示書さえあれば何回でもOK」ではなくなるということです。
指示書に「なぜ頻回の訪問が必要なのか」「どんなケアを想定しているのか」を明確に記載されていることが求められます。
「必要性」の線引きが課題に
ただし、現場からは次のような声も上がっています。
「指示書の必要性なんて、病名やADLからいくらでも書ける」
「訪問側からこう書いてくださいと指示書案を送られることもある」
「結局、主治医と事業者が合意すれば形だけ整ってしまうのでは」
現状でも、形式的に必要性ありと記載されていれば報酬請求できてしまうケースが少なくありません。
そのため、「本当に実効性のある規制になるのか?」という懸念が挙がっています。
一方で、「必要な訪問が制限されるのでは」という不安も
神経難病、終末期など、1日の中で複数回の訪問がどうしても必要なケースもあります。
疼痛コントロール、酸素管理、緊急時対応などこれらは訪問看護がなければ安全な生活が維持できません。
「規制強化」という言葉だけが独り歩きすると、必要な医療まで削られてしまうのではないかという現場の不安も理解できます。 本当に大事なのは、「不正を防ぎながら、必要なケアは守る」その線引きを明確にすることです。
囲い込み構造も見直しの焦点に
もう一つ問題視されているのが、有料老人ホームやサ高住における事業者間の囲い込みです。
「入居と同時に「訪問看護・訪問診療・薬局」がセットで紹介される」
「入居前のケアマネや訪問介護を続けたくても、「施設指定の事業所しか使えない」とされる」
こうした「パッケージ化」は、利用者や家族がサービスを選ぶ自由を奪うだけでなく、事業者間の不正温床にもつながります。
2026年度改定では、この囲い込み構造の是正も議論される可能性があります。
【お役立ち研修】
医療・介護の現場で活かせる実践的リハビリ評価&介入セミナー
第23回日本通所ケア研究大会
https://tsuusho.com/conference/